「モジュール学習」とは?【知っておきたい教育用語】
現行の学習指導要領では、各学校ごとの授業時間を弾力的に設定、運用することが容易になりました。そこで注目されているのがモジュール学習です。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
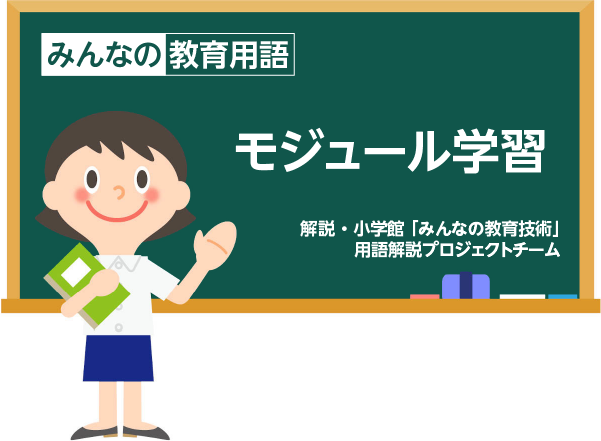
目次
柔軟な授業時間の設定とモジュール学習
【モジュール学習】
10分~15分程度の短い時間を単位として、繰り返し教科指導などを行う短時間学習のこと。「帯学習」と呼ばれることもある。基本的な知識やスキルを身につけるための反復学習などにおいて導入が進められ、その効果が認められている。
現行の学習指導要領では、各教科等で求められている年間授業時数の確保を条件として、具体的な授業の1単位時間を定められることになっています。小学校における標準的な1単位時間は45分ですが、このことにこだわらず、1単位時間を何分にするかを決めることができるということです。
学習指導要領には、以下のように記されています。
授業の1単位時間すなわち日常の授業の1コマを何分にするかについては,児童の学習についての集中力や持続力,指導内容のまとまり,学習活動の内容等を考慮して,どの程度が最も指導の効果を上げ得るかという観点から決定する必要がある。
文部科学省(PDF)「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編」平成29年7月
こうしたことから、短い時間で行う「モジュール学習」が可能になりました。ただし、モジュール学習では、45分間で行うよりも、より効果があると想定される必要があります。例えば、道徳などの時間を10分で行うことを妥当とは考えられていません。一方、計算や漢字の反復学習においては、10分~15分のモジュール学習の導入が進められています。こうした基礎的な学習に加え、語学(英語)学習をモジュール学習として行うことも奨励されるようになりました。
具体的なモジュール学習の展開としては、週に3回、15分授業を行ったり、45分の授業に15分間を繋げて60分にしたり、45分授業との関連を明確にしたうえで別の時間枠として15分の学習を設けたりすることなどが考えられます。
モジュール学習の実際
国立教育政策研究所は、モジュール学習の特徴ある取組として以下のような事例を紹介しています(一部、内容を抜粋して紹介)。
事例① 15分×3のモジュール学習「集中タイム」の導入
●毎週3回1時間目を「集中タイム」とし、45分間の授業を15分間ずつ3つのモジュールに分割して基礎的な学習内容を取扱う授業とする。(授業時数の計算にあたっては、3回で1単位時間と計算)
●1モジュール(15分)を、さらに短い5分〜10分程度のプログラム(活動)の組み合わせによって構成する。
●発声練習・音読・フラッシュカードを使った学習など、大きな声を出したり、素早く反応したりすることにより脳の活性化をねらう。
●読む・書くなどの反復練習により、学習の定着をめざす。
●リズムよく、集中して実施するため、あらかじめ板書の内容を紙でつくっておくとともに、教具などの配付にも手間がかからないように準備しておく。
●教員の指示は、できるだけ少なく短くするように努める。
●子どもの集中力を維持するため、同じような内容を連続させず、学習に変化をもたせる(例:モジュール1は国語、モジュール2は算数、モジュール3は学年で決めたさまざまな教科の内容を取扱うなど)。
事例② 朝のチャレンジタイム ~みんなで統一した取組を~
●火曜日の朝タイム(15分間)を使い、基礎的な計算問題(実施5分、答え合わせ5分、カード記入等5分)に取り組む。
●問題は当面「10の合成」「くり上がり・くり下がりのある足し算、引き算」「100マス九九」とし、問題プリントは表計算ソフトを使って自動生成する。
●子どもに「個人カード」を持たせ、得点とタイム、コメントを記入させる。
●5回ごとに総括し、その効果や問題点・改善点について話し合いながら進める。
以上のように、モジュール学習は工夫次第で多彩な学習の取組を実践することができます。実践のポイントとして、子どもたちの集中力を途切れさせず、継続して行えるような取組をめざしましょう。

