大人と子どもの権利保障はどう違う?学校における子どもの権利の保障~シリーズ「実践教育法規」~
- 連載
- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第28回は「学校における子どもの権利の保障」について。教育を受ける権利が制度上保障されていることはもちろんのこと、子どもが学校の校則に対して意見を表明する機会を確保することなども求められています。
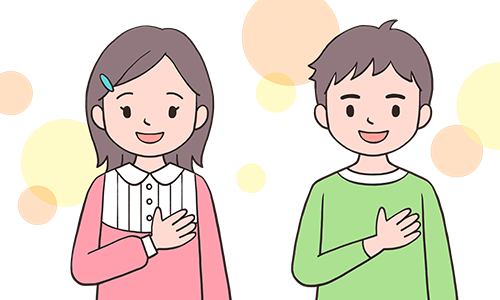
執筆/栗原 真孝(鹿児島純心大学人間教育学部准教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#28
目次
子どもの尊厳に基づいて人権が尊重される
日本国憲法第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される」と定められており、大人だけではなく、子どもも個人として尊重される存在として位置づけられています。また、憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」と定められており、大人だけではなく、子どもも人権の享有主体として位置づけられています。人権は個人の尊厳に基づいて尊重されるため、学校においてもそれぞれの子どもの尊厳に基づいて人権が尊重されなければなりません。
その上で、憲法第26条1項に規定されている教育を受ける権利は、子どもだけの権利ではないものの、学校における子どもの権利の中で代表的な権利と言えます。教育を受ける権利は、現在は学習権を中心にして理解されています。1976年の旭川学力テスト事件の最高裁判所の判決では、「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」と示されています(最高裁大法廷判決昭和51年5月21日刑事判例集30巻5号615頁)。
こうした中で、学校において体罰が発生した場合は、子どもの教育を受ける権利の保障を妨げる問題と言えます。体罰は学校教育法第11条で禁止されており、教員による体罰や不適切な指導によって、子どもの教育を受ける権利の保障が妨げられてはなりません。

