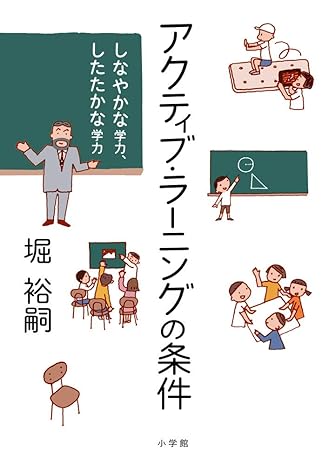【連載】堀 裕嗣 なら、ここまでやる! 国語科の教材研究と授業デザイン ♯2 私はなぜ、「教育技術の法則化運動」に参加しなかったのか?~「文脈」を読む力について・その2~

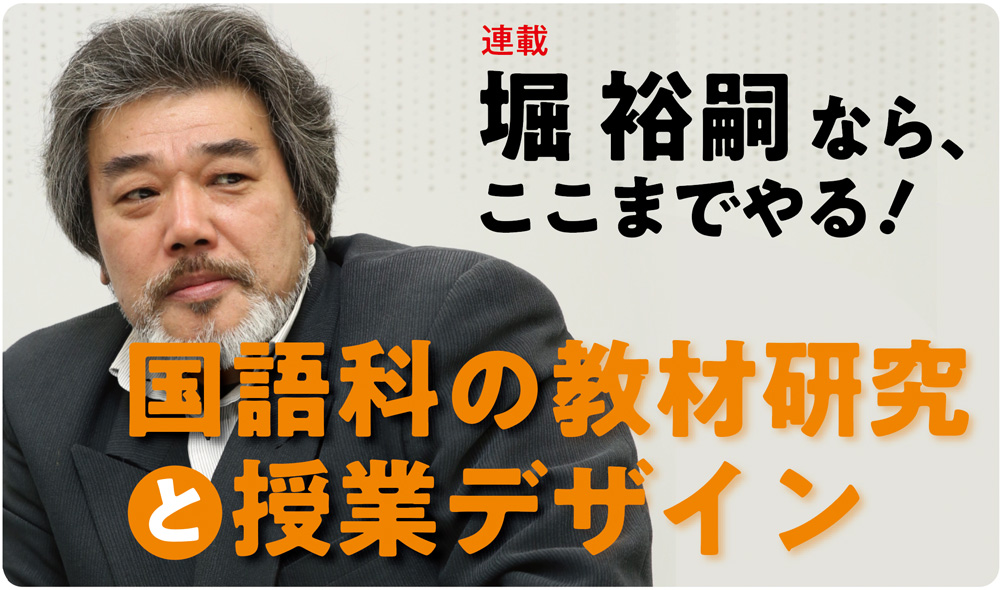
国語科・道徳科において、確固たる理論的裏付けに基づくクリエイティブな教材開発、教材研究、授業実践に定評のある堀 裕嗣先生の新連載第2回。史上最大の教育運動「教育技術の法則化運動」に遂に参加しなかった理由から書き起こし、前回同様、ディテールにこだわりつつ「文脈」を読む力について考えていきます。
目次
1.法則化運動は過去のものではない?
安西冬衛に「春」(『軍艦茉莉』1929年)と題された一行詩がある。
てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた。
かつて向山洋一が「一文で1時間の授業をつくる」際の代表例として、或いは「視点の授業×討論の授業」の代表例としてこの詩を盛んに取り上げていたので、年配の読者には懐かしさを感じる者もいるかもしれない(『斎藤喜博を追って』向山洋一・昌平社・1979年・他)。いずれにしても、80年代半ばから90年代にかけて、法則化運動の参加者ならずとも、この詩を用いて授業した経験を持つ者は多いだろう。
私が教職に就いたのは1991年のことだが、当時は「教育技術の法則化運動」が隆盛を極めていた。若手中堅の読者は、「TOSS」運動に参加する教師でない限り、既に向山洋一には馴染みがないかもしれないが、いまなお精力的に講演活動を続け、この「みんなの教育技術」でも盛んに発信を続けている野口芳宏、その死後もなお継承者たちが影響下にある実践を盛んに全国発信し続けている有田和正、全国の児童絵画の質を大転換させてしまったと評される酒井臣吾など、「教育技術の法則化運動」はいまなお教育界に多大な影響を与えている。それどころか、現在五十代以上の教育研究者・実践者において、法則化運動に影響を受けていない者(反面教師として機能させた者も含めて)はほぼ皆無だろうと思う。いや、ネット上に掲載される実践報告を参考に授業づくりをしている現在の若手教師たちでさえ、多くの者たちがそうと知らずに多大な影響を受けているはずだ。いずれにせよ、「教育技術の法則化運動」が歴史上、最も大きな教育運動であったことは誰もが認めるところである。
1991年に教職に就いた私の周りには、法則化に参加する教師たちがたくさんいた。札幌にも法則化サークルが複数あり、盛んに例会や公開研究会が行われていた。インターネットが普及していない時代、学校には法則化セミナーの案内ちらしが毎週のように配布されたものである。法則化関連の刊行物の数たるや、当時は月十冊を下ったことはなかったのではないか。それほどの勢いだった。
しかし、私はそれなりの影響を受けながらも、遂に「教育技術の法則化運動」に与することはなかった。書籍はおそらく数百冊読んだと思う。情報を集めるために雑誌も定期購読していた。向山洋一の毎月の動向も関心をもって読んでいた。法則化運動に参加する教師たちとの交流もあった。しかし、最後までいわゆる「看板を担ぐこと」はなかったのである。
実は、その要因となったのが安西冬衛の「春」の授業だった。
2.視点って物理的?心理的?
作者安西冬衛の略歴や、この詩の成立した背景などはここでは措こう。私が当時、違和感を覚えたのは向山洋一の「視点」の扱い方だった。
言うまでもなく、「視点論」は我が国の国語教育界では「西郷文芸学」の支柱の一つである。いまでは教科書でさえ手引きで中心的に扱われるようになったが、この流れをつくったのは間違いなく、西郷竹彦に影響を受けた「法則化分析批評」を中心とした各種分析批評実践、「科学的『読み』の授業研究会」を中心としたいわゆる「読み研」実践、そしてこれらを統括する形で盛んに「視点」を議論し続けた「言語技術教育学会」あってのものである。また、それとミックスする形で「全国大学国語教育学会」に参加する研究者の視点論研究や文体研究、「日本文学協会国語教育部会」の語り手研究の功績も無視できない。いずれにせよ、これらを国語教育界で一般化した功績のオリジンは西郷竹彦にある。
さて、向山洋一の「春」の授業は、ごくごく簡単に言うなら、「視点」を「Point of View」としてのみ押さえていた。韃靼海峡の側面図を描き、飛んでいる蝶を描き、話者の視点の位置として「目」を描く。もちろん子どもによって目の位置が割れる。それを論拠とともに討論させるという構成を採っていた。授業終盤になっても合意形成を図ることは意図されず、活発な議論が展開され、「意見と理由」「主張と根拠」を「討論の授業」の中で定着させようとする試みである。中には最後まで「解」のない授業にアナーキズム型授業である、放牧型授業であるとの批判もあったが、私はそこには違和感を抱かなかった。あくまで、「視点」を「Point of View」として、つまりは物理的な位置づけとして捉えていたところに違和感を抱いたのである。
西郷竹彦は「視点」を、形象理論の延長として捉えていた(「形象」とは語り手や登場人物になりきり、まるでその場にいるような臨場感をもって読むことと捉えていただけれれば良い。若い読者にはテレビ画面を見るのではなく、ゴーグルをつけてVRで見ているとでも想像していただけれればわかりやすいかもしれない)。つまり、「視点」を「Point of View」としてのみならず、視点人物の、或いは話者の、或いは語り手のその描写瞬間の精神性までを包含して「視点」と呼んでいたのである(『西郷竹彦文芸・教育全集14 視点・形象・構造』西郷竹彦・恒文社 ・1998・他)。学生時代から「西郷文芸学」に大きく影響を受けていた私には、この向山洋一の「視点」の捉え方が許せなかった。現象的な子どもたちの討論の活発さや、意見と理由をセットで発言するという「話すこと・聞くこと」領域の指導のために、「視点論」の根幹を蔑ろにしている。他の目的のために「読むこと」の指導自体を放棄している。そんな風に当時の私には見えたのである。
3.助動詞が作品世界をつくる?
前回、「文脈」について大まかに述べた。今回はその2回目である。
堀 裕嗣 先生のご著書、好評発売中です!
↓「スクールカーストの正体ーキレイゴト抜きのいじめ対応―」
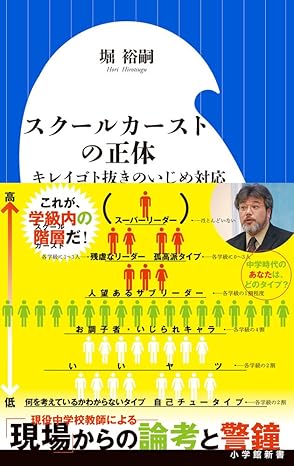
↓「アクティブ・ラーニングの条件ーしなやかな学力、したたかな学力-」