短時間で効果的な「朝の会・帰りの会」の進め方【主体的に生きる力を育む学級経営の極意⑤】

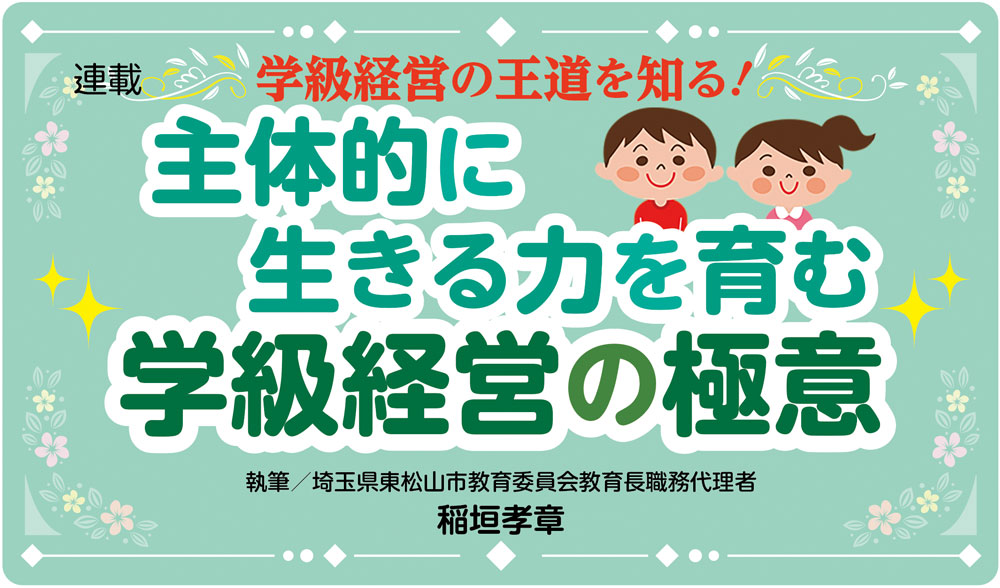
子供たちが多様な他者と関わりながら社会につながり、主体的に生きる力を育んでいくために、教師はどのような学級経営をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて基礎基本を解説します。第5回は、「朝の会・帰りの会」の設定法について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「朝の会・帰りの会」の活動は、学級経営の基盤とも言えます。この時間の子供たちの様子を見れば、そのクラスの学級経営がわかるとも言われます。「朝の会」は、一日の学校生活のスタートとなるものであり、「帰りの会」は、一日の学校生活のまとめをする時間です。「朝の会・帰りの会」の特質を踏まえ、「朝の会の特質」「帰りの会の特質」「実践上の配慮事項」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 朝の会の特質
「朝の会」は一日の学校生活のスタートとなる大切な時間です。朝の「挨拶」の仕方でスタートの気分も変わってきます。子供たちは教師の表情をよく見ています。まずは、教師が笑顔で挨拶をしましょう。
「朝の会」は、歌を歌ったり、係からの連絡等も取り入れたりしたいところですが、定められた時間で効率よく進めなければなりません。そのため、教師からの連絡を短時間で明確な話として行うことが求められます。あらかじめ、連絡事項は項目立てをして掲示するなどの手立てを講じていくことも考慮していきましょう。
「健康観察」は聞き合う指導の根幹です
「健康観察」は、「聞き合い」としての思いやりの行為を体現する時間でもあります。クラスの友達の健康状態をよく聞くことによって、グループ等での活動上の対応も変わってくることがあります。体調がすぐれない友達に対して、掃除や給食等の時間の配慮も考えられます。まずは、友達の健康状態を一言も聞き漏らさないことの意義を指導し、誰もが相手への思いやりの行為として、「健康観察」は「聞き合い」の大切な時間であることを根気強く指導していきましょう。

CHECK② 帰りの会の特質
「帰りの会」も下校時刻等の関係から時間は限られています。一日の振り返りや係からの連絡等の活動を取り入れることは効果的ですが、短時間で進行ができるように指導していくことが求められます。
「帰りの会」は、一日の学校生活を振り返り、成果と課題を見いだす時間です。特に、気を付けたいのが、「今日の反省」と称して、友達への苦情や批判の言葉を言い合う時間ではないということです。友達の行動を「判決台」に上げるのではなく、「表彰台」に上げるという認識で進めて行くことが大切です。
翌日への期待感を高める時間にします
「帰りの会」で、友達から注意を受けたり、うまくできなかった行動等を批判されたりすると、翌日の学校生活への期待感は薄れてしまい、登校への希望さえ失ってしまうことがあります。「帰りの会」は、互いに認め、称賛し合う活動を展開し、翌日への期待感を高める時間であることを再確認しましょう。
CHECK③ 実践上の配慮事項
「朝の会・帰りの会」には、教師の教育理念が表れます。短時間であることから単に、連絡事項の伝達に終わることなく、子供たちの自主的な活動を効果的に取り入れていくことが求められます。具体的には、次のような視点を踏まえていきましょう。
①成果を取り上げる場合は、個人だけでなく、グループや学級集団としての視点も取り入れ、特定の子供だけを取り上げないようにします。
②課題を取り上げる場合は、個人攻撃とならないことを前提とし、次の活動に向けた改善策を中心に取り上げるようにします。
③短時間でも係活動等の連絡、調整の時間を確保し、子供には簡潔に発表できるように根気強く指導します。
④教師の連絡事項は、ホワイトボード等に事前に書いておいたり、高学年からは中学校に向けて聴写できるようにしたりします。
⑤教師の連絡や説話は、視点を明確にし、見通しをもって計画的に行います。
どの子供も活躍できる場面を設定します
「帰りの会」で、「今日のMVP」といった活動を取り入れているクラスが散見します。一部の子供だけが称賛されるような活動にするのではなく、「今日の日直のよかったところ」等のように、どの子供も称賛されるような手立てを講じていきましょう。
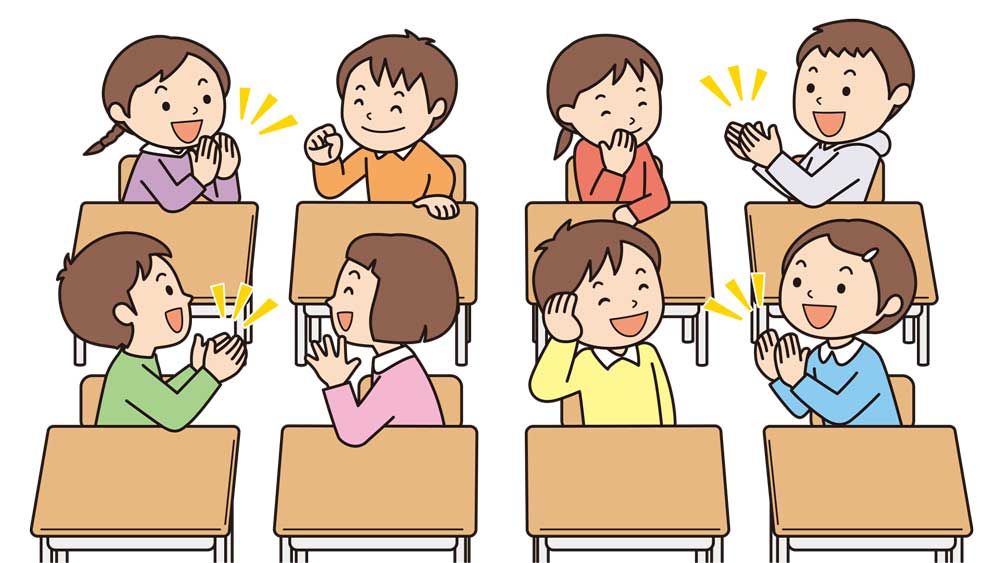
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

