希望と目標をもって生きる態度を育む 「学級目標」の設定法【主体的に生きる力を育む学級経営の極意②】

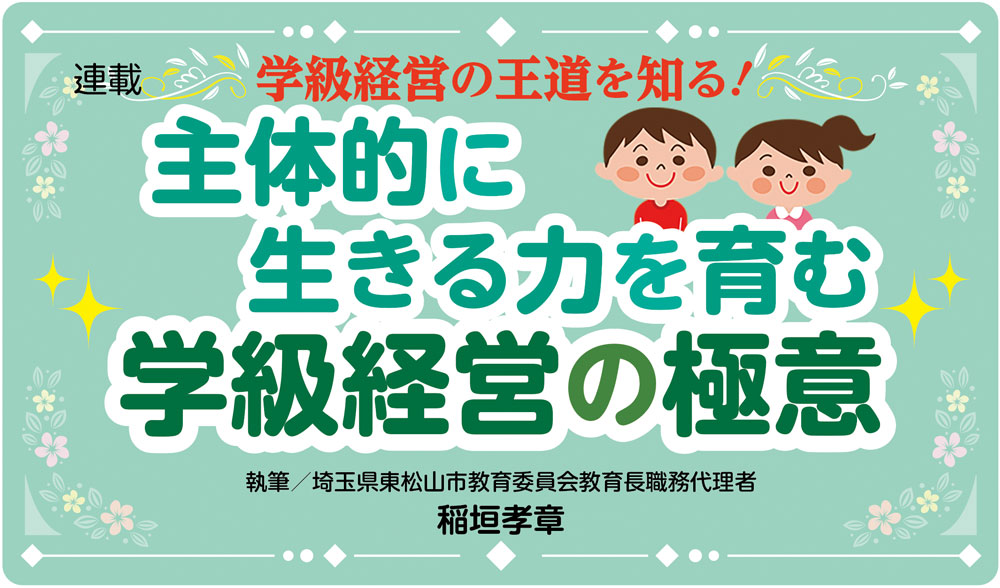
子供たちが多様な他者と関わりながら社会につながり、主体的に生きる力を育んでいくために、教師はどのような学級経営をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて基礎基本を解説します。第2回は、「学級目標」の設定のポイントについてです。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
学級目標は1年間の学級経営の基盤です。しかし、その設定の仕方は、各担任に任せられているという現状が散見します。学級目標には、基本的な設定の手順があります。次の3つのキーワード「学校教育目標との関連」「教師・子供・保護者の願い」「設定に当たっての配慮事項」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 学校教育目標との関連
教育基本法第1条(教育の目的)に、「教育は、人格の完成を目指し……」という文言があります。この原理原則を踏まえ、「学校教育目標」は、人格の構成要素である「知育・徳育・体育」の視点で設定されていると思います。まずは、「学級目標」は、「学校教育目標」を受けて設定するという認識をもつことからスタートします。
学校での教育活動は、「学校教育目標」の実現を目指して行われます。各学級では、子供たちの実態に即して、「学校教育目標」の実現を目指して「学級目標」を設定します。ゆえに、「学級目標」も単なる合言葉のような文言ではなく、「知育・徳育・体育」の視点で設定するようにしましょう。
「学級目標」は「知育・徳育・体育」の視点で「教師が設定」します
「一人はみんなのために、みんなは一人のために」「団結」「輝く3・さん・三組」など、教師の思いや子供たちの考えを生かした様々な学級目標が散見します。しかし、このようなキャッチフレーズは、学校教育目標を受けた適切な学級目標とは言えません。
「学級目標」は、「学校教育目標」を受けて「知育(頭づくり)・徳育(心づくり)・体育(体づくり)」の視点で、教師が年度当初に設定します。この3つの視点で設定された「学級目標」をもとに、子供たち一人一人が個人としての具体的な「達成目標(行動目標)」を設定できるようにしていきましょう。
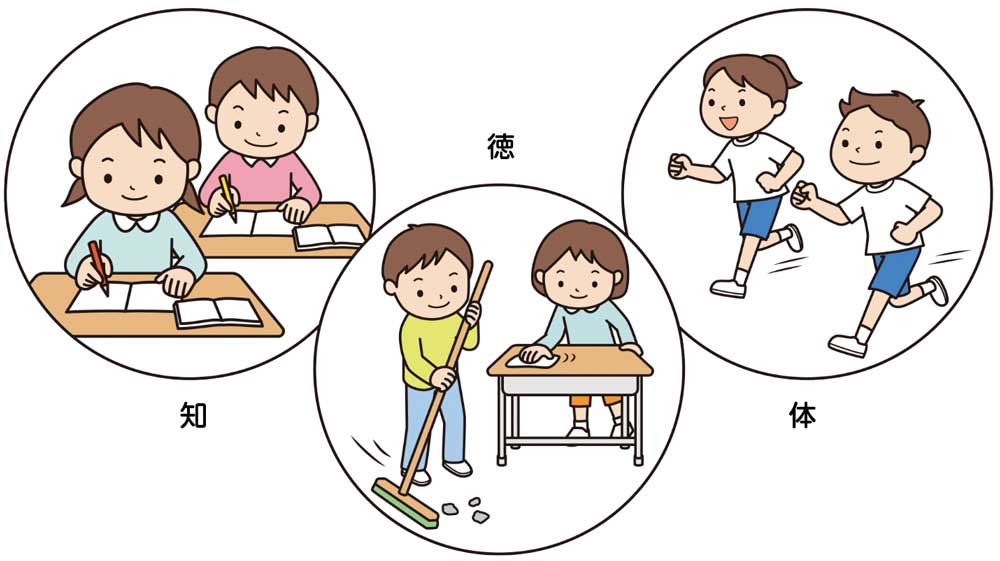
CHECK② 教師・子供・保護者の願い
「学級目標」は、学級会などを活用して、子供たちの話合いで決めるという方法は適切ではありません。「学級目標」には、「教師の思い」「子供の思い」「保護者の願い」を盛り込んで、「教師が適切に設定」していくことが大切です。
特に、「保護者の願い」を取り上げるためには、年度当初、保護者に「どのような子供に育ってほしいか」という簡単なアンケート調査を実施するようにしていきましょう。
「学級目標」は目指す子供の姿で示します
「学級目標」は、教師の学級経営の基盤です。その手順としては、まず「教師の思い」を明確にして子供たちに提示します。次に、「子供の思い」を取り上げるため、「こんな〇年生になりたい」という個々の思いを集約します。さらに、「保護者の願い」を集計して、三者の思いや願いを集約して「教師が学級目標を設定」します。
具体的な「学級目標」を設定する際の文言は、「目指す子供の姿」を「知育・徳育・体育」の3つの視点で取り上げるようにしましょう。

CHECK③ 設定に当たっての配慮事項
「学級目標」と「クラスの合言葉やキャッチフレーズ」などが混在している学級の実践が散見されます。まずは、「学級目標」は、「学校教育目標」を受けて設定することが基本です。また、設定の時期は、年度当初の早い段階に行い、学級活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」の授業で、個人目標を行動目標として意思決定できるようにすることが求められます。
「学級目標」は「~の子」という文末表現にします
「学級目標」の文末表現は、「~のクラス」という集団づくりを主とするのではなく、「個を生かす集団活動」を展開するという理念が基盤です。そのため、「知育・徳育・体育」の視点で、目指す子供の姿として「~の子」という文末表現にすることが基本です。
「学級目標」は、1年間の学級経営の中核です。設定した「学級目標」の実現を目指して、子供たちの学級生活の指針となるように指導し、学級・学校生活に対して希望や目標をもって生きる態度が高まるようにしていきましょう。
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

