「年度末に向けて再設定した目標を達成しよう」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #10

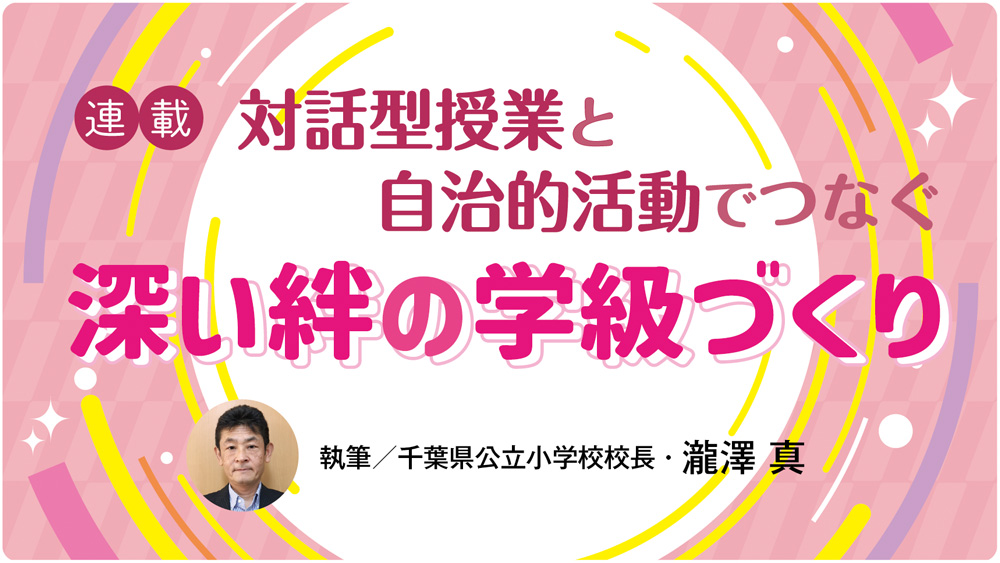
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第10回は、年度末に向けて、目標を再設定し、それに向かってがんばることでクラスの絆を深める活動について解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
年度末に向けてラストスパート
今年もいよいよ終わりが近付いてきました。そして、年が明ければ、学年末までもうすぐです。
そこで、ラストスパートとして目標を再設定し、それを達成することで、子供が成長し、クラスの絆も深まる取組を紹介します。
再設定した個人目標を達成しよう

多くの学級では、4月に個人目標を設定していると思いますが、すでに達成していたり、到底達成できない状況だったり、ということはないでしょうか。
そこで、一人一人が年度末までに達成したい目標を再設定します。
4月の目標と関係ないものでもかまいません。今の自分にとって絶対に達成したいと思うようなものを決めてもらいます。
ただし、簡単に達成できるような目標では意味がないし、絶対に達成できないようなものでもだめです。少しがんばれば達成できそうな目標を立てるように助言します。
そのために、仮の目標を書いたら、一度教師に提出してもらい、それをもとに難易度について子供と教師で話し合います。
例えば、二重跳びが10回できる子が、11回跳びたいというのは簡単すぎますが、100回では多すぎます。ではどのくらいがいいのか、その調整をします。
とはいえ、最終的には子供自身が決めます。教師は助言はするけれど、自分のことは自分で責任をもつのです。
全員の目標が決まったら、それを一覧にして掲示します。
そして、7割の子が自身の目標を達成したら、お祝いをします。牛乳で乾杯するくらいでもいいでしょう。
すると、残り3割の子もがんばろうと思うでしょう。そこで、まだ達成していない子を支援してくれる子を募ります。
先の例で、二重跳び20回を目標にして、15回まではできるようになったとします。あと5回、どうしたらできるのか一緒に考えたり練習したりする子に集まってもらうのです。

ただし、支援されることを嫌う子もいるでしょう。そんな場合は、無理に支援してはいけないというルールをつくっておきます。だれにも助けられたくないという子の考えも尊重します。
でも、多くの子は手伝ってもらってありがたく思うものです。そうやって助け合いながら、9割の子が目標を達成したら、少し長めのレクをやるとよいでしょう。「目標達成パーティー」などとネーミングすると盛り上がります。
ここでのポイントは、10割を目指さないということです。
全員達成を目指すと苦しくなってしまう子がいるかもしれません。達成できると思ったのにできないこともありますよね。また、10割を目指すと、達成できない子を責めるような雰囲気も出てしまうかもしれません。
それでは、絆どころではありません。そこで、9割の達成者が出たら、全体としての取組は終了します。あとは個人的にがんばろうねと声をかけ、掲示物も取ってしまいましょう。

