日本を離れ派遣教師として子どもを教えるということ~フランス・パリより~
世界には在外教育施設派遣教師として、異国の日本人学校で教壇に立つ先生方が数多くいます。なぜ日本人学校の教師に? 赴任先の教育現場はどんな感じ? 日本の教育事情との違いは? ここでは、現地で活躍している先生の日々の様子をお伝えします。今回登場するのは、2015~2017年フランス・パリ日本人学校に勤務していた師尾勇生先生。海外で教職の研さんを積みたいと考えているあなたへ、先輩教師からのメッセージです。
執筆/東京都公立小学校教諭(元パリ日本人学校教諭)・師尾勇生
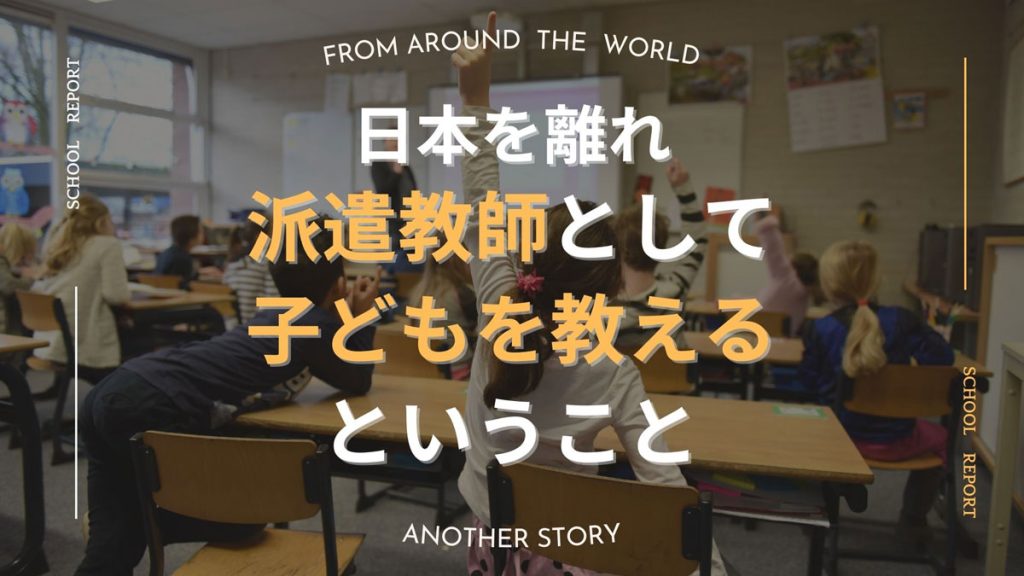
目次
背中を追いかけたい先輩たちは派遣教師の経験者だった
私が派遣教師を目指した理由は2つあります。その1つめは「在外教育施設派遣は教師の魅力を増幅させる」と感じたからです。
初任校では日本人学校に派遣経験のある九貫政博先生という先輩に出会いました。九貫先生はとても魅力的な方で教育観、授業観、児童との関わり方など、どこをとっても尊敬できる点ばかりでした。楽しそうに子どもたちの笑顔に囲まれているときもあれば、熱く指導をする強さもありました。どの子にも真剣に向き合い、とくに先輩が作成した通知表の所見の表現力は圧巻で、一人ひとりの良さを文学のように多彩な表現力で的確にあたたかく表現していました。
勤務外でも働き方や休暇の過ごし方、人生観などを居酒屋で語ったり、日本人学校でのエピソードもいろいろ教えてくれたりしました。日本国内ではできないような経験談が次から次へと出てくるので、派遣教師というのは人生経験がとても豊かになるのだなと強く感じました。
その後も「素敵な先生だな、見習いたい」と私が思った先輩方は、「日本人学校派遣経験あり」という共通点がありました。そしていつしか「日本人学校での経験は教師を魅力的にする」という確信に変わっていき、在外教育施設派遣を目指すようになりました。
理由の2つめは、体験入学に来た海外在住児童を指導した経験からです。海外では6月末から夏休みに入る学校が多く、そのタイミングを生かして日本の学校で学ぶ「体験入学」というものがあります。海外在住で日本にルーツのある子が日本の教育を体験するというものです。
私の初任校では、当時、海外から一時帰国した児童の体験入学を受け入れていました。7月の2週間ほど、毎年数名が体験入学をしていました。私のクラスにも1人、体験入学の児童が入りました。その子への指導を通じて、私は、こちらの言葉がうまく伝わらない子への指導の難しさを知るとともに、伝えたいことが伝わるうれしさを感じました。
また、私が子供の頃、貿易関係の仕事をしていた父親がよく海外に単身赴任をしていました。今思うと、「海外で仕事をする」ということが身近で、心の奥底で「海外で働くのもいいな」と思っていたのかもしれません。
このような理由から派遣教師への準備をすすめました。そんなとき、先輩から「東京都海外子女教育・グローバル教育研究会」という、東京都から認可されている教育研究団体を教えてもらいました。その研究会の方々は、全員日本人学校から帰国された先生たちでした。研究会に参加するたびに、様々な国での教育実践を聞いて毎回エネルギーをもらったり、どのような人材が日本人学校で求められるのかなどのお話が聞けたりしました。面接の練習などもしてもらい、試験本番に備えることができました。
教師であり、日本人学校に通う娘の保護者でもあり
私が派遣していたパリ日本人学校への交通手段は、日本ではあまりなじみのない“キックスケーター”を利用していました。だいたい15分くらいかけて通勤するのですが、冬は8時にならないと陽が昇らないので、暗いなか通勤していました。夏はカラッと湿度もなく気持ちのよい気候で、街中で咲き誇る美しい花壇を見ながらのキックスケーター通勤は、とても有意義な時間でした。
同僚の先生方は車通勤の人が多く、私も自動車で通勤もできたのですが、あえてキックスケーターで通っていました。というのも、娘が私と同じ日本人学校に通っていたので、家の車は娘の送り迎えに妻が使っていたからです。娘のお迎えのときにはキックスケーターを車に積み込み、私も一緒に乗って帰れるので、とても便利でした。
娘と校内ですれ違うときは「こんにちは」と、普通の教師と児童のように関わります。慣れるまでは少し寂しい感じがするなと思っていましたが、家で娘から「お父さんがこのような仕事をしていた」などの話が出ると、少しくすぐったくもうれしい気持ちになりました。毎日の仕事をしている様子を自分の子供に見せるという貴重な経験ができたと思います。
また、娘が友達と休み時間に楽しそうに活動をしていたり、運動会などの行事に向かって成長を重ねたりするのを見ることができたのは、とても喜ばしいものでした。とくに小学部では、運動会の表現演技を2学年合同でやっていたので、自分が2学年を指導する中に娘がいるということもありました。その時期は家でも一緒にダンスを練習するなど、家でもブラッシュアップしていったのを覚えています。
クリエイティブで知的好奇心の強い子どもたち
派遣校では小学部1年生、6年生、5年生を担任しました。研究主任も担当していました。どの子どもたちも「優しい」「クリエイティブ」「知的好奇心が強い」の3つの魅力を持ち合せていると感じました。
「優しい」の背景にあるのは、出会いと別れが多いことです。他の日本人学校もそうですが、転入・転出がとても多いので、一緒にいられる時間を大切にし、友達も大切にするという印象があります。
物理的な要因で日本と同じようなことができないとき、そこにある材料や道具だけで工夫するなど「クリエイティブ」な発想が生まれます。印象的だったのが「流しそうめん」です。家庭科と図工、総合的な学習の時間として、ペットボトルを切ったりつなげたりして作った流しそうめんをみんなで食べたのは、忘れられない思い出になっています。
「知的好奇心が強い」というのは、教科書の内容を深掘りした質問などが多かったことです。小学校6年生の歴史の学習では、教科書にも資料集にも載っていない事柄を話し合う機会を設けたら、反応が良かったのを覚えています。子どもたちの期待に応えられるような教材研究をするのは骨が折れましたが、できるかぎり努力しました。
また、ひとつの行事を作り上げるのにも時間がかかりました。なぜなら「補教(いつもと違う先生が授業をすること)」や「実踏(遠足の下見をする実地踏査の略)」という言葉が、様々な自治体から派遣されている先生方には通じなかったからです。これまで当たり前に使っていた言葉が通じないもどかしさを感じましたが、職員室で話し合う時間を増やし、コミュニケーションを丁寧にとって解決していけるようにしました。
めったに経験できない“ヴェルサイユ庭園でのウォークラリー”
パリ日本人学校らしい行事といえば全校遠足です。小学部の全児童でヴェルサイユ庭園に行きます。ヴェルサイユ庭園ではたて割班でウォークラリーアドベンチャーを行いました。これは庭園の中の銅像、噴水、広場などの各ポイントに先生たちが待機。先生たちが待つポイントに子どもたちが来ると、先生がお題であるアクティビティ「新聞紙にグループ全員がのって10秒数える」「グループの誰かが先生とじゃんけんをして3回勝つ」などのお題を出し、これをクリアするとキーワードがもらえるという形式のウォークラリーでした。
ウォークラリーの後はお弁当です。庭園内の芝生に120名ほどの小学生がレジャーシートを敷いてお弁当を食べているのは、現地の人にとっては珍しいらしく、質問されたり写真を撮られたりすることもありました。
午後は芝生広場に集まり、班ごとに遊びました。フランスでは子どもが1人で外出することが禁止されており、公園に遊びに行くのも、通学も見守りや送り迎えが必要なため、大勢の子どもたちが屋外で遊ぶ機会はめったにありません。その影響もあってか、広場で遊ぶ子どもたちは本当に楽しそうに遊んでいました。こんな全校遠足は私にとっても、日本人学校における素晴らしい思い出の1つです。


また、学年ごとに「社会見学」という行事もありました。芸術、文化、歴史を大切にするフランスについて学ぶことができる貴重な機会でした。
実際に行った社会見学は次の通りです。それぞれの学年のカリキュラムを総合的に学べるように計画しました。
- 小学校1年生 パリ5区動物園
- 小学校2年生 サンカンタン商店街
- 小学校3年生 ロダン美術館
- 小学校4年生 オルセー美術館
- 小学校5年生 オランジュリー美術館
- 小学校6年生 ポンピドゥ現代美術館
- 中学部 ルーブル美術館
建造物を見るだけでも圧倒されましたが、実物を見たときにはその壮大さや迫力に驚かされたものがたくさんありました。子どものうちから「本物」に触れる体験に立ち会えたことは教師としてもうれしいものです。
環境や子どもたちによって深いレベルの教育実践ができた
フランスだけではなく、在外教育施設の多くは、「日本と同じようなものが手に入らない」ことがあるかと思います。その環境で教育活動を行うことで、「手に入るもので工夫して授業をする」スキルが高まったように感じます。
ポスター発表の資料を作るときにも、フランスでは模造紙のような大きな紙がないので、郵送されたものの梱包用に入っている紙をつないで作成しました。また、日本の学校では捨ててしまっていた教科書や教材などを梱包するシワシワの紙も、丁寧に伸ばして授業などで使っていました。
それでも教材が手に入らないときには、ホームセンターのようなところに行って、代わりに使えそうなものがないかを探し歩いたのを今でも思い出します。
この経験は日本に戻ってきてからも生かされていて、なんでもお金を出して買うのではなく、「何か別のもので代用できないか」と考えて結びつけることで、問題を解決する力が身に付きました。
在外日本人学校は私立学校としての側面もあります。学費をいただいていることもあり、高いレベルの教育が求められていると感じました。普段の授業や学校の子どもたちの様子が保護者の方にしっかりと伝わるように、日頃の授業や学びについて定期的に発信していました。
保護者の方々はとても協力的でした。読み聞かせボランティアをしてくださる保護者の方々は、いつも工夫をこらしたくさんの読み聞かせをしてくださいました。子どもたちは読み聞かせを楽しみにしており、学校と家庭が連携して教育活動を行っていることを強く実感しました。
また、日本人学校の児童は自分の考えをもっている子が多いと感じました。討論のような授業では、とても深いレベルのところまで進むこともありました。授業の質を落とさないように、広く深く教材研究をしておき、子どもたちに応えようとしていました。今振り返ると、自分自身としても、それまで届かなかったレベルの教育実践ができたように思います。今でも、日本人学校の子どもたち、保護者の方々、同僚の先生方、環境から大きく成長させてもらったと強く感じています。
印象に残っている教育活動では、フランスのHONDA工場に見学をしたときの動画を作成し、NHK for schoolの「未来広告ジャパン」という番組に応募したところ、見事「ナイスプレゼン賞」という賞を受賞しました。子どもたちが主体性を生かしてクリエイティブなことを実現できるように、関係する方々に事前に連絡をしたり、道具を準備をしたりなど、工夫をして取り組ませるようにしました。
また、校内の授業改善やグローバル人材を育てる研究に取り組み、その活動の一環として、補習校への授業支援を行っていました。フランス国内で10校以上ある補習授業校では、平日に現地の学校でフランスの教育を受けている子どもが、土曜日には日本の教科書や教材を使って学習します。
その補習校の先生が集まって行う研修会では講師もしました。先生方はとても熱心で、抱えている問題に対して相談に乗ったり、授業を提案したりもしました。実際に補習授業校に通う子どもたちを相手にして授業をしたこともありました。
なかでも印象的だったのは、UNESCO(国際連合教育科学文化機関)で働く教育担当者の方にワーキングメモリを鍛える絵本「アタマげんきどこどこ」の教材を紹介したことです。私がその絵本の教材作りに関わっていたこともあり、とてもセンセーショナルな体験だったことを覚えています。UNESCOの担当者の方から「この絵本のモデル(形式)を使って様々な教材に応用できそうですね」とのご意見をいただきました。
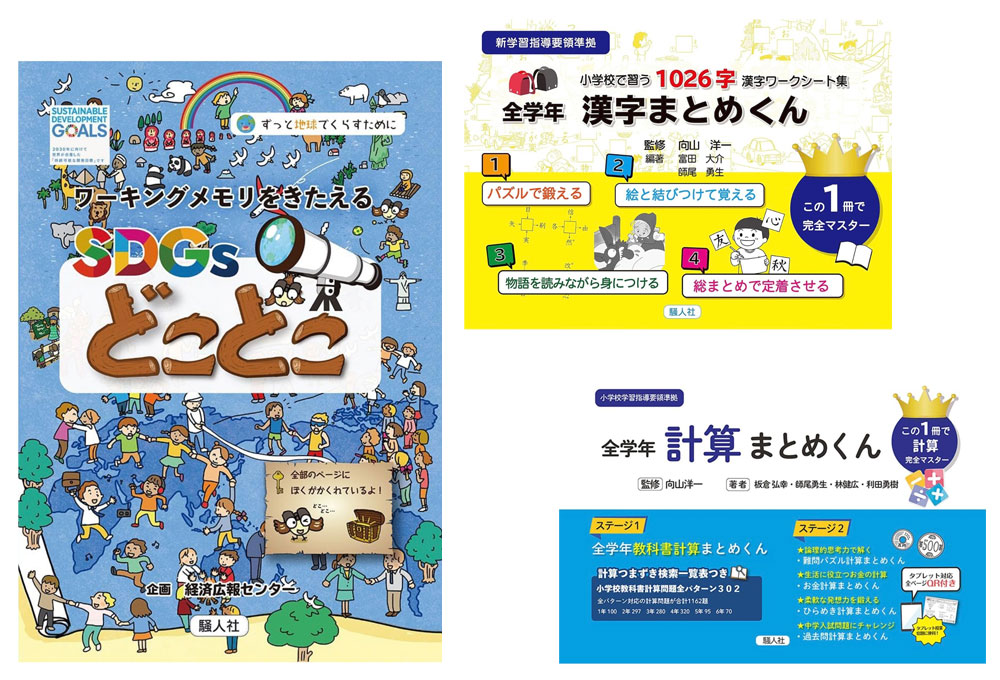


海外で教師をめざすあなたへ
在外教育施設での派遣教師を通じて、「世界は広い」と感じました。日本の学校で議論していたことが、そもそも議論の土俵の上にも乗らないようなこともあります。というのも、日本では「体育着を忘れたら体育ができない」という慣習を当然のように受け入れていましたが、在外の派遣校では体育着ではなく、色とりどりの「動きやすい服装」で体育をすることに最初は抵抗を感じていました。しかし、体育の授業は体を動かすことが本質であり、体育着は動きやすいものであればいいんだといつしか思えるようになりました。限りある資源の中で教育活動を行うことで、本質的なものを感じる力がついたように思います。
現在、教育現場にはたくさんの課題があるように思います。教師の利便性や指導のしやすさを重視するあまり、本質的なものを見失っているように見えることもあるように感じます。在外教育施設派遣に対して1%でも興味がある人は、ぜひ世界の広さを見てきてください。ご自身の魅力はきっと高まり、本質的なものを感じる力が身に付くと思います。
最後にフランスで活躍した画家、藤田嗣治の言葉を紹介して終わりにします。
「日本人よ、世界へ行きなさい。日本の中だけの成功で私は満足できません。」
※上記の内容は派遣期間中のことで、現在の状況とは異なる場合もあります

師尾勇生(もろおゆうき)●1979年神奈川県出身。青山学院大学理工学部卒。半導体技術者として社会人経験後、東京都公立小学校に勤務。公益財団法人 海外子女教育振興財団 日本人学校教育 DX 推進調査専門委員。東京都海外子女教育・グローバル教育研究会事務局。編著「全学年漢字まとめくん」、編著「全学年計算まとめくん」。「キーワードで教えるSDGs」「SDGsどこどこ」などその他出版協力多数。Xでは、もろQ(@chammochammocha)としてコミュニティ『X海研』の月1回の学習会を開催。

