<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #9 高知大学教育学部附属小学校2年B組②<前編>

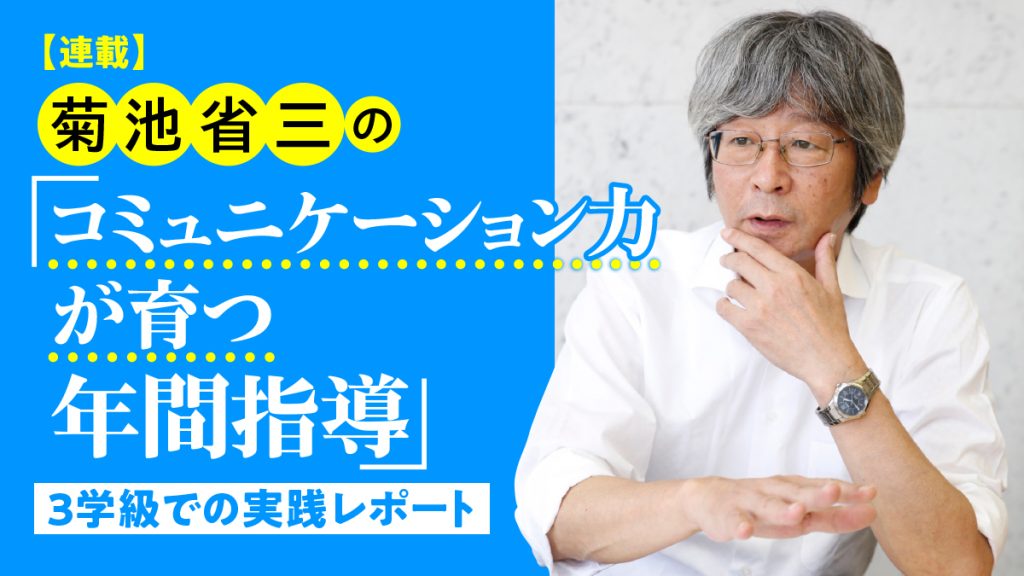
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載です。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。
今回から、高知の小笠原学級(2年生)における、9月中旬の授業レポートが始まります。「ほめ言葉のシャワー」をレベルアップするための、菊池先生+小笠原先生による合同授業実践です。

目次
担任・小笠原由衣先生より、学級の現状報告
2学期に入り、子供たちが授業中に落ち着いて学習に向かう姿が少しずつ見られるようになってきました。
立場を決めて話し合いをする活動をしたときも、友達と比べながら相談し、相手の話を静かに聞こうとする子が増えてきました。誰かが発表しているときは口を挟まないことを意識し始めている子も多くなりました。
一方で、学級としてのチームワークがまだまだ弱いな、と感じています。「みんなでやろう」という意識がかなり低いのです。
話し合いのときも、仲がいい子のところには話に行けますが、誰とでも話せるまでには至っていません。1年以上同じ学級で過ごしていても、話したことがない子供同士もいるようです。
そこで、友達の発表を聞き合えるよう、意見が対立するような授業や、参加していない子供も巻き込んでいくような授業づくりを意識して取り組んできました。
5月から始めたほめ言葉のシャワーも、だんだんとスムーズにほめ言葉を伝えられるようになってきています。
そこで、今回は、ほめ言葉のシャワーをレベルアップし、次のステップに持って行きたいと考え、菊池先生との合同授業に臨みました。
菊池先生と小笠原先生の合同授業レポート
「2Bでほめ言葉をやっていますね。日本一のほめ言葉のシャワーをしましょう」
菊池先生が子供たちに話しかけると、全員が元気いっぱいに、「はいっ!!」と答えた。
まずは、今まで行ってきたB組のほめ言葉のシャワーの録画をモニターで確認。ところが、パソコンがテレビモニターにうまく接続できないアクシデントが起こった。
待っていた子供たちがそわそわしてくると、菊池先生が、
「じゃあ、ほめ言葉(の録画)が始まったら、みんなで拍手をしよう。いつ、映るかわからないから、集中して聞くぞ」
と声をかけた。子供たちの視線が、再びモニターに集中した。
パソコンとモニターは相変わらず接続できない状態が続く。すると、菊池先生がモニターの下にあるパソコンの横で、
「じゃあ、ここに集まって。押しくらまんじゅうしたらだめだぞ」
と声をかけると、みんなが集まった。
「押さないで」「見えないよー」
集まった子供たちが押し合いそうになったので、視聴はいったん中止。
「録画を見るのは後にして、菊池先生には本物を見てもらいましょう」
と小笠原先生が声をかけた。
そして、席に戻った子供たちに、
「『ほめ言葉はすごくいいですね』とおうちの人からお手紙をもらったので、紹介しますね」
と手紙のコピーを配った。
保護者からの手紙には、
「悪いところを見つけるより、いいところを見つけて言う方が素敵な人ですね。そういう活動をしているB組はいいですね。学校で、みんなから見てもらえてほめてもらえる日があるのはうれしいです」
と書かれていた。
「だれのお母さんかなあ?」
「先生、だれのお母さん?」
「『名前は言わないで』といわれたので、秘密です」
「えーっ」
小笠原先生と子供たちの楽しそうな会話が続いた。
![]()
ちょっとした “隙間時間” が、子供たちの集中を妨げることがあります。ざわついて落ち着かないとき、まず子供たちを集中させて聞かせることが必要になります。
パソコンとモニターが接続できなかったとき、「ほめ言葉が始まったら、みんなで拍手をしよう。いつ、映るかわからないから、集中して聞くぞ」という言葉かけをしたり、保護者の作文を読んだときに保護者名を伏せることで「誰のお母さんだろう?」と気にかけさせたり。
教師は、状況に応じて即興でアレンジしていくことが大切です。 子供たちを威圧して締め付けるのではなく、意欲をかき立てて引き締めることが大切です。言葉を大切にする学級づくりを目指すのであればなおさらのことです。
話し合い活動は、レベルが高い学びです。子供たちの集中力が途切れていたら、知的な学びの楽しさは体験できません。
教師は、学びの内容・種類に合った教室の空気づくりの調整が常に必要です。

