小学校理科「知識・技能」の技能面の評価って、どうすればいいの?【理科の壺】

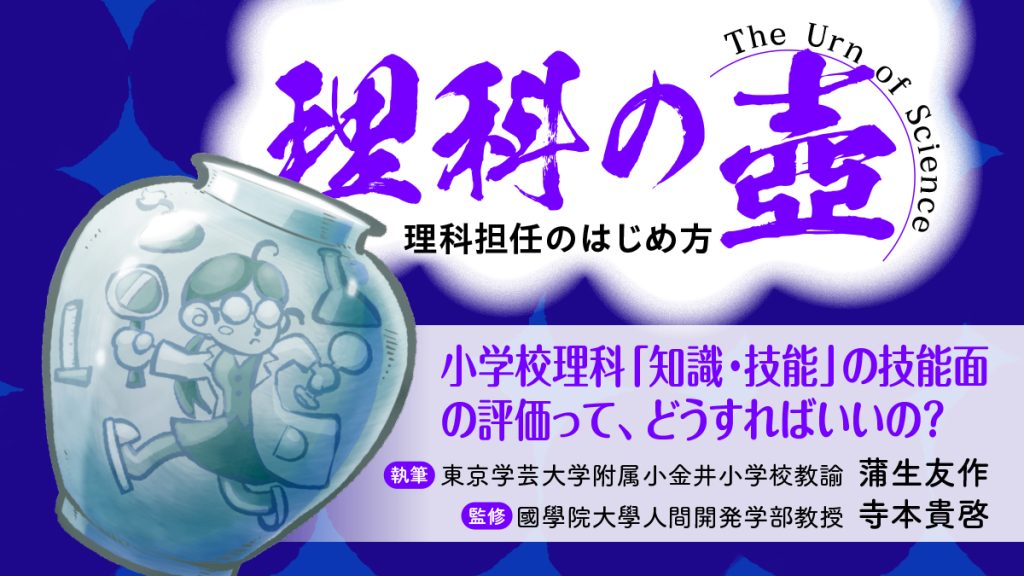
授業における評価の観点については、国立教育政策研究所の評価資料や教科書会社から出ている教師用の資料など様々ありますが、具体的にどのように評価するかについては、各学校や先生方に任されています。そのため、子どもたちの状況や単元内容、先生の考え方によって評価の方法が結構異なっています。また、指導法の研修はあっても、評価の研修はなかなかないかと思います。皆さんはどのような方法で評価をしているのでしょうか。今回は、「知識・技能」における、技能面の評価方法についての紹介になります。ご自分の方法と比べながら、よりよい方法を考えてみるのもいいですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・蒲生友作
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
皆さんは学習評価をどのように行っているでしょうか。評価には「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」がありますが、中でも「知識・技能」の技能面における評価は、なかなか難しいのではないかと思います。今回はその方法について、考えていきたいと思います。
1.知識・技能の技能面の評価について
知識・技能での技能面での学習評価について、国立教育政策研究所教育課程研究センター(2021)の『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 理科』p33~44において以下のように示されています。
第3、4学年
「(A)について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。」第5、6学年
「(A)について、観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択して、正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。」(A)は、「内容のまとまり」における学習の対象を示しています。例えば、第6学年「燃焼の仕組み」ならば、(燃焼の仕組み)が(A)となります。
国立教育政策研究所教育課程研究センター『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 理科』

