日本を離れ派遣教師として子どもを教えるということ~ベルギー・ブリュッセルより~
世界には在外教育施設派遣教師として、異国の日本人学校で教壇に立つ先生方が数多くいます。なぜ日本人学校の教師に? 赴任先の教育現場はどんな感じ? 日本の教育事情との違いは? ここでは、現地で活躍している先生の日々の様子をお伝えします。今回登場するのは、ベルギー王国・ブリュッセルで子どもたちに指導をしている海老原司先生。海外で教職の研さんを積みたいと考えているあなたへ、先輩教師からのメッセージです。
執筆/ブラッセル日本人学校教諭・海老原司
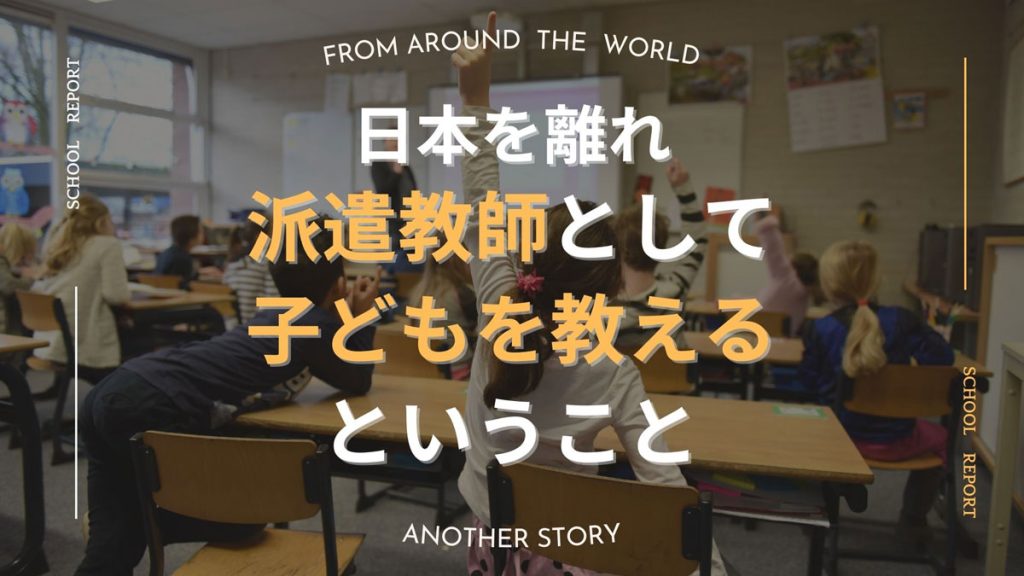
目次
派遣教師へのきっかけは幼少期に経験した海外生活
父の仕事の関係でシンガポールで生まれ、9才までは香港の日本人学校へ通っていました。就学前は現地の幼稚園に通っていたので、七夕や節分といった日本の伝統的な行事を経験したことがありませんでした。当時の香港はイギリス領だったため、幼稚園の友達はイギリス人が多く、先生は英語で話をします。家族とは日本語で会話をしますが、街に出ると、広東語が飛び交うなど、様々な言語の中で生活することが当たり前でした。
そんな私が日本人学校に入ったことで日本の文化に触れ、伝統行事を体験し、日本人としてのアイデンティティを確立できたように思います。とくに運動会で踊った荒馬踊りのことは鮮明に記憶に残っていて、図工の時間に馬の絵を描いたり、クラスのみんなと踊りの練習をしたりしたことは今でもよく覚えています。
私にとっての小学校6年間は、在外教育施設で過ごした時間のほうが長く、教師を志したのも自分のように在外教育施設で学ぶ子どもたちに日本の良さを伝えたり、感じたりしてもらいたいという思いからでした。派遣教員の応募要件を満たしてからは、毎年のように応募したい旨を管理職に伝えていましたが、学校の事情ですぐには応募できませんでした。2021年にようやく試験にこぎつけ、無事に派遣教師に決まりました。
派遣教師として合格するために、私は次のことを心がけました。
■自分の強みを前面に押し出す
①9才まで香港の日本人小学校に通っていたので、在外教育施設で学ぶ子どもの気持ちを理解していること
②東京教師道場、教育研究員、研究開発委員という東京都が行っている理科の研究に参加し、教科の専門性と授業力を高めたこと
③現任校が小規模校で、校務分掌のかけもちが当然の環境であったこと
面接や提出書類でこれらをアピールできるよう意識しました。
■自分のためではなく、在外教育施設に通っている子どものため
「自分の視野を広げるため」など、自分目線の応募動機だと「それなら日本の学校で実践すればいいのでは」と、思われてしまうかもと考え、「自分ではなく、子どものために何かしたい!」という気持ちを強く意識しました。
■派遣教師の経験者から様々な情報を得る
面接の内容だけでなく、実際の海外での生活のこと、お金のこと、子どものこと……多くの方の話を聞きましたが、ほとんどの方が、「行ってよかった。行けるならすぐにでもまた行きたい」と話していました。そんな話を聞いて自分のモチベーションを上げていました。
派遣校では中学生と関わる機会が増え、系統的な指導の重要性を実感
ブラッセル日本人学校での1日のスケジュールは基本的には日本と変わりはありません。時間までに出勤し、1時間目から6時間目まで授業があり、16時前に子どもたちは下校します。ただし、日本のように子どもだけで帰ることはできず、必ず保護者の迎えが必要になります(中学生からは子どもたちだけで帰ることができます)。放課後は翌日の準備などをして、時間になったら退勤します。会議は基本的に水曜日と決まっていて、水曜日以外の日に会議が行われることはありません。
授業も基本的には日本と同じですが、外国語の授業が小学1年生から毎日あるのが日本との大きな違いです。本校の場合、小学3年生以上の子どもたちは英語かフランス語のどちらかを選択し、授業を受けます(2年生まではどちらも受けます)。授業は現地の先生が、日本語をまったく使わずに行います。日本から来たばかりの子は、外国人の先生の発音や話す速さに初めは戸惑う子もいますが、少しずつ慣れてくると数か月で聞き取れたり、英語やフランス語で話ができたりするようになる子もいます。


本校はヨーロッパでは比較的、児童生徒数が多く、小学部は11学級(2024年現在)あり、1学級の児童数は約15~20人です。小学校籍の先生は全員小学部の担任を務めています。しかし、中等部の先生のなかには自分の専門以外の教科を教えたり、小学部の児童を教えたりしている方もいます。中学部の先生が小学部の児童を教えるのは初めての方が多く、いつも以上に言葉遣いに気をつけること、丁寧に説明したり話したりすること、話し方や話すスピードを子どもに合わせること、ノートに即した板書をすること、集中時間を意識した時間の使い方など、いつもと違うようで、苦慮されている方もいらっしゃいます。
反対に小学部の先生が中学部の生徒と関わることもあります。運動会の応援団を担当したのですが、中学生との関わり方に初めは戸惑いました。今までに、中学校との授業交流で中学の授業を見に行ったことは何度かありましたが、行事のなかで生徒と深く関わることは初めてでした。私は小学校での指導しか経験がないのですが、知らず知らずのうちに、必要以上に丁寧に、細かく説明をしたり、話し方が幼かったりしていたようで、中学部の先生に指摘を受けました。中学生と関わるときには
「必要以上に説明したり、話をしたりしない」
「子どもたちに考えさせる」
「子どもたちが考えたあと、きちんと実行できるよう見守る」
ということを小学生との関わり以上に意識するようにしています。この関わりを通じて、小学校の先の発達段階を肌で感じられたことは、これからの指導を系統的に行う上でも、よい経験になっています。
本校の独自の行事といえば、「サン・ニコラ集会」と「現地校交流」があります。サン・ニコラ(Saint-Nicolas)というのは、聖ニコラのことで、日本ではサンタクロースが一般的ですが、ベルギーでは、サン・ニコラがプレゼントやお菓子をもってきてくれます。12月6日が「サン・ニコラの日」なのですが、その日に合わせてサン・ニコラ集会を行います。毎年、サン・ニコラやお供のピートを学校に招き、歌を歌ったり、ゲームをしたりします。昨年はフランス語の先生に踊りを教わり、みんなでダンスをしました。

「現地校交流」は、現地の小学校との交流です。1年生から6年生まですべての学年で行います。相手の学校へ行くときと、本校へ来てもらうときの2回行います。現地校の子どもはまったく日本語がわからず、ほとんどの子が英語も話せません。フランス語しか理解してもらえないのですが、子どもたちは身ぶり手ぶりや準備したイラストなどを使って、様々な方法でコミュニケーションを図っています。うまく伝わらないもどかしさや伝わったときの嬉しさ、何かを一緒に経験できた喜びなどを感じられる活動となっています。中学部も現地校やヨーロピアンスクールと年1回ずつ交流しています。
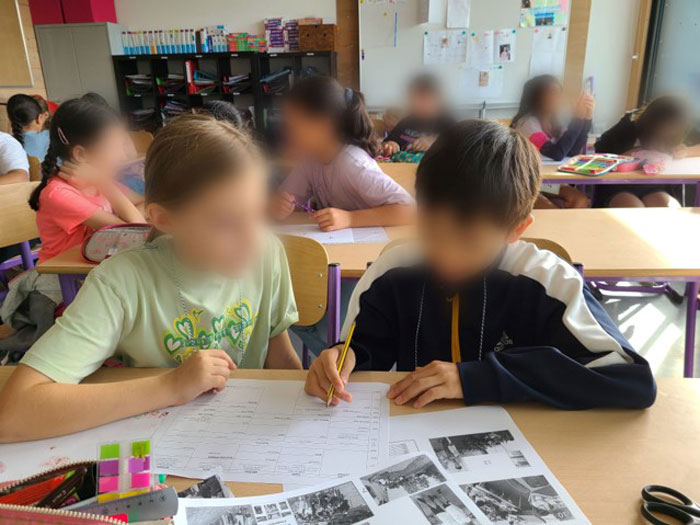
授業や給食の時間を一緒に過ごしコミュニケーションを図ります



