「助け合える学級にするためのアイデア2選」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #6

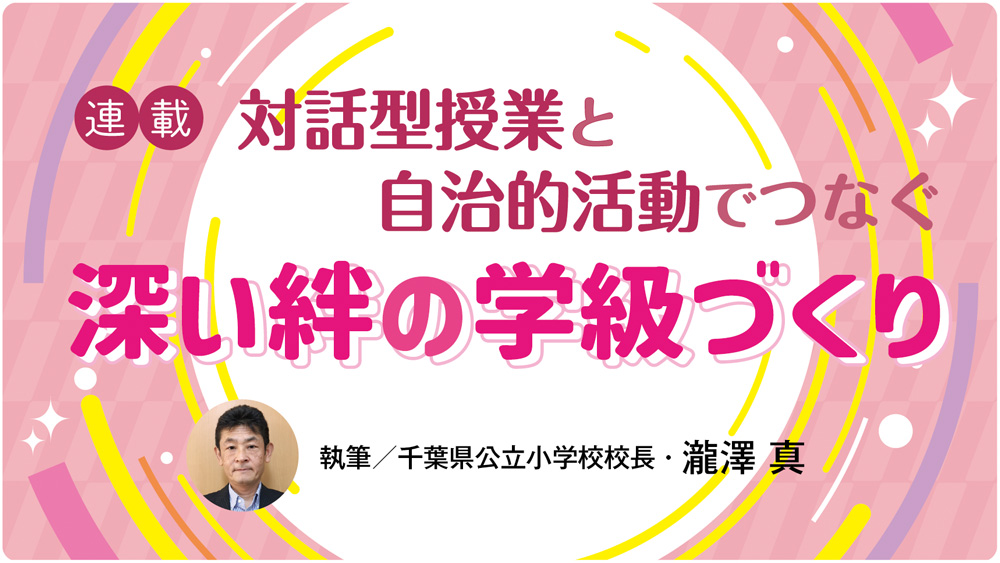
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第6回は、みんなが助け合える学級にするためのアイデアについて解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
深い絆のある学級は、みんなが自然と助け合っている
本連載は深い絆のある学級づくりがテーマですが、どんな状態だと自分の学級は深い絆で結ばれているなと感じるでしょうか。
私のイメージでは、「みんなが自然と助け合える」です。
学級がそういう状態だというのが、1つの目安になるのではと思います。
では、みなさんの学級は、どうでしょうか。困っている人がいれば、さっと手を貸す子がいるでしょうか。学級をよりよくするために、力を発揮している子がいるでしょうか。
もし、そうした様子が見られないならば、今回提案する2つのことに、ぜひ取り組んでみてください。
アイデア1:教師が子供の手助けの見本を示し、また、子供に助けを求める
担任が休んだときに、私が授業の補欠に入ることがあります。
その際、授業で使用する資料を黒板に貼ろうと思っても、マグネットが見つからないということがあります。そこで、「どこかにないかな」などと探し始めると、それを察して、マグネットを持ってきてくれる子がいます。学級によっては何人もそうやって手助けしてくれます。そういう学級は間違いなくよい学級と言えるでしょう。助け合える学級です。
教師が困っている姿を察する感度があるということは、友達が困っていることにも気付くでしょうし、そうであれば、きっと子供同士も助け合っているでしょう。
一方で、まったく無反応な学級もあります。
だれも手助けしてくれません。仕方がないので、「磁石はどこにあるかな」などと聞くと、やっと教えてくれます。そういう学級では、子供同士の絆が深いということもないでしょう。
そこで、自分の学級はまだまだ助け合えるような感じではないなというときには、教師がまずは親切に、積極的に子供の手助けをするとよいでしょう。
例えば、消しゴムを忘れて困っていたら、「どうぞ、これ使っていいよ」と言って、笑顔で貸してあげましょう。
間違っても、「前の日にしっかり確認しないのだから忘れるのですよ」とか、「この前も忘れたよね!」などと責めないようにしましょう。
子は親の鏡と言いますが、これは教師にも当てはまります。教師の行動が子供に影響を与えます。ですので、子供がたくさんの荷物を持っていたら、「半分持つよ」と声をかけてあげたり、習字の墨で床を汚してしまった子がいれば、一緒に拭き取ったりしてあげましょう。そんなことを続けていれば、「自分も一緒に手伝います」という子が必ず出てきます。
そうしたら、「一緒にやってくれる子がいるなんて、嬉しいなあ」と伝えれば、さらにお手伝いしてくれる子が増えるでしょう。
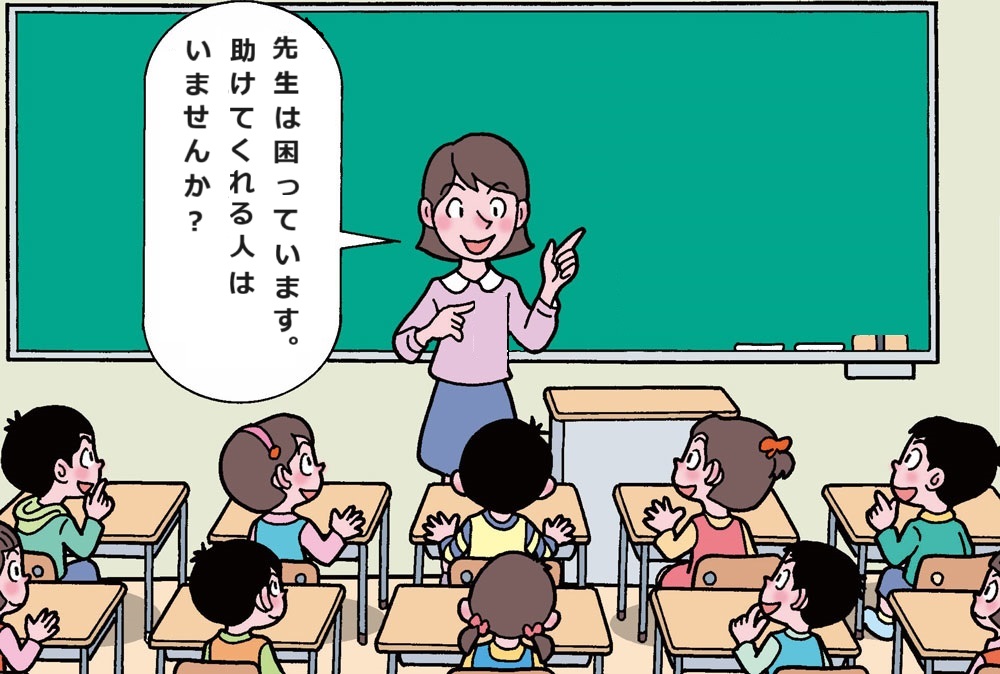
また、教師が助けてほしいなという場面では、遠慮せずに子供たちに声をかけましょう。
窓を開けて換気したいなと思えば、「だれか一緒に窓を開けてくれないかなあ」と言います。すると、何人かがさっと窓を開けてくれるでしょう。
そこですかさず、「すぐに手伝ってくれる子がいてありがたい。嬉しいな」と伝えましょう。手伝ってくれたことをほめるのではなく、嬉しいと気持ちを伝えるほうがいいのです。ほめられるから行うのではなく、相手に喜んでもらえるから行うほうが、その後、子供同士での助け合いにもつながります。

