宮口幸治先生が語る “親ガチャを乗り越える哲学”【みん教×EDUPEDIAコラボインタビュー】
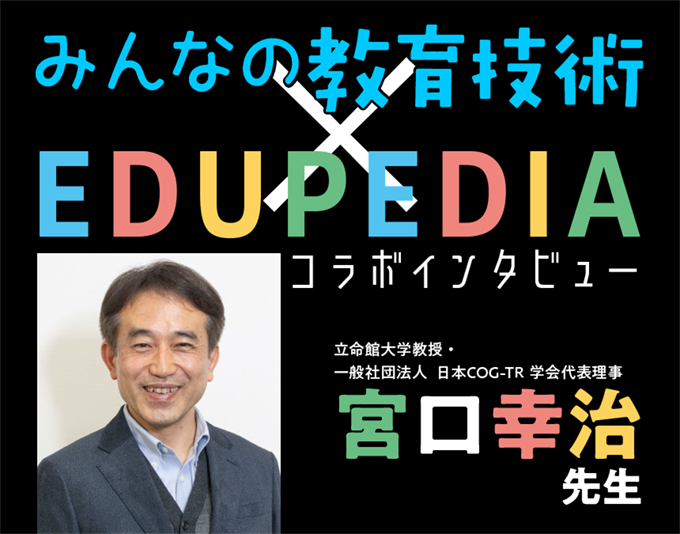
弊サイト連載「『コグトレ』でコミュニケーション力を育てよう」でもおなじみの、立命館大学教授・宮口幸治先生が共著でご執筆の新書『逆境に克つ力 ー親ガチャを乗り越える哲学ー』の内容をもとに、EDUPEDIA編集部がインタビューします。「親ガチャ」の根源である、妬みや諦観、不安を抱える子どもたちに、我々教師や大人たちができることについてお伺いしました。
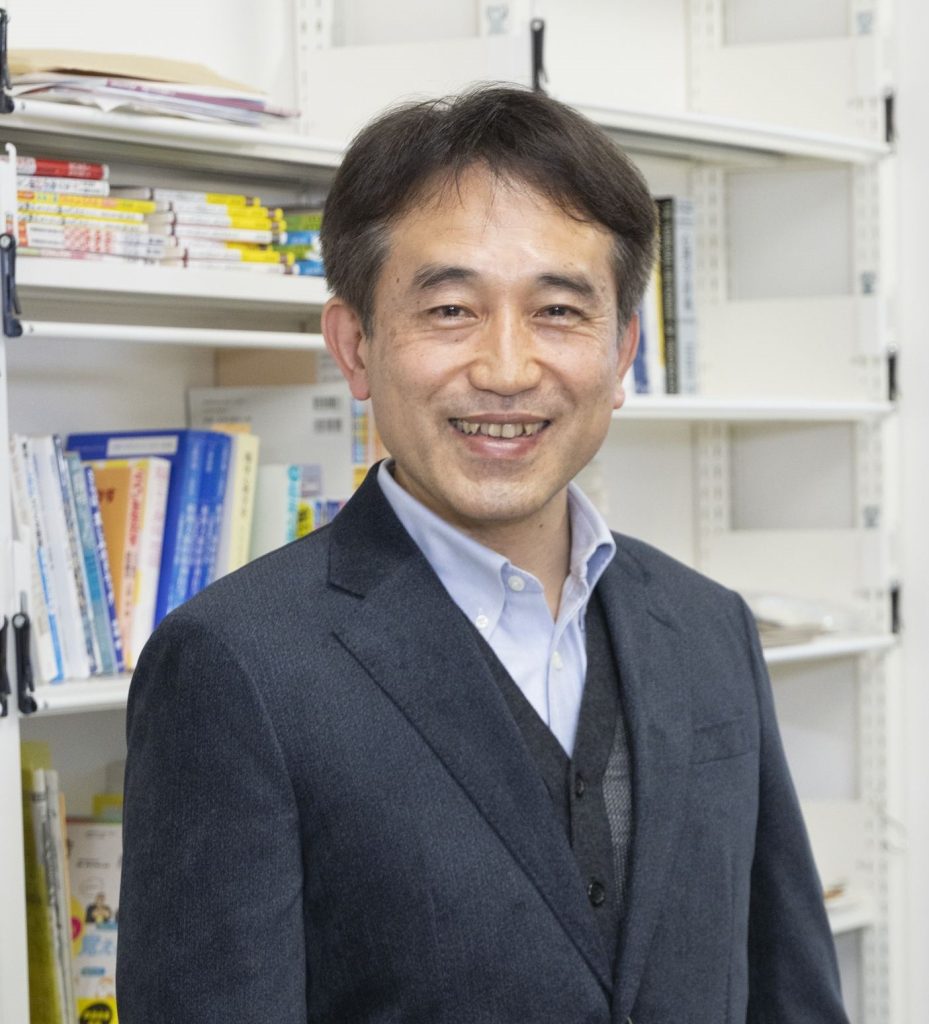
宮口幸治/みやぐちこうじ
立命館大学教授・児童精神科医。一般社団法人日本COG-TR学会代表理事。京都大学工学部を卒業し建設コンサルタント会社に勤務後、神戸大学医学部を卒業。児童精神科医として精神科病院や医療少年院等に勤務、2016年より現職。困っている子どもたちの支援を行う「日本COG-TR学会」を主宰。医学博士、子どものこころ専門医、日本精神神経学会精神科専門医、臨床心理士。著書『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)が大ベストセラーになる。
目次
子どもは「親ガチャ」を先生に相談しない
ーー学校などで「うち、親ガチャはずれなんだよね~」のような発言・相談をしてくる児童・生徒がいる場合、教員はどのような声かけ・対応をするのがよいのでしょうか?
宮口 そもそも、「親ガチャ、ハズレなんだよね」って相談してくる児童生徒がいるでしょうか。そんな子はあまりいないでしょう。なぜかって言うと、自分が、親ガチャだったり、貧乏だったり、経済的に恵まれてなかったり…なんてことがあったら、普通は、恥ずかしくて言えないですよね。隠したいですよ、そういうことは。
もし、そのようなことをあえて言ってくる子どもがいたとしたら、その背景を知ることが大事。どうしてそういうことを言ってくるんだろう、その子どもは何を求めているのだろうってことを、その子どもの背景として考えるということですね。
ーー確かに言われてみますと、本当に隠したい子どもっていうのは、そういうことは発言しないかもしれませんね。
宮口 とはいえ、教員を信用していないと、教員に相談しには来ないですよね。 信頼できないような先生に決して言わないでしょう。だから、子どもをしっかり観察して信頼されるっていうのはとても大事なんです。
ーー受験やテスト、偏差値など、今の教育システムは競争を強いられる場面が多すぎると感じる人も多いと思います。そのような環境にあって、嫉妬心を抱かない・自分は独立した存在であると感じることは難しいのではないかと感じています。今の教育システムで、嫉妬心に惑わされない、自分は独立した一個の存在であると考えることは可能なのでしょうか?
宮口 興味深い質問をしていただいて、ありがとうございます。
今の教育システムは競争を強いられているとのことですが、では、昔はどうだったでしょうか。私が若い頃は、共通一次テストがある世代でした。昔のことを思い浮かべてみると、共通試験システムって、昔の方がすごかったと思います。5教科7科目と試験科目が多く、二次試験も前期・後期なく一発勝負でしたし。しかも、子どもの数が多かった。ベビーブームなどで今の1.5倍ぐらいはいたでしょうからね。今はというと、様々な入試制度があって、いろんな選択肢もありますし。
今の世代は、昔の人より多様な機会に恵まれている気がします。しかし一方で、SNS等の出現で別の意味で自由が制限され、生きにくくなっていることも確かだと思います。興味深い質問と感じたのは、30年経ってもきっと同じ質問があるだろうと思ったからです。嫉妬心に惑わされず、自分は独立した一個の存在であると考えることができれば、誰も苦労しません。
でも、そもそも嫉妬心をもつこと自体は悪いことではないんです。
嫉妬というのは、紀元前から記録に残っているものです。どの時代においても、ある意味、嫉妬が歴史・世界を動かしてきたのです。だから、嫉妬心がなかったら、人は進化していかなかったかもしれない。
自分よりも成績を上げている人を見たら嫉妬したくなるでしょう。そこで頑張って、自分のめざす道を見付けて進んでいく。
ただ、嫉妬で自分の人生を左右されてしまうのは、ちょっともったいない。そういう不毛な嫉妬から自由になる、自分を独立した存在と捉えるということが大切だということを、本では言ってるということです。
その嫉妬を子どものプラスに働かせるためにできること
ーー不毛な嫉妬というものに向かってしまうと、やっぱり、足を引っ張り合うなど、悪い面が出てきてしまいますよね。そのような不毛な嫉妬ではなくて、プラスに働く嫉妬の方向に向かわせるために、学校教育で先生が何かできることっていうのはありますか。
宮口 一番いいのは、先生ご自身の体験を語られるのがいいでしょう。「先生は昔、こんなことに嫉妬して、いろいろあったんだけど…」なんて。私も、自分が教わった先生の体験談や先生自身が体験された話って、すごく残ってます。先生の体験を聞くことが、すごく心に響くんですね。「こうすべきだ、ああすべきだ」なんて諭すより、ずっと説得力があります。
私自身、いろんな先生と出会ってきたんですけれど、この先生にこの時にこういうひと言を言われたなってこと、ずっと一生の宝物になってることってあるんですよね。
小学校6年の時、先生からさりげなく言われたことが、ずっと今も、心の糧のように、それが自信となって残ってるような感じです。先生のひと言が、その子の人生を大きく左右するようなこともある。そのくらい影響力があるということなんです。
実は昨年、その先生と何十年かぶりにお会いできて、その時のお礼を伝えることができました。もちろん、その先生は覚えておられませんでしたが。
子どもの将来、日本の将来を変えられるのは、先生方しかいないと私は思っています。
ーー親・教員以外に、どのような大人が子どもたちの成長に関わることが可能でしょうか?
宮口 子どもの成長に関わるというのは、大人に限る必要はないんです。たとえば、同級生でもいいですね。 極端に言ったら、人でなくてもいいんです。動物でもいい。それこそ、動物の世話をするとかでもいいんです。
動物を世話した感覚だったり、自分が役立ってるなと感じたり、それが成長につながるんですね。誰かに世話してもらうことで、成長につながるんじゃないんですよ。逆に、世話することで人の役に立ってるっていう感覚が、成長につながっていくんです。
たとえば、3歳ぐらいの子が、自分よりちっちゃい1歳の子を世話してあげることもありますよね。どの年代でも、自分よりも弱い立場とか、ちっちゃいものに対して、「役に立ちたい」「世話してあげたい」って気持ちがあるんです。そのために頑張るんです。だから、どんな場面でも、どんな年代でも成長できる場面があると思います。

