ウェルビーイングを学校でつくる! ~SDGsの授業プラン #33 「Goal 16 平和と公正をすべての人に」・その2|岡川陽介 先生


全国各地の気鋭の実践者たちが、SDGsの目標に沿った授業実践例を公開し、子どもたちの未来のウェルビーイングをつくるための提案を行うリレー連載。今回は「平和と公正をすべての人に」について学ぶ授業実践提案の第2回です。ご執筆は、大阪府の岡川陽介先生。小学6年生、総合的な学習の時間での実践例です。
執筆/大阪府公立小学校教諭・岡川陽介
編集委員/北海道公立小学校教諭・藤原友和
目次
1 はじめに
はじめまして。大阪府枚方市で小学校教員をしております岡川陽介です。
今年度は6年生の担任をしています。私は広島出身であり、親戚にも被爆者がいることから、幼い頃より「原爆」「戦争」を身近に感じながら過ごしてきました。そのため、「戦争」「平和」に関しては、私なりではありますが関心を高く持っているつもりです。
私が勤務する枚方市は、市内44校全ての小学校の修学旅行の行き先は広島であり、全校が広島平和記念公園を訪れて平和学習を行います。その事前事後での平和学習の教材開発や、社会科や総合的な学習、道徳の時間などで、「戦争」「平和」、特に「原爆」についての授業づくりをこれまで行ってきました。今回の授業も昨年度、総合的な学習の時間で行ったものです。
2 Goal 16「平和と公正をすべての人に」について
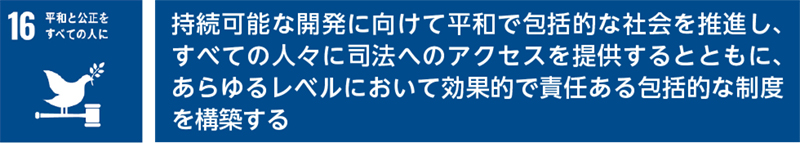
この目標においては、「平和で公正な世界」をめざし、「全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させること」を筆頭の目標とし、「紛争による難民の増加」「出生登録がされていない多くの子どもが多く存在すること」「子どもに対する虐待、搾取」「人身売買」「人種差別」「開発途上国の暴力に対する法的効力の低さ」などを問題として挙げています。
私たち日本人がこれらの他国の事実を知り、問題意識を持つことは、この目標達成に向けて極めて重要なことです。しかし、今回はあえて日本の過去の戦争に目を向け、これからも日本が戦争のない平和な国であり続けられ、その平和を世界に広げていけるよう、様々な立場からの様々な考え方があることを知り、その中でいかに「平和と公正をすべての人に」を実現できるかを、子どもたちなりに考えるきっかけとなる授業を目指しました。

