学級の「話合い活動」アップデート|気付きが生まれる話合いを促す技【中野裕己の授業技術アップデート06】

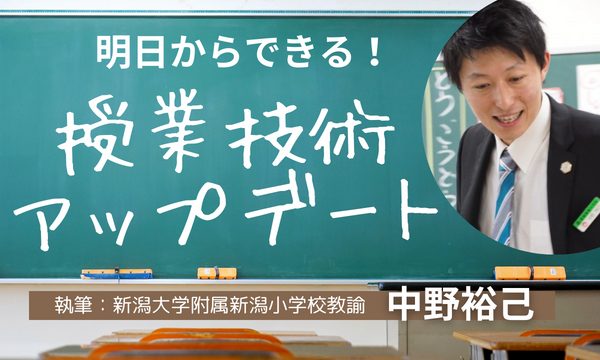
『小学校国語授業アップデート』の著者で、国語科(読むこと)、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による新連載!「発問」「教師の“ポジショニング”」「価値付け言葉」「問い返し」「ICT活用」「話合い活動」「授業準備」の7つの柱をテーマに、“明日から”できて“ずっと”役立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。
第6回目のテーマは、《話が「止まらなくなる」話合い活動》です。
執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己
目次
「話合い」とは?
連載第6回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。
現行の学習指導要領で示されている「主体的・対話的で深い学び」、中教審答申で示されている「協働的な学び」が象徴するように、授業において「話合い活動」は重要視されています。
そこで、今回の授業技術は、どの教室でも大切にされているであろう話合い活動に関わる授業技術を取り上げたいと思います。
まずは、教室で行われる話合い活動の形式を整理してみましょう。
ペアの話合い活動
「まずはペアから」などと、話合い活動の導入として行われることの多い形式です。一対一であるため、話すことと聞くことの役割分担が円滑になるとともに、発話する機会もある程度保証されます。
一方で、話合いの様相は、ペアになった2人の関係性に、強く影響を受けます。
つまり、何らかの理由でお互いに抵抗感があれば、話し合うこと自体が十分に行われない可能性もあります。

グループの話合い活動
「まだグループは難しいかも」などと、導入のハードルを高く設定している先生もいらっしゃるのではないでしょうか。4〜5人であるため、話すことと聞くことの役割分担は難しくなります。ともすれば、発話する機会が訪れない場合もあります。
また、ペアと同様に、話合いの様相はメンバーの関係性に強く影響を受けます。しかしながら、複数名であるため、ペアよりも特定の関係性は薄まります。

学級の話合い活動
この形を「話合い活動」と呼ぶのであれば、おそらく一番多く取られる形式であると考えられます。挙手して話すことが一般的であるため、話すことと聞くことの役割分担は明確になります。なお、集団であるため基本的に聞く時間が多くなります。
また、教師が明確に位置付いた形式であるため、子供同士の関係性による影響は小さくなります。

それでは、この話合い活動をより効果的に運用する授業技術について、今回も【Before】【After】でお示ししていきます。
【Before】発表的な話合い活動
まずは【Before】ということで、話合い活動の「あるある」といっても過言ではない、『発表的な話合い活動』について述べていきます。例えば、以下のようなグループの話合いです。
「ごんぎつね」では、兵十に「神様のしわざ」と思われていながらも、栗や松茸を届けに行くごんの姿が描かれています。これを取り上げて、「ごんが、その明くる日も兵十の家に行ったのはどうしてかな」という問いで学習を行うことがあります。
じゃあ、まずぼくから言うね。ごんが兵十の家に行ったのは、それだけ反省していたからだと思います。反省していたから、神様のしわざって思われてもよかったんだと思います。
次は誰の番? 私でいい? 私は、つぐないだから、自分だって分からなくても、関係ないと思います。兵十にいいことがあれば、それがつぐないになるから。
次はぼくね。ぼくは、毎日やってればいつか気付いてくれるかもって思ったからだと思います。
最後は私。私は、気付かれなくても兵十がよい気持ちになればいいって思ったから、栗と松茸を持っていったと思います。
みんな違うね。
そうだね。いろいろな考えが分かったね。
分かりやすく示すために少々あからさまになってしまいましたが、ここで伝えたいことは、用意してきた考えの発表に終始しているということです。
「大きな声で話す」「すらすら話す」といった発表の練習にはなっているかもしれませんが、新たな気付きが生まれるような話合いにはなっていません。

