「全員活躍型のお楽しみ会で絆を深めよう」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #3

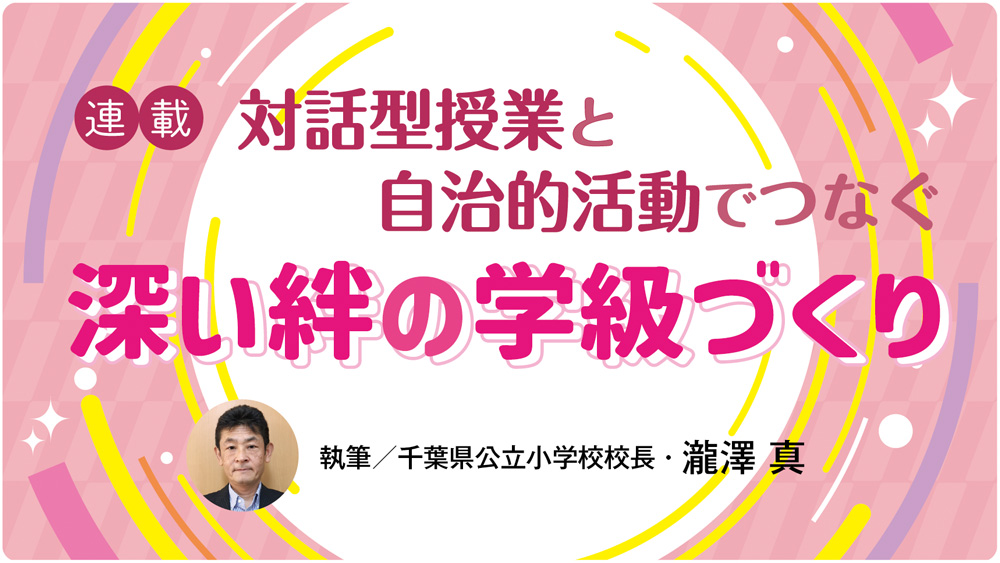
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第3回は、年間を通してお楽しみ会を計画することを提案します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
年間を通してお楽しみ会を計画しよう
新型コロナウイルス感染症の流行が拡大していた頃、私は市の教育委員会に異動になりました。職員のみなさんはとても優秀で、非常に仕事がしやすい職場でした。しかし、何かもの足りない、少し壁があるなあと感じました。
その大きな原因は、仕事以外でのふれ合いが全くないということでした。やはり、仕事以外での楽しいふれ合いがあると、人間関係がグッとよくなるものです。
このことは学級にも当てはまります。何かを一緒にやると、距離が近づきますよね。特に、そこに「楽しい」という感情が付随すると、その人との関係まで楽しく感じることもあるものです。
そこで、いわゆる「お楽しみ会」を、年間通して計画していくようにしましょう。お楽しみ会というのは、完璧にできる必要はありません。正直なところ、ぐたぐたであっても、誰にも迷惑がかかりません。こういう会こそ、大いに子供に任せ、自治的に活動できるようにしましょう。スムーズにできずトラブルもあるでしょうが、そこをうまく乗り越えることで、絆が深まるでしょう。
回数の目安としては3~4回、1学期に1回程度というイメージです。それにイレギュラーでやるものをプラスします。
この記事では、子供たち自身で企画、運営した経験が少ない学級という前提で話を進めていきます。
まずは教師主導でお楽しみ会をしよう

子供に任せるといっても、経験がなければ何をどうしていいか分からないでしょう。そこでまずは、お楽しみ会をやる上で心がけてほしいことを伝えます。
・みんなが楽しめる会にする
・できるだけ自分たちだけの力でやりとげる
・全員が関わる
この3つを守ることが、お楽しみ会を通して絆を深めることにつながります。
例えば、ドッジボール大会をやろうとなったとします。
では、ドッジボールは、本当にみんなが楽しめるのか。
得意な人だけが楽しいのではないか。
それなら、別の遊びにする。もしくは、ルールを工夫する。
そんなふうに話合いができるようにします。この話合いをすること自体が、様々な人のことを考えていくという土台づくりになります。
全員が関わるというのは、一部の係の子たちに任せてしまわないということです。
例えば、どんなお楽しみ会をやりたいのかを班で話し合い、それぞれの班から出た意見から1つを選んで実施していくというやり方があります。これならば、企画の段階から全員が参加することになります。
また、1班が企画、2班が準備、3班が運営など、役割を割り振っていくというやり方もあります。
いずれにせよ、全員が関わるからこそ、そのイベントに前向きに取り組むようになりますし、ものごとの進め方の勉強にもなるのです。
このような前提を伝えたら、みんなで実施計画を考えます。
計画に必要なのは、「目的」「日時」「場所」「プログラム」「遊びのルール・必要なもの」です。教師が司会をしながら、どんどん決めていきましょう。
以下、計画例です。
目的……いろいろな人と仲よくなる
日時……5月15日(水)2校時
場所……教室
プログラム
〇はじめの言葉
〇実行委員の話
・今日の目的など
〇レクその1(連想ゲーム)
〇レクその2(なんでもバスケット)
〇先生の話
〇おわりの言葉
遊びのルール・必要なもの
〇連想ゲーム
[遊びのルール]
・「○○と言えば」というお題から連想することを紙に書く。
・班対抗で点数を競う。同じ考えがいる人の数が得点になる。
[必要なもの]
・連想したことを書く紙
※なんでもバスケットは省略。
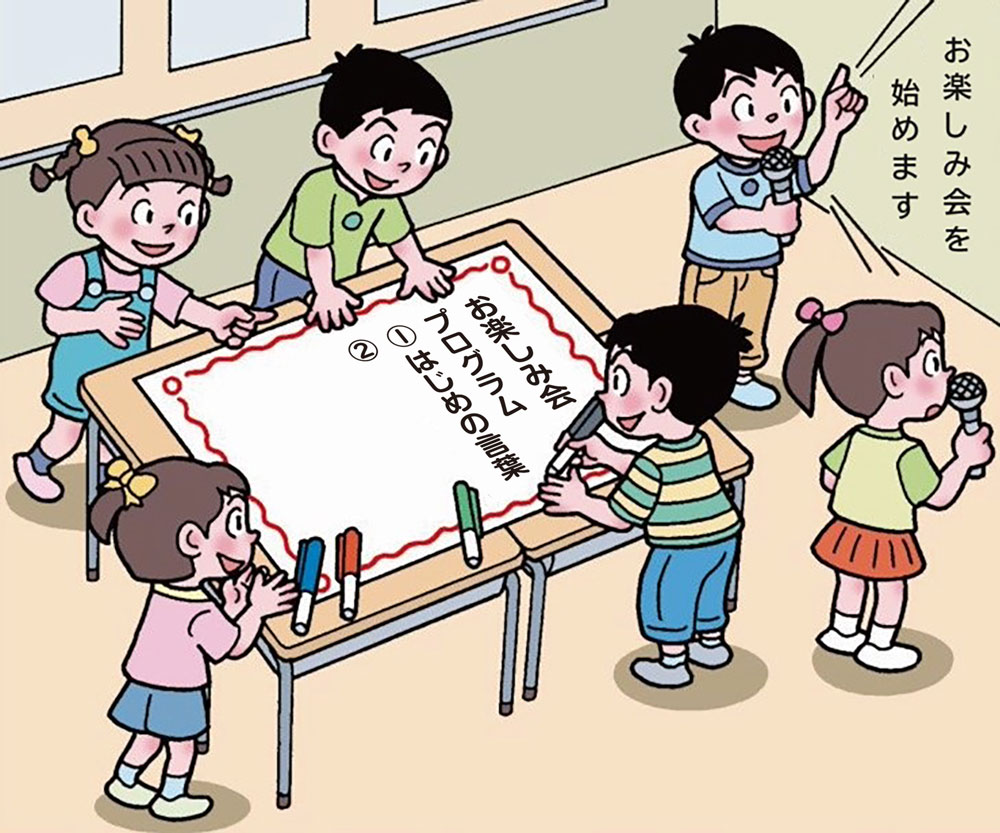
一通りできたら、だれがどの役目をやるのか決めます。例えば、司会、道具の準備、ゲームの審判などです。
こうして、教師主導でお楽しみ会を1回やっておけば、次からは話合いの段階から子供たちに任せてよいでしょう。もちろん、スムーズにはいかないでしょうが、スムーズにいくのが大切なのではなく、みんなで協力したり、時にはもめたりするような経験が大切なのです。

