「学習者用デジタル教科書」の現状と課題~どうしたら活用していけるのか~(後編)
令和6年度より、全国全ての小学5年生から中学3年生に、英語の学習者用デジタル教科書が導入されます。一部の小中学校では、「算数・数学」でも導入される予定です。いよいよ本格導入が見えてきた学習者用デジタル教科書。しかしこの先には活用へ向けての課題も横たわっています。
本記事では、教科書会社の担当者や学習者用デジタル教科書を活用している先生方への取材から浮かび上がった現状と課題をもとに、元教科書編集者/元教育ソフト開発者としての筆者の視点から、活用に向けた考察と提言を3回に分けてお届けします。今回はその最終回です。
取材・文/村岡明
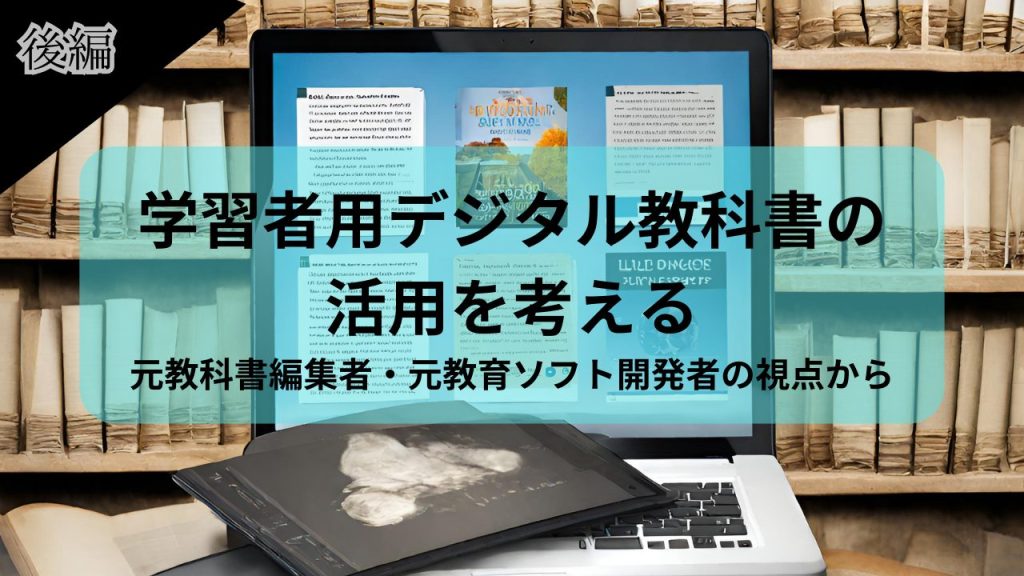
【前回の記事はこちら】
いよいよ本格導入へ!「学習者用デジタル教科書」をめぐる現状と課題~どうしたら活用していけるのか~(中編)
目次
「デジタル教科書の良さ」が共有されない状況
前回までの記事では、多くの先生が学習者用デジタル教科書について、「存在を知らない・使っていない・良さが感じられない」と感じている現状について述べてきました。良かれと思って導入したのにこうした現象が生じるのは、けっして先生方が怠慢なわけではありません。こうした混乱は、業務をデジタル化しようとしたとき、ほとんどの組織において多少なりとも生じていることです。
こういった状況を解消するには、「とにかく使って慣れる」ということだけでなく、「問題点を教科書会社に報告し改善を促す」ということがあります。前回の記事でも、現場の先生方に対して「使いにくいと感じることがあった場合は、ぜひサポートセンターに連絡してください」とお願いをしました。
では、先生方からの意見を受け取った教科書会社は、どのように製品に反映すればよいでしょうか。以下は、元・教育ソフト開発者としての提言です。
顧客の声を「聴く」
一般に商品開発においては、「顧客の声を聴け」と言います。けれども、それは簡単ではありません。聴くためには、その製品に関わる深い知識と豊かな経験が必要だからです。
以前、授業取材の際に出会った学校教育用ソフト会社の担当者は、子供たちのパソコン操作ばかりを見て、先生の発問や指示、動作には注目しませんでした。おそらくは、授業の知見がないからです。これでは授業で生かせるソフトの開発は難しいでしょう。
教科書会社の人であれば、教育的知見はあるでしょう。しかし学習者用デジタル教科書を見ていると、制作側に教育課題を解決するための技術的な知見(自然言語処理やベクトル検索など)が足りないように感じます。たとえば東京書籍が採り入れているAR(拡張現実)のように、教育に生かせる技術はまだまだあるはずです。
学校教育に関する知識と情報技術に関する知識を併せ持つこと。さらに製品化の経験を重ねること。こうすることで、ようやく顧客の声が聴けるようになると筆者は考えます。


