考えを広げて整理できる「メモ」のとり方とは【ノート指導12】
- 連載
- ノート指導早わかり
上手にメモをとるコツをつかめれば、いろいろなシーンで役立てることができます。今回は、「メモ」を使った学習のアイデアについて解説します。
執筆/北岡隆行

目次
メモをとるときは観点をしぼって
観点をしぼったうえで、大事な言葉を抜き出す
「メモをとりなさい」と言ったことがあると思いますが、メモをとる内容と方法について、指導したことがありますか。
「ありの行列」(光村3年上)の2時間目のことです。教科書に書いてある課題を書かせました。
だれが、どのようにして、その考えを見つけたのでしょう。
課題を読み、答えをノートに書かせました。あてられた子のほとんどが、
「ウィルソンという学者がありのことを観察していて、それで答えがわかりました。」
と書きました。
ここがメモ指導のポイントと考え、これをそのまま板書して、あらためて問いかけました。
・「だれが」

・「どのように」
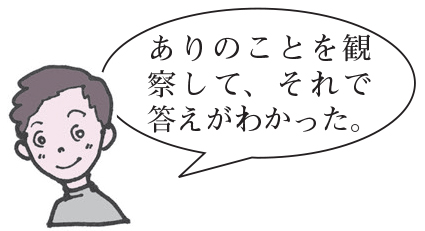
・「もっと短くしてごらん。どのように。」

・「もっと短く。どのように。」

と板書をチョークの二重線で消しながら短くしました。
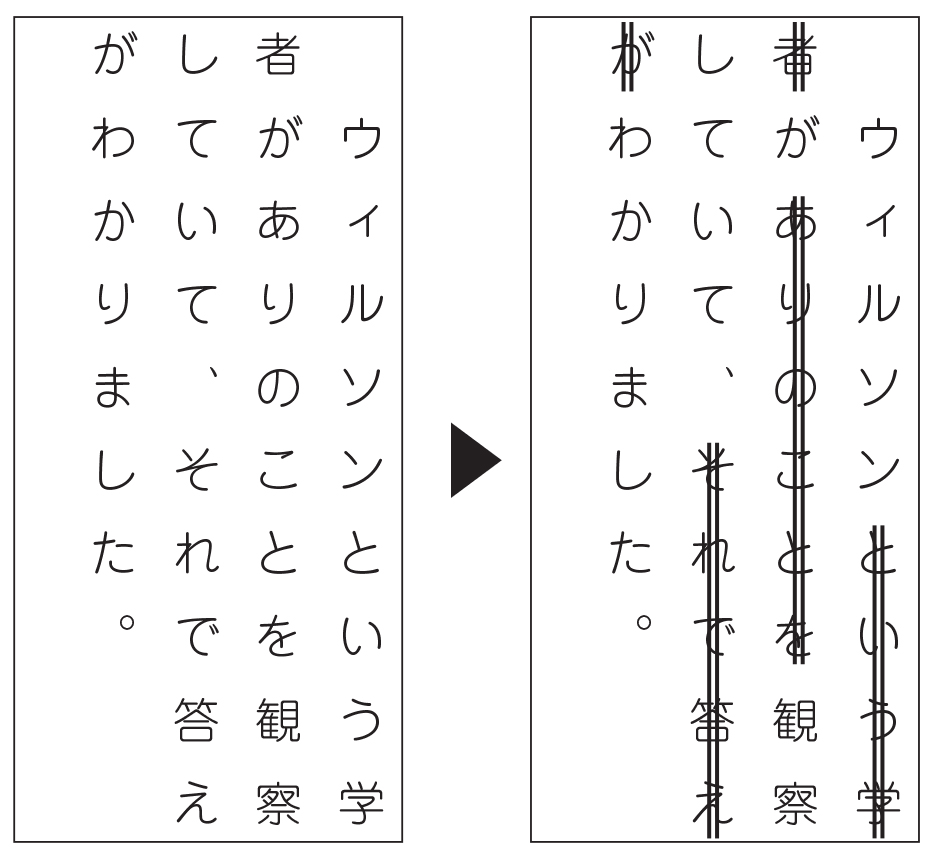
メモをとるときに大切なことは、○○を考えるうえで大事な言葉はどれか? 観点をしぼることです。問いに対応した部分だけを抜き出させることがポイントなのです。

