子供たちの忘れ物を減らす具体的で効果的な指導法

忘れ物の指導に悩んでいる先生や保護者の方は多いのではないでしょうか。うまくいかない理由は、忘れ物の原因を追求しようとする姿勢にあるのかもしれません。相手の事情を理解し、忘れ物という問題を解決するための【探究活動】だと思って指導に取り組んでみると、学級全体にもよい影響がありますよ。
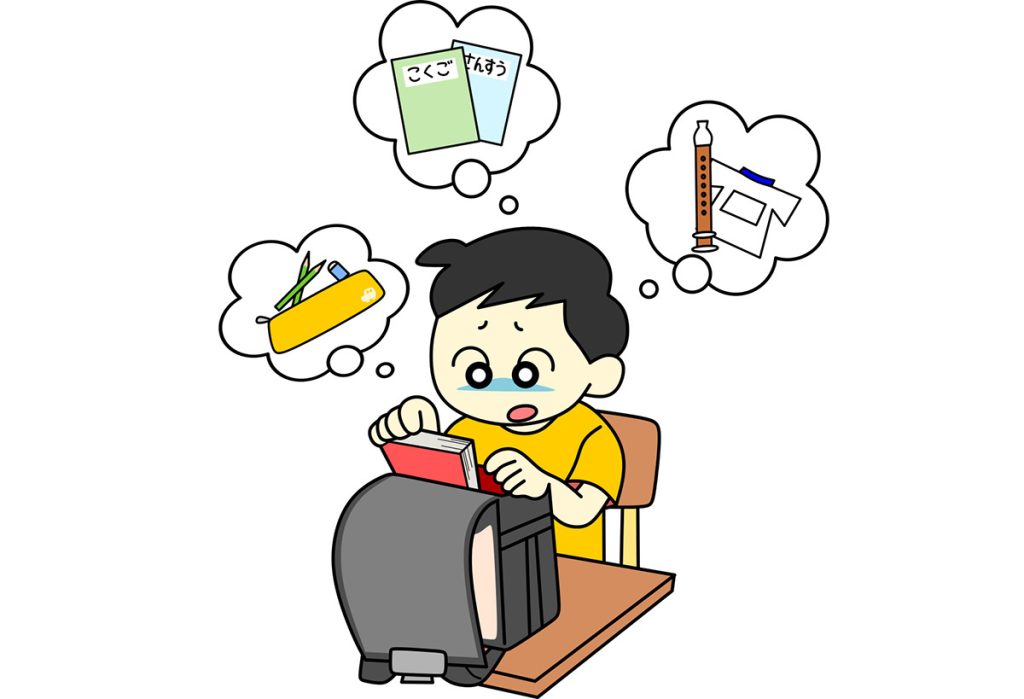
執筆/東京都公立小学校教諭・松原夢人
目次
「なんで忘れたの?」と言われても……
忘れ物の多い子供に対して、どのような指導をしていますか?
- 「なんで忘れたの?」「いつになったら持ってくるの?」「お家の人に連絡するからね!」などと言って、強い口調で注意する
- 忘れ物をした子供の名前を黒板に書いたり、チェック表を掲示したりする
- 「忘れ物をする人が多いので宿題を増やします」と連帯責任をとらせる
などの指導をしている人もいるかもしれません。
このような指導をして一時的には改善されたとしても、長期的には忘れ物が減る効果は感じられないのではないでしょうか。学級の子供たちを追い詰め、苦しめることは避けなくてはなりません。
では、子供たちの忘れ物を減らすためには、どうすればよいのでしょうか?
原因の追求から問題解決の探求へシフト
子供たちが学習で使う物を学校に持ってくるために、教員は連絡帳で伝えたり、メール配信で知らせたり、学年便り(学級便り)に記載したりしているでしょう。
しかし、購入して用意したり、子供にランドセルや手さげ袋に入れさせるところまでは直接指導はできないため、保護者に一任しなければならないところがあります。
だからこそ、保護者との連絡を密に取ることが重要ですが、上手く機能しないこともあるでしょう。
保護者も仕事や育児などで余裕がなく、子供の持ち物まで目が行き届かないことも多いものです。毎日、連絡帳を読んだり、子供に学習内容や持ち物について話したりできればよいのですが、その時間さえ取れない状況であることも考えられます。
「どうして忘れ物をするのか?」という原因を見つけても排除できないのであれば、「子供が忘れ物をしなくなる方法は何か?」と解決方法を探す方向へシフトする必要があります。

