生成AI×特別活動|小4「AIリテラシー教育」

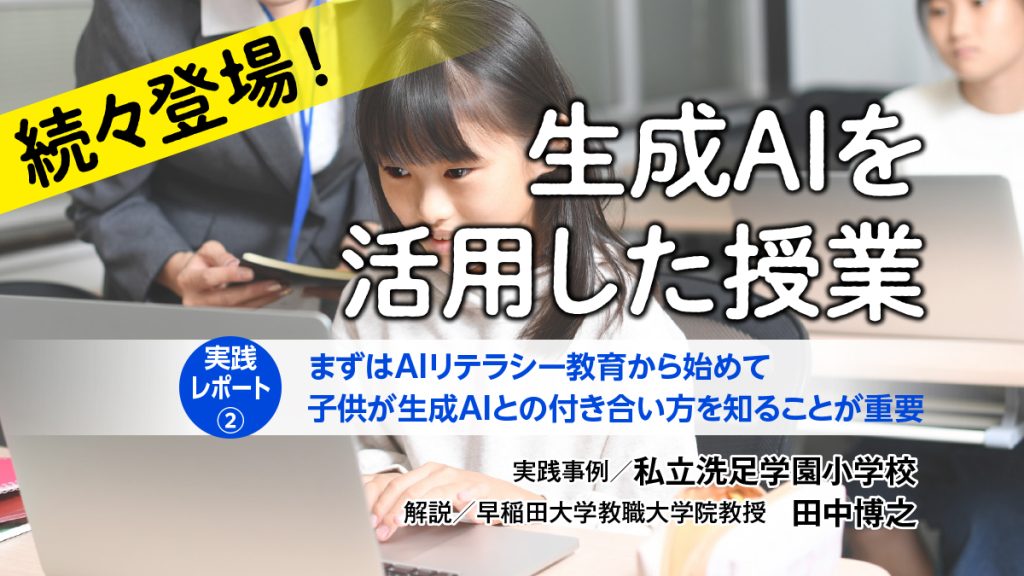
文部科学省が2023年7月に公表したガイドラインを踏まえ、実際に、生成AIを授業にどのように取り入れていけばよいのか、気になっている先生方は多いことでしょう。子供たちが操作をする前に、まずはAIリテラシー教育から始めてみませんか。今回は、神奈川県川崎市にある私立洗足学園小学校(田中友樹校長、児童数451 名)で、4年生の特別活動の時間に行われたAIリテラシー教育の実践例をご紹介します。最後に、早稲田大学教職大学院の田中博之教授による解説があります。
■ 本企画の記事一覧です
●生成AI×総合的な学習の時間|小6「学級キャラクターを作ろう」
●生成AI×特別活動|小4「AIリテラシー教育」(本記事)

目次
生成AIへの期待と不安
私立洗足学園小学校では、子供たちの学びを主体的なものに切り替えていくために教育のイノベーションを進めています。その中の手段の一つがICTの活用です。2018年4月に最初は3年生に1人1台iPadを貸し出すことから始めて、iPadを文房具の一つとして日常使いすることをめざしてきました。2023年度からは、1年生には入学段階で1人1台を買ってもらっているそうです。そのiPadを制限なしに、子供たちが自分で判断して、正しく使えるようにと、ここ数年はデジタル・シティズンシップ教育にも力を入れています。
「そのような流れの中で、ChatGPTは使いようによっては、子供たちの学びを、さらに主体的にさせるいい道具になるかもしれないと期待しています」と田中校長は話します。
「世間でこれだけ生成系AIが話題になっていて、子供たちが大人になって社会に出たときにはもっと進化しているでしょうし、子供たちの学びの部分にも様々な可能性をもっていますから、一つのツールとして大変興味深いと感じていました。
ただ小学生にどうやって伝えていけるだろうかと考えていた時期に、ちょうど現場の教員から『授業で取り組んでみたい。そのための研修に参加したい』との申し出があり、早稲田大学教職大学院の田中博之教授のもとで学んできてもらいました。ですから、授業を行うことに関しては特に不安はありませんでした」
田中校長には唯一、心配だったことがあったそうです。
「それは本校の保護者に受け入れられるかどうかです。 AIの危険性を指摘するようなニュースが流れていますし、保護者の中には不安を感じる方もいるのではないかと思ったのです。しかし、授業の目的や、必ずAIリテラシー教育を行うこと、教員立ち会いのもとで使うことなどを書いた文書をお渡ししたところ、反対する方はほぼいませんでした」
授業者の野口紗百合教諭に、生成AIを授業に取り入れようと思った理由を聞きました。
「生成AIを授業で使ってみようと思ったのは、学びの選択肢を増やすためです。私は生成AIは一つのツールだと思っています。子供が悩んだとき、何かアイデアが欲しいときに、今までの選択肢は友達、先生、家族の意見でしたが、新たにChatGPTという選択肢が増えることは子供にとって大きなメリットだと考えています」
この日の授業の前に、クラス全体にChatGPTの画面を見せながら様々な活動をしてきたそうです。
「子供たちには9月からChatGPTの画面をプロジェクターに映し、見せてきました。『なんて聞きたい?』、『聞きたいことはある?』などと問いかけ、子供の意見を聞きながら私がプロンプト(指示文)を入力すると、その度にどんな答えが返ってくるのか、興味津々で見ていたのです。今回の授業で、子供たち自身が初めて指示文を入力します」
生成AIの長所と短所を知る
ここから、4年生の特別活動の時間に行われた、AIリテラシー教育の授業をご紹介します。授業で使用するのはGPT-4です。

最初に野口教諭が問いかけます。
野口教諭「AIって聞いたことがありますよね?」
多くの子供が頷いています。
野口教諭「AIをなぜ最近、学校で使っているかというと、みなさんに一つのツールとして使ってほしいからです。例えば、Keynote、ロイロノートなどと同じだと私は考えています」
野口教諭「質問です。AIとは、何の略でしょう」
子供「人工知能」
野口教諭「正解です。英語ではどうなると思う?」
子供たちは考えています。
野口教諭「英語にすると難しいのですが、artificial intelligenceといいます。artificialは人工の、人がつくったという意味です。intelligenceは知能という意味です。だから、人が作った知能のことをAIといいます」
野口教諭「これだけではよくわかりませんよね。学研キッズネットなどを参考に、子供向けの説明を考えてみました。AIとは『コンピューターが人間の脳と同じように、記憶・判断・推論・学習などをする能力のこと』です」
野口教諭「ちなみに、皆さんの周りにはChatGPT以外にも、AIがたくさん使われています。例えば、Googleレンズです。この間、多摩川の校外学習に行ったときに、私のスマホのGoogleレンズで、『このお花の名前を教えて』と聞いてみたら、教えてくれましたよね。あとは皆さんご存じの、Siri。それから、Google翻訳。自動音声。あとは? 家にもあります。人を感知するエアコン。お掃除ロボット。自動運転機能付き自動車もあります。
そんな中で最近、洗足学園小学校の3年生や4年生が使っているのは、ChatGPTです。これはAIの中でも、生成AIといって、言葉をつくったり画像をつくったりしてくれます」
野口教諭「ここで大事なポイントがあります。生成AIの使用は13歳以上から、というルールがあります。18歳未満の人は保護者の同意が必要になります。なので、みなさんが自由に一人で使えるのは、18歳になってから、ということになっています。これはどこが決めた基準なのかというと、みなさんご存じのユネスコです」
子供「世界遺産の」
野口教諭「そうです。ユネスコは正式には国際連合教育科学文化機関といいますが、世界遺産を登録している機関ですよね。このユネスコが、生成AIを使用するときの基準を示していますので、みなさんが使うときは、私と一緒に使ったり、あるいは家の人と一緒に使わせてもらったり、という形で活用してもらえればいいかなと思います」
続いて、「生成AIとの付き合い方」について伝えます。
<生成AIとの付き合い方>
●情報が正しいか、必ず確認する
●生成された作品は生成AIの作品と考える
●個人情報を入力しない
●使いたいときには保護者と使う
野口教諭はプロジェクターにポイントを提示した後、項目ごとに説明を加えました。
●情報が正しいか、必ず確認する
野口教諭「出てきた答えを『これが正しい答えだ』と思ってしまうのは危険です。以前、誤情報が出てきましたよね。『バスケットボールの河村選手はNBAに行けますか?』と聞いたら、知らない人の話になりましたよね。そういうふうに苦手な分野もあります。だから、あくまでもヒントとするといいと思います」
●生成された作品は生成AIの作品と考える
野口教諭「生成AIには画像をつくってくれるものもあります。ただ、そういう作品は、生成AIの作品だと考えてください。『私が指示文を書いたから私の作品です』と、思ってしまうとそれは違います。生成AIの作品と考えます」
●個人情報を入力しない
野口教諭「個人情報を入力しないでください。これはどうしてでしょう」
子供「覚えてしまうから」
野口教諭「そうです。例えば、洗足学園小学校のAくんはどこに住んでいて、どこの塾に通っていますとChatGPTに入力したとします。その後どうなると思います?」
子供たちは考えています。
野口教諭「誰かがChatGPTに『洗足学園小学校には、どんな子供が通っていますか?』と質問したときに、「Aくんが通っています」と答えられてしまったら大変ですよね。なので、個人情報を入力しないようにしてください」
●使いたいときには保護者と使う
野口教諭「先ほど言った通り、生成AIの使用は13歳以上から、というルールがあります。18歳未満の人は保護者の同意が必要になります。ですから、家で使いたいときは保護者と一緒に使ってください」
★田中博之教授のポイント!★
AIリテラシーを育てる授業では、適切な利用と不適切な利用、個人情報の漏洩、著作権保護などについて簡潔にまとめて分かりやすく解説することが重要です。
さらに、生成AIを使うことで、どんな力がつくのかを確認しました。
●論理的に考える力
●創造する力
●情報を見極める力
野口教諭「一つ目は、論理的に考える力です。ChatGPTに適当に指示文を入力しても、求めている答えが返ってきません。どういうふうに聞くかを考えないといけないので、論理的に考えられるようになります。
二つ目は、創造する力。この間も『ごんぎつね』の学習で、自分たちが思いつかないときにChatGPTに質問したら、ヒントをもらえて、新しい案が出ましたよね。クリエイトする力がつきます。
三つ目は、情報を見極める力。これは正しいけど、それは違うんじゃないかと情報を見極める力がつきます」
この授業では、4~5名の班に分かれて、ChatGPTを使います。野口教諭が四つのテーマを提示しました。
①本の内容を読み、読書感想文を書いてもらう。
②見たことがない景色の画像をつくってもらう。
③自分が書いた文章を添削してもらう。
④何かを調べるときに生成AIを使う。
どのテーマを担当することになるのか、子供たちの期待が高まる中で、野口教諭はChatGPTの使い方の注意を伝えます。今回はあえて、質問の回数を4回までに制限しました。制限しないと、思いつきで何度も質問を繰り返す子供が出てくる可能性があるからです。
野口教諭「各グループ、4回までしか質問することができません。よく考えて質問し、1回目の質問に対する答えが返って来たら、それを踏まえてあと3回で、何を聞くのかをみんなでよく相談してから質問してください」
さらに、授業の最後に班ごとに発表してもらうための、ポイントを示しました。
野口教諭「発表してもらう点を三つにまとめました。
一つ目、この使い方からよいヒントを得られるか、得られないか。
二つ目、なぜそう思ったか。
三つ目、『ただし、こういう場合はヒントを得られるよ……』という例があったら、教えてください」

