総合的な学習の時間【わかる!教育ニュース#42】
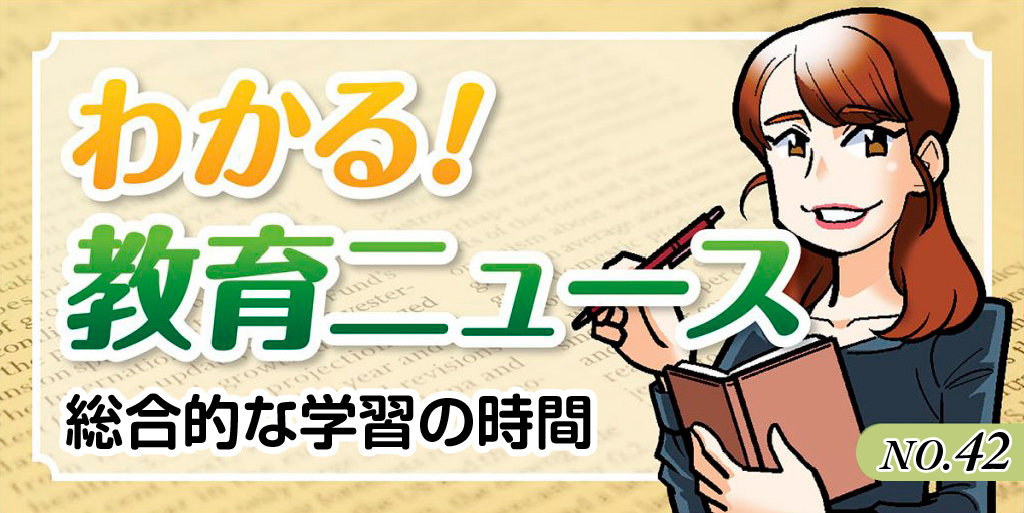
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第42回のテーマは「総合的な学習の時間」です。
目次
東京都渋谷区が区立小中学校で、「総合学習」を年155コマ
関心をもったことについて、もっと知りたい、技術を身に付けたい。そんな思いに駆られ、自分から動いて学び取ったものは、財産になります。では、学校でそういう授業がどこまでできるのでしょうか。興味深い取組が始まります。
東京都渋谷区が2024年4月から、子供が主体的に学ぶ「探究学習」の充実を掲げ、全ての区立小中学校で「総合的な学習の時間」を大幅に増やすことを決めました。興味や関心をもったことを調べ、課題を見付け、解決する力を養うのがねらいです。
科目名は「シブヤ未来科」(参照データ)。午前は国語や算数・数学など通常の教科学習が中心、午後は「シブヤ未来科」にし、地域や企業での体験活動、テーマに沿った調査や分析、意見発表などをします。
でも、どこから時間をひねり出すのでしょうか。区は、文部科学省の「授業時数特例校制度」という特別な仕組みを活用し、通常教科の授業を減らす代わりに総合学習の時間に上乗せし、減らした授業の学習内容を組み込みます。全体の授業コマ数は同じですが、総合学習はこれまでの倍以上の年155コマになる見込みです。
教科学習で培う考え方やスキルは、社会の事象を考察する場面で生かさなくては、本当の学力として身に付かない。区はそう説き、この取組で「生きて働く、本物の学力」を目指しています。評価はばらつきが出ないよう担当教員がチームで行い、数値を使わず、学習への姿勢や成果を所見で伝えます。

