空気のあたたまり方の学習を活用した、理科の「ものづくり」 【理科の壺】

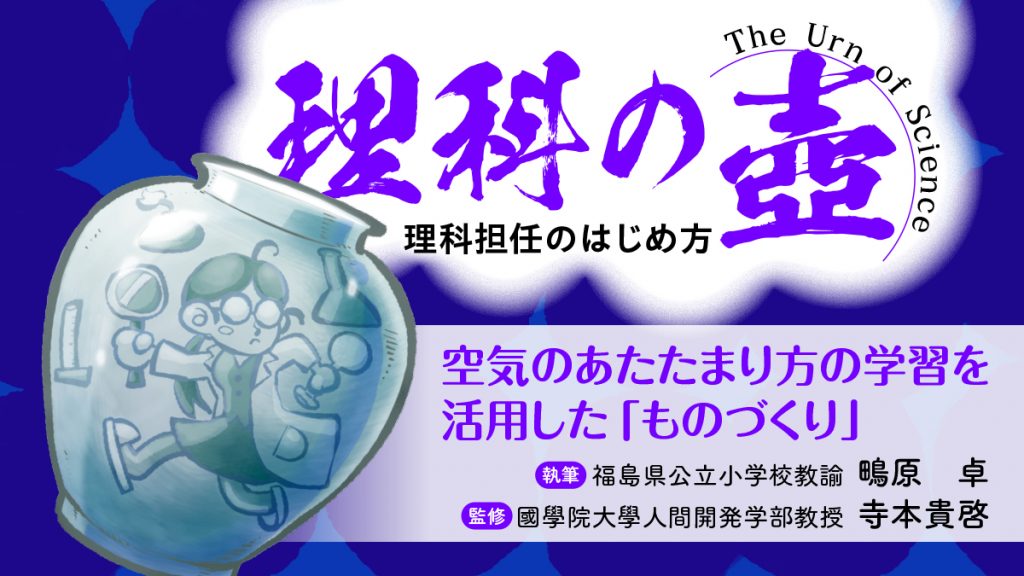
「ものづくり」と言うと、教材として販売されているモーターカーなどの印象が強いかもしれませんね。既成の教材は数多くあり、それらを採用して説明書通りに作らせると、実験には失敗しなくなるかもしれませんが、果たして本当に子どもの学びになっているのでしょうか?
理科における「ものづくり」では、
①子どもたちが目的をもって作っているか
②学んだことを使って作り方を考え、試行錯誤しているか
の2つがポイントになります。 今回は、子ども自身で考えた、まさに手作りの事例を紹介し、「ものづくり」の可能性を広げていくような実践紹介です。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/福島県公立小学校教諭・鴫原卓
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
はじめに
理科の学習指導要領では、「A 物質・エネルギー」の領域において各学年で2種類ないし3種類以上「ものづくり」をするように規定されています。
そのポイントは、「子どもが学んだことの意義を実感できるような学習活動の充実を図る観点から、子どもが『明確な目的をもち,ものづくりを行うこと』」と、「どのような学んだ内容を活用するか」です。今回は、第4学年、空気のあたたまり方における「ものづくり」を紹介します。
1 教師の目的をもった単元への「ものづくり」位置づけ
金属や水の熱の伝わり方を、子どもたちが視覚的に捉えることができるようにするために、示温インク(サーモインク)を活用して、実験を行うことが多いのではないでしょうか?
しかし、温められた空気の変化を調べるために、空気に色をつけることはできません。教室の天井や床に温度計を設置して、その気温の違いから、暖かい空気は上に行き、冷たい空気は下にいくことを捉えたり、線香の煙の動きを観察したりしますが、子どもが、温められた空気が上にいくことを実感を伴って理解しているのか不安になったことはありませんか?
そこで、単元末に空気の温まり方を目で見て、実感できるようにするために「ものづくり」を単元末に位置付けました。

