「通知表や個人面談で成長を伝えよう」保護者を味方にする学級経営術 #10

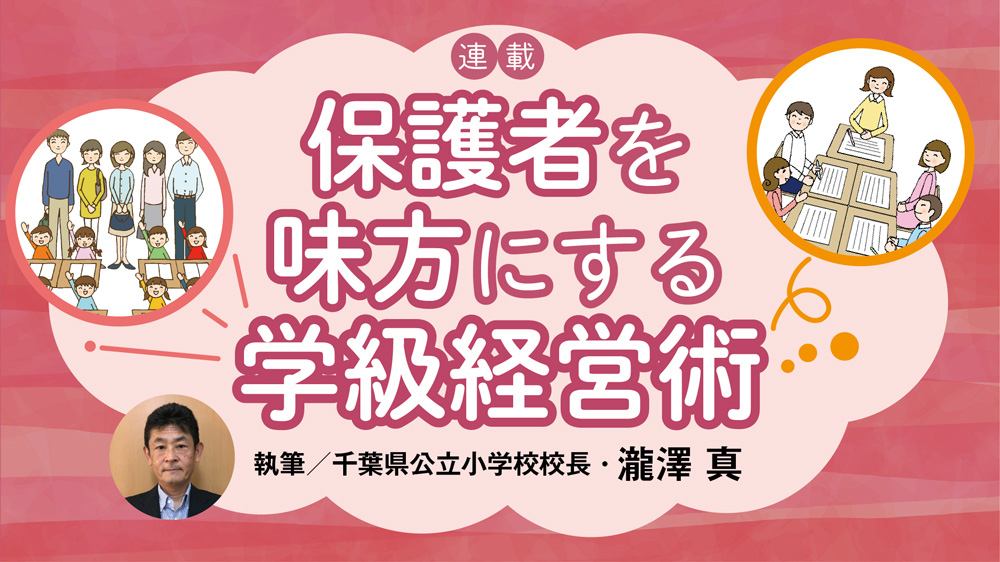
学級担任なら、一度は保護者対応に悩んだ経験があるのではないでしょうか。しかし、保護者が味方になってくれたら、こんなに心強いことはありません。この連載では、保護者が担任と学級を応援したくなるような学級経営について、その月の学校状況に合わせたアイデアを紹介します。第10回は、「通知表や個人面談で成長を伝えよう」を取り上げます。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
子供がもっとも成長する2学期!
通常2学期というのは最も長く、1年の中で子供が一番成長する時期といえるでしょう。その成長をとらえ、個人面談や通知表で伝えることで、保護者の信頼を得ることができます。
逆になんの成長も伝えられないようでは、当たり障りのない内容になり、この先生に教わっていてもいいことがないと保護者は残念に思うでしょう。
また、個人面談で子供の成長を伝えれば、そのことが保護者から子供自身にも伝わり、次へのがんばりにつなげることもできます。教師が直接その子をほめることも大切ですが、保護者を介してほめられるというのは、それはそれでうれしいものなのです(そのほうが、より効果的なこともあります)。
そこで、次のようなことを伝えるようにしましょう。
課題を克服したことを伝える
個人面談・通知表では、その学期でよくできたことを中心に伝えることが多いでしょう。もちろんそれでかまわないのですが、成長を意識した場合には、困難を克服した場面を取り上げることも大切です。そうした場面を認めることで、3学期も頑張ろうという気持ちにさせることができます。そこで、1学期にそれぞれの子にどんな課題があったのかを確認し、課題が解決したり向上したりしたことはないかという視点で、伝える内容を考えていきましょう。
例えば、2年生の算数で九九の練習を頑張っていた子がいるとします。実はその子は、1学期には九九がなかなか覚えられなかったのです。そんな場合には、次のような所見を書きましょう。
○かけ算九九の練習に熱心に取り組みました。休み時間も友達と一緒に練習したり、家庭でも積極的に学習したりし、着実に定着しました。
もちろん、大きな進歩がなかった場合もあるでしょう。ですが、かすかな成長でもかまいません。そうしたことをとらえ、伝えることも大切です。わずかな進歩でも、それが先生に認められたと分かれば、自信がつき、もっと頑張ろうという気持ちにもなるでしょう。
例えば、算数の計算が苦手で、たし算やひき算の時に、1学期は指を使って計算していた1年生が、2学期の終わり頃には、ほとんど指を使わずに計算できるようになった。そういう変容を見逃さず、記述するのです。
その場合、次のような所見文になります。
○算数のたし算やひき算では、1学期に比べて、すらすらと答えを出せるようになってきました。

このように、「1学期に比べ」という言葉を入れると、小さな変容でも書きやすくなります。1学期と対比させることで、他の誰かではなく、その子自身の成長という視点で記述することができるからです。また、普段からこのような目で子供たちを見ることが大切です。

