【教科調査官に聞く】道徳科の新学習指導要領-改訂ポイントと授業改善の視点
学習指導要領の改訂にあたり、資質・能力のポイントや授業改善の視点などをテーマに、文部科学省・浅見哲也教科調査官と畿央大学・島恒生教授に対談していただきました。
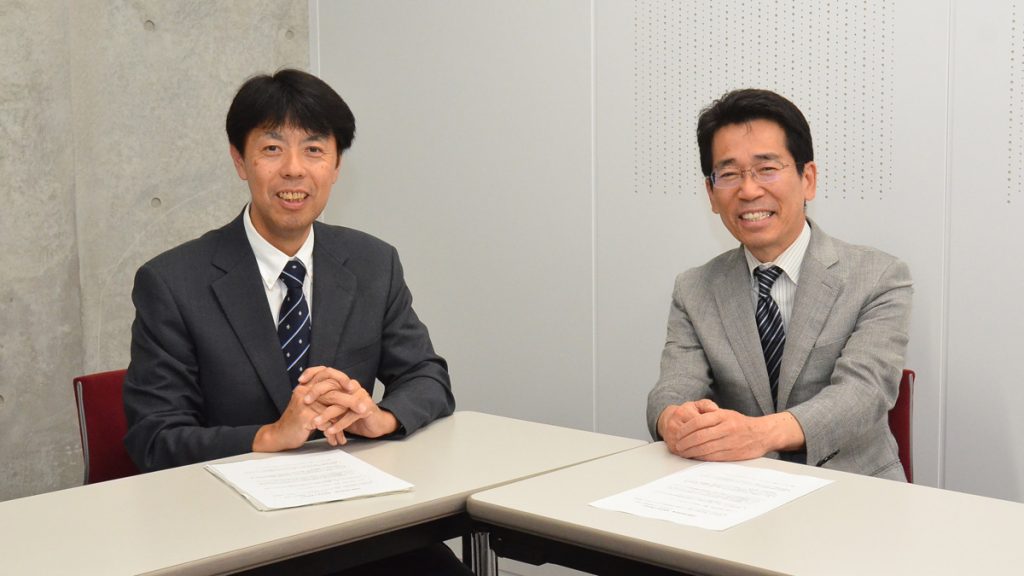
島恒生(しまつねお)[右]:兵庫教育大学教育学修士、奈良県公立小学校、奈良県立教育研究所を経て、現在、畿央大学教育学部教授。中央教育審議会専門委員(初等中等教育分科会道徳教育専門部会)、文部科学省「道徳教育に係る評価の在り方に関する専門家会議」委員、「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」作成協力者を務める。全国の教育委員会や学校での研修会講師として活躍。著書に、『教育技術MOOK 島恒生・吉永幸司のみんなでつくる「考え、議論する道徳」』(小学館)他多数。
浅見哲也(あさみてつや)[左]:埼玉県公立小学校教諭・主幹、埼玉県教育委員会生徒指導課指導主事、埼玉県深谷市教育委員会学校教育課課長補佐兼指導主事を経て、埼玉県深谷市立豊里小学校教頭、深谷市立藤沢小学校校長兼藤沢幼稚園園長を歴任後、2017年4月から現職。道徳教育のために情熱を注ぐ。
目次
目標をわかりやすくし、内容の体系化、指導の改善、励ます評価
島 本年度から「特別の教科 道徳」が小学校で全面実施になっていますが、小学校現場ではどのような状況でしょうか。
浅見 数多くの学校で授業を見学する機会がありますが、道徳科の授業を大事にしていることが伝わってきます。また、授業の導入では、本時に考えることを「学習課題」「めあて」「テーマ」などにして、投げかけることを多く見かけます。問題意識をもって、授業に臨もうとしている表れかと思います。
島 小学校「特別の教科 道徳」の学習指導要領の改訂ポイントは何でしょう。
浅見 改訂のポイントは、大きく4点あります。1点目は、道徳科の目標をわかりやすくしたという点です。その目標の中に、私たちが目指すべき道徳科の学習活動を明示しています。
2点目は、道徳教育及び道徳科の内容の体系化です。内容項目数も、低学年、中学年は増え、低学年19、中学年20、高学年22、中学校22、ほぼ同数で、低学年から系統的に道徳的価値について学んでいこうというねらいがあります。
3点目は、指導方法の部分です。これまでの道徳の時間の課題として、読み物資料の心情理解のみの授業、一定の価値観の押し付け授業、型にはまった授業などがありますが、「主体的・対話的で深い学び」「考え、議論する道徳」といったフレーズを使って、授業改善を図っていこうとしています。
4点目は、道徳科の評価です。道徳科では、子供たち一人ひとりのよさを認めて、励ます評価をすることが基本となります。
【道徳教育 目標】
文部科学省「小学校学習指導要領」より
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
(小学校学習指導要領第1章第1の2の(2))
【特別の教科 道徳科 目標】
第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。
(小学校学習指導要領第3章第1)
島 「考え、議論する道徳」へ授業の質的転換を言っていただいたのですが、「考え、議論する道徳」はどのようなことでしょうか。
浅見 「考え、議論する道徳」の姿として基にしていただきたいのは、道徳科の目標に示された学習活動です。そして、「議論する」と言っても、発達の段階によって、その様子は異なると思います。低学年であれば、ねらいとする道徳的価値のよさに気付かせるという要素が他の学年以上に必要だと思います。それは、道徳的価値のよさ自体に気付いていないことも多いからです。また、自分の考えのほかに、友達の考えがあることに気付かせることも大事だと思います。
そして中学年になると、自分の考えと友達の考えを比べるということが大切です。比べて同じところを見つけたり、違うところを見つけたりして、どちらの方が自分にとって大事なのか考えていきます。さらに高学年になると、自分の考えをしっかりもち、友達の考えもしっかり聞きながら、どちらかの考えを否定するのではなく、それぞれの考えのよさに気付くということが大切です。決して答えが一つではない課題に対して真剣に考えることがとても重要で、それぞれのよさを生かしながら、自己の生き方についての考えを深めることができるとよいと思います。
いずれにしても、自分のこれまでの体験において、その時に感じたり、考えたりしたことを基にしながら友達と話し合い、最終的には、一つの物事に対して様々な捉え方ができるようになり、それらを自分に取り入れながら、これまでの自分の考えをより明確にしていけるとよいと思います。
島 よさという時に、あいさつパワーや友達パワー、やさしさパワーなど「パワー」を使うと、どんなパワーが発揮できるか見えるので、低学年の場合は、馴染むものではないかと思います。
浅見 パワーはわかりやすいですね。私がよく例えるのは、アンパンマンとばいきんまんです。「アンパンマンとばいきんまんは、どこに住んでいると思いますか」と聞くと、「テレビの中」といった答えが出てくるのですが、「みんなの心の中に住んでいるのですよ。アンパンマンの心もあるけど、ばいきんまんの心もあるよ」と伝えます。「ばいきんまんの心はどんなの?」と聞くのが、子供にはわかりやすいようです。
島 それが中学年になった時の、善と悪のひっぱり合いにつながっていきますね。
多面的・多角的な見方を自分に取り入れるために「議論する」
島 「議論する」とは、どういうことですか。
浅見 議論する目的は、一つの見方ではなく、多面的・多角的な見方を自分の中に取り入れるためなのです。何か判断しなければならない時に、いくつかの選択肢をもって判断したほうが、よりよい選択ができ、よりよい生き方につながると思います。そんな様々な考えを自分の中に取り入れることができるというねらいで話し合う、つまり、議論があるのです。
島 「考え、議論する」というのは、「主体的・対話的」と同じだ、と考えればよいのでしょうか。
浅見 私はそうは思っていないのです。道徳科の授業は、深い学びにたどりつくことが大事です。「考え、議論する」は、自分の考えを明確に持って、議論することによって、いろいろな考え方を知ったうえで、再び自分の考えをさらに明確にするところまでたどってはじめて、「考え、議論する」が、「主体的で、対話的」で止まらずに「深い学び」にたどりつく授業になります。
島 深い学びから、逆算することが大事ですね。

