理科授業での “振り返り” で「問題解決の力」を育てる 【理科の壺】

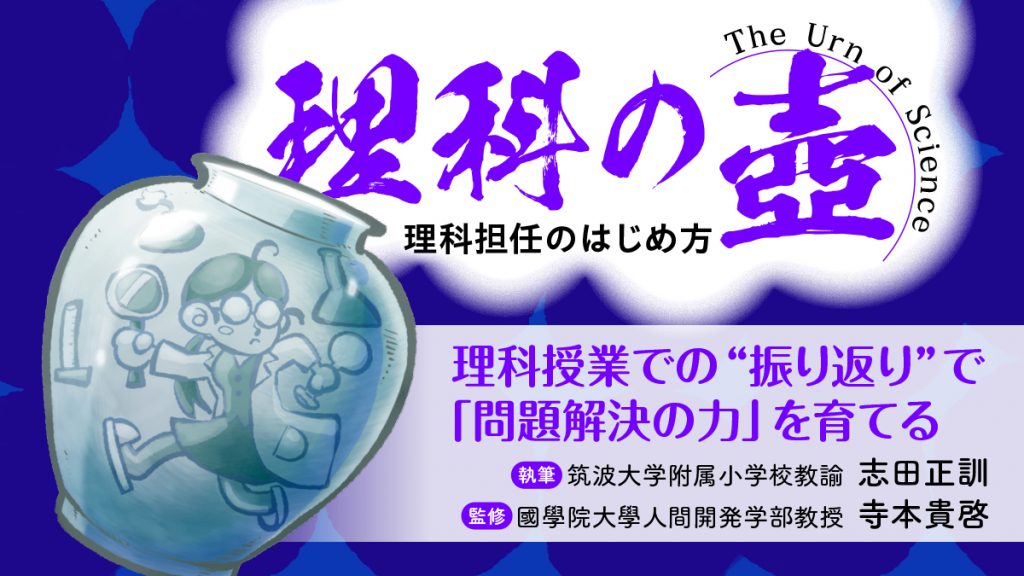
理科授業の振り返りは、どのようなことをさせていますか? 振り返りをする際、子どもたちがどのようなことが書けることを想定していますか? 振り返りの時間には、①教師が子どもの理解度を確認するため、②子どもが自分自身の理解を確認して強化するため、③子どもが自分の考えを見直すため、など、いくつか役割があると思います。今回は、「意味のある振り返り」がテーマです。具体的にどのように振り返りをしたらいいのか考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/筑波大学附属小学校教諭・志田正訓
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.振り返りの際、どんな声かけをしていますか?
「では、今日の授業の感想を、ノートに書いてみましょう」
理科の授業が終わって、その授業について振り返るときに、こんな言葉で子どもたちに授業の振り返りを書かせていませんか? でも、振り返りは、その授業時間を文字通り「振り返り」、その授業で大切だったことを改めて思い出したり、その授業で学んだことを、他の生活と結び付けたりすることができる貴重な時間です。上のような声かけだと、子どもたちは、授業について、自分が感じたことに注目し、「楽しかった」とか、「もっとたくさん実験してみたかった」といった、自分の感情に沿った記述が多くみられることでしょう。これでは、効果的な振り返りができたとは言えません。
2.どうして振り返りをするの?
そもそもなぜ授業の振り返りをするのでしょうか?
その答えの一つは、子どもたちに問題解決の力を育成するためです。例えば、第5学年の「発芽の条件」に関する学習で、種子の発芽に必要な条件を制御しながら実験の方法を考えたとしましょう。授業が終わって、「実験方法を考えるときには、条件を制御しながら進めることが大切なんだ」ということを授業を受けた子どもたち全員が考えられるようになったといえるでしょうか。私は子どもたちが授業について振り返り、「条件制御に注目して実験の方法を考えることが大切なんだ」ということを自分の言葉で書けたときにこそ、授業で学習した大切なことを学んだといえるのではないかと思います。

