解説|田中博之 生成AIの不適切な使い方と適切な使い方 【「生成AI利用ガイドライン」徹底解説 #3】

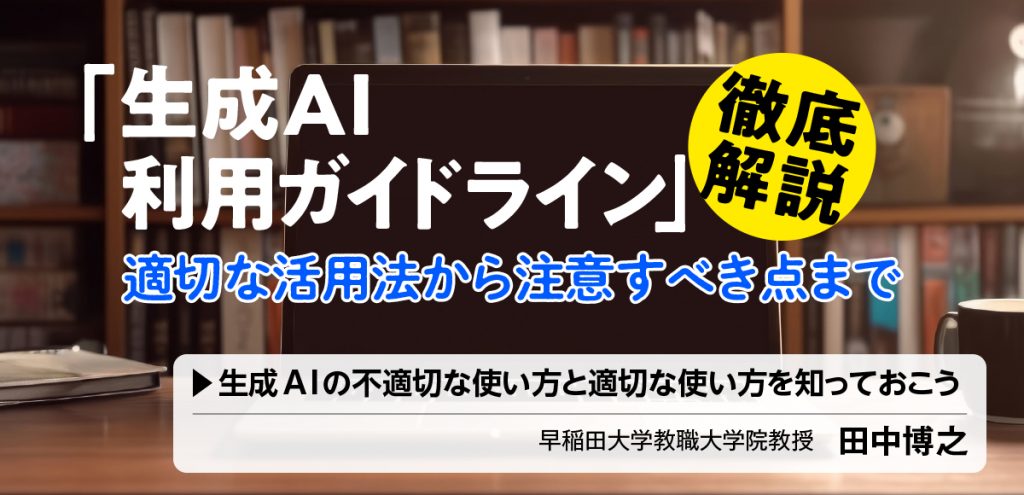
生成AIが世界中で急速に普及していることを受けて、2023年7月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的ガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表しました。今後、学校で、家庭で、ガイドラインに沿った適切な使い方をしていくためのポイントを、AIの教育利用について研究を進めている早稲田大学の田中博之教授に聞きました。第3回目は、学校での不適切な使い方と適切な使い方です。

田中博之(たなか・ひろゆき)
1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。2007~2018年度、文部科学省の全国的な学力調査に関する専門家会議委員。現在、21世紀の学校に求められる新しい教育を作り出すための先進的な研究に取り組んでいる。『NEW学級力向上プロジェクト』(共編著、金子書房、2021)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全3回予定)
●解説|田中博之 生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方<子ども用チェックリスト付き>
●解説|田中博之 学校で使用する前に確認したい4つのポイント
●解説|田中博之 生成AIの不適切な使い方と適切な使い方(本記事)
目次
生成AIの不適切な使い方とは?
文部科学省のガイドラインには、生成AIの利用にあたって「適切でないと考えられる例」と「活用が考えられる例」が紹介されています。
まず、「適切でないと考えられる例」です。8例挙げられていますが、この中で特に注目して欲しいのは①から④です。
ガイドラインの内容を引用しながら解説します。
生成AIを使って何をしてよくて何がダメなのかを児童生徒に意識させるような教育、つまり、AIリテラシー教育をまずは行う必要がありますので、この項目が1番目に書いてあるのは、非常に有意義なことだと思います。教科の授業で使う前に、このような生成AIを適切に活用する力を育てる授業を、最低1時間でも行うことが大切です。そのときにメリットやデメリットを、例を挙げながらわかりやすく教え、この連載の第1回でご紹介した子ども用のチェックリストも使いながら、子どもの意識を高めることが重要です。
ただ、ガイドラインでは、育成するものを「情報モラルを含む情報活用能力」に限定している点は、少々配慮する範囲が狭いと思います。安易に使うと、自分自身の思考力や問題解決能力などが育たなくなり、危険であることを子どもたちに十分理解させる必要があります。
これもとても大切なことですが、コンクール用の作品でなければいいわけではなく、夏休みの宿題や学校で出される課題についても言えることです。夏休みの宿題で、文章に関わるものにはレポート、小論文、日記、読書感想文など、いろいろあります。このような課題に対しても、生成AIを使うことは適切ではありません。それは、小中高校生のうちに身に付けなければいけない、思考力や問題解決力が育たなくなるからであると、しっかりと子どもに伝える必要があります。
これは、国語や音楽、図工、美術の授業のことを指しているのだと思います。ここでは感性や独創性が挙げられていますが、それ以外に、思考力、創造性、想像力、問題解決力も育たなくなります。ですから、安易に創作活動を生成AIに任せてはいけないのです。生成AIは、プロンプト(指示文)さえ書けば、条件に合う作品をつくってくれますが、創作の場面では、「最初は自分で考える」という大原則を教える必要があります。例えば、生成AIに文章を書いてもらうのであれば、最初は自分でテーマや構成、あらすじ、表現技法などを考えてみることが重要です。
これは社会と理科が該当するのだと思いますが、調べ学習においても、調べる観点や方法などを、「まずは自分で考える」ことが重要です。自分たちで考える前に、「何を調べるかを生成AIに聞いてみよう」などの丸投げはするべきではありません。そして、最後は自分で責任をもってまとめる、自己責任の原則もしっかり伝える必要があります。

