授業中の離席を減らすには?【伸びる教師 伸びない教師 第33回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

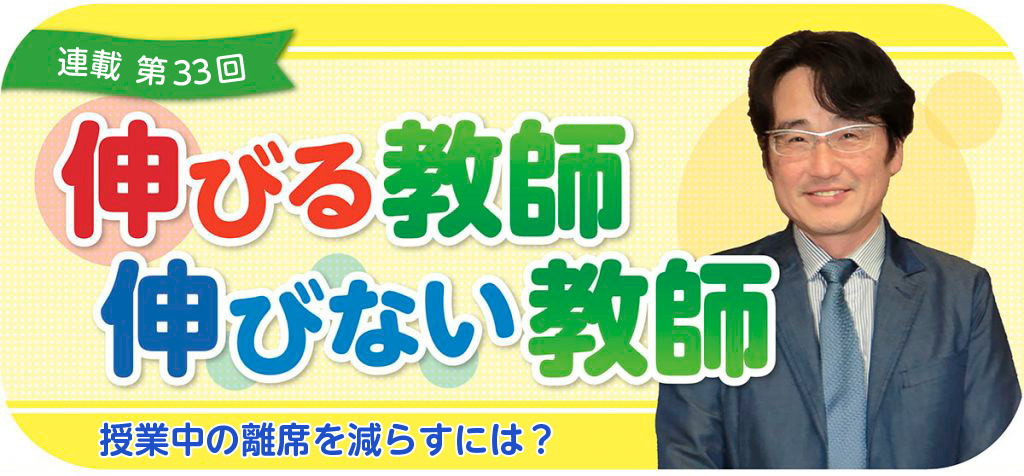
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「授業中の離席を減らすには?」です。子供たちの動きたいという欲求を先に満たしたり、活動を入れたりして、目の前の子供たちの実態に合わせて工夫するお話です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
動きたいという欲求を満たす
以前、2年生を担任したときのことです。となりの学級の体育も担当することになりました。その学級には、授業中に離席をしてしまう子供が何人かいて学級全体が落ち着かず、担任の教師も苦労していました。
それは体育でも同じでした。
校庭で鬼ごっこをすると、終わりの合図で笛を吹いても誰も戻ってきません。鬼ごっこを続ける子、砂場で遊ぶ子、登り棒に登る子など、みんな好き勝手なことをしています。全員をはじめの場所に戻すのに20分以上かかってしまいました。
次の時間からは、体育館で行うことにしました。しかし、授業の初めに整列し、礼をするまでの間、列から飛び出し走り出してしまう子が何人かいて、なかなか授業を始めることができませんでした。
そこで、体育館に入ったらすぐに太鼓の音に合わせてスキップ、ギャロップ、横走りなど、体育館の中を自由に走り回らせました。続けて犬走り、くも歩きなど、動物になりきって歩かせました。その後、「動物歩きで、こっちにおいで」というと、前の時間、走り回っていた子供もすんなり集合することができました。
教室で離席してしまう子供の多くは、動きたいという欲求を抑えきれずそのような行動に走ってしまうことがあります。初めに活動をさせ、その欲求を満たしてあげると落ち着いて指示を聞けることがあります。

礼の後に活動を入れる
これは教室の授業でも同じです。
礼をしてすぐに活動を入れることで欲求を満たすことができる場合があります。活動は、リレー音読、漢字の空がき、九九の暗唱、フラッシュカードなど、子供が集中できる活動であればなんでもよいのです。
また、活動とは、体を動かすことだけでなく頭を動かすことも入ります。
国語では全員で音読した後、「教科書には、『真っ赤な顔で言いました』って書いてあるけど、声の大きさは大きかった? 小さかった? 周りの人と話し合ってみて」と、登場人物の気持ちに迫る発問をすることもあります。
もちろん、授業の初めだけでなく、集中が途切れてきたなと思ったら「自由に席を立って友達と意見を交換していいですよ」など、体を動かせる活動を取り入れることで子供たちの欲求がリセットされることがあります。

