火中の栗を拾う【玄海東小のキセキ 第7幕】
- 連載
- 玄海東小のキセキ
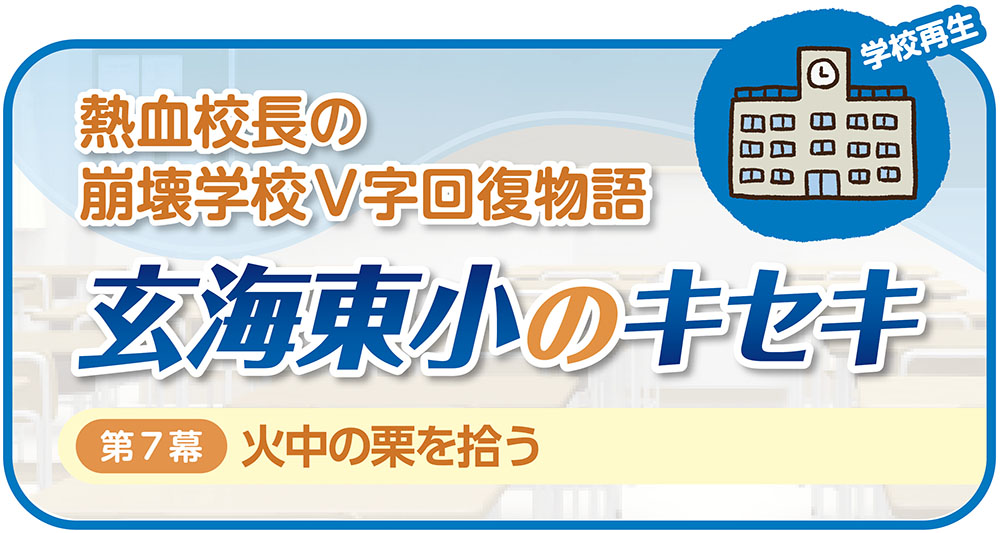
宗像市教育委員会主幹指導主事の脇田哲郎は、学級が崩壊した原因を探るべく、玄海東小学校に聞き取りに入ります。すると、4月の段階から3年生のクラスが荒れていることが判明しました。校長や教頭は転校生の問題行動がその発端だと語ります。すぐにでも荒れを収束させたい校長は、あくまで対処療法的な対応に終始するのでした。
目次
半年も放っておかれた学級崩壊

2008年10月上旬に行われた玄海東小学校の学校訪問で主幹指導主事の脇田哲郎は、私語が絶えず、教科書を開かない子供たちの姿を見せつけられた。
宗像市教育委員会に戻る道すがら、脇田は小学校が教育の場として機能しなくなっていることを学校教育の敗北だと受け止めた。授業が成立しない状況は、3年生から6年生まで広がっていたが、特に酷い3年生の学級崩壊をまず食い止めなければならない。
自分が玄海東小学校を担当しようと脇田は決めた。福岡県教育委員会から出向する形で宗像市教育委員会に勤務することになった脇田は、市教委から主幹指導主事の辞令を受けるとともに、県教委から校長職の辞令も出されていた。同校の担当を部下の指導主事に任せることもできたのだが、翌年度(2009年度)から実施予定の小中一貫教育の準備に部下の指導主事は忙しかった。脇田は校長資格を持つ主幹指導主事として校長を指導するという役割を優先したのである。
今後は、脇田が玄海東小学校の校長などから状況説明を聞き、なぜ学級崩壊が起きたのかを探るという聞き取りを行い、それを踏まえて校務掌理権を持つ同校校長が改善策を打ち出すというプロセスをとることになる。
それから数日経った秋晴れの午後、脇田は聞き取りを開始するために玄海東小学校に向かった。
玄海東小学校の玄関に立ち、ふと玄関脇を見ると、庭石に囲まれた小さな池があった。ずいぶん立派な庭だったが、池の水は涸れていた。入口の奥から子供たちの騒ぎ声と、担任たちが子供を叱る罵声が生々しく聞こえてくる。脇田は気が引き締まる思いがした。
玄関ホールには、廊下が左右に走っており、左に曲がれば低学年の教室に行く。脇田はそこを右に曲がり、校長室に向かった。
校長室の引き戸は閉じられていた。脇田はそれが気になった。これだけ学級が崩壊していれば、日々闘いという状況になるはずで、すぐに飛び出していけるように、扉を開けっぱなしにしておくものだがな、と脇田は思った。
引き戸を開けると、校長はそそくさとデスクから立ち上がり、スーツの上着を羽織ると、応接ソファを抜け、会議用のテーブルのところまで来て脇田を出迎えた。
校長室の壁には、波濤が描かれた100号(長辺約1.6メートル、短辺約1メートル)はあろうかという大きな油絵が飾られていた。玄海灘の波濤だろうか。ジョン・レノンが愛用していたような丸めがねをかけた細身の校長がその油絵の前に立つと、余計に体が細く見える。会議用のテーブルは10人ぐらいが囲めるような楕円形のテーブルで、脇田は油絵を背にした校長と対面する形で席に着いた。
脇田は校長に単刀直入に切り出した。
「3年生の授業が成立しない状況になって、どのように指導されましたか」
それに返答する校長の言葉は滑らかだった。
「子供たちはかわいいですよ。子供が悪さしたり、担任の言うことを聞かなかったりしたら、その子を校長室に連れてきて、こんこんと諭しています。担任の代わりに勉強を見たりもしていますよ」
「校長室で勉強ですか」
「ええ、そうです。漢字のプリントや算数のドリルをしています」
校長は担任たちと同じ視点に立っているようだった。子供が悪さをすれば、校長がそれに対応することは必要だが、それだけでは対処療法で終わってしまう。
「ひとりやふたりを個別に生徒指導したところで、荒れが収まりますか」
「子供とはその都度、しっかり向き合うことを心がけています」
校長室で教え諭すことと、子供と向き合うことは、事後指導という意味では同じことを言っているに等しい。子供の問題行動に対する未然防止に向けた予防的な指導を整備していくことが校長の仕事ではないのか。校長には、学校全体で荒れを何とかしようという発想がないようだった。
校長は、子供たちの騒がしさを抑える日々を送るせいで、胃痛に悩まされ、ぎっくり腰に何度もなったとも言った。しかし、それについて脇田は同情を示さなかった。大変なのはむしろ子供のほうだと思ったからだ。
「校長室は子供を指導するところではありません。校長室は学校という組織を動かす学校経営の最前線基地ではないですか。学校全体で子供たちの荒れに対応することを考えてください」
指導主事が行使できるのは学校経営に対する助言にとどまり、具体的にこうしろとは言えない。しかし、つい持論が口を衝いてしまった。
脇田は次の質問に移った。
「なぜ3年生は崩壊したのですか」
校長は、「崩壊……」と言葉に詰まって少し間が空いたあと、「元気がよくて騒がしいとは思いますが」と言葉を添えた。どうしてそこまで言われなければいけないのかという表情が校長の顔に出た。校長には、学級崩壊の危機感がないのだろうか。
「そうおっしゃいますが、授業が成立していないではないですか」
校長の顔を覗き込むようにして脇田はたたみかけた。
「担任は懸命に授業をしてくれています」
そう言って校長は黙った。脇田は「3年生が荒れた原因は何ですか」と聞き直した。
校長は3年生が2年生のときは問題行動を起こすようなことはなかったと前置きして話し出した。
「ところが、2年生の3学期に転校生が転入してから非常に騒がしくなったのです。その転校生は男の子で、人を巻き込む力がありましてね。その子の反抗的な態度に周りの子供たちが同調し、抑えが急速に効かなくなったのです」
校長によれば、その転校生は運動が得意で、遊ぶときにはリーダーになるような男の子だという。性格は激しく、怒るときと沈むときの感情の揺れが大きかった。離婚して実家に戻った母親の手ひとつで育てられたということだった。
「では、ほかの学年は、なぜおかしくなったのですか」
「赴任当初から3年生と6年生が荒れ気味だったものが広がったのだと思います」
「ということは、4月から騒がしかったのですか」
校長の目が虚ろに動いた。前任校長との引き継ぎのなかで、当時の2年生が荒れているという報告はなかったと校長は言った。
「なぜ半年も放っておいたのですか。校長として何も仕事をしていないと言われても仕方ありませんよ」
脇田は自分より数年先輩の校長に対して失礼な言い方をしてしまったと思った。しかし、主幹指導主事という立場上、言うべきことは言わなければならない。
目の吊り上がった子供たちの叫び声が、脇田には悲鳴に聞こえた。3年生の学級崩壊に対する改善策を講じるように念を押して校長との面談を終えた。
重い空気が漂う職員室
続いて脇田は、校長室で教頭や教務主任に話を聞いた。ふたりとも髪型がきちんと整えられ、スーツ姿で校長室に入ってきた。理科が専門だという教頭は、いつも低姿勢で人当たりがよかった。教務主任は脇田が2002年度から2004年度まで宗像市立東郷小学校で教頭をしていたときの同僚で、パソコンを自作することが趣味だった。
そのころ、東郷小学校では算数教育に力を入れていたので、教頭の脇田は算数の授業を参観し、授業で気になった点を書いたメモを担任全員に渡していた。そういう関係があったから、少しは忌憚ない話が教務主任から聞けるかと思ったが、口を開いたのは教頭で、教務主任は同席しただけだった。
校長にしたのと同じ質問をすると、返答は校長と変わらず、転校生の立ち振る舞いが引き金になったという。
「その男の子は、どのような問題行動をとったのですか」
転校生は当初、授業中に頻繁に立ち歩くことが多かった。それが3年生になると、自分の気に入らなければ、友達に暴力を振るい、担任の指示に反発するようになった。
仲間を引き連れて行動することでクラスを牛耳るまでに発展したというのだ。
担任はその転校生を指導するたびに校長に預けた。校長はその子を校長室でこんこんと諭した。度重なる指導に対して転校生の母親は、前任の担任に対して、「なぜうちの子ばかりが悪いのか」と食ってかかるようになった。保護者との人間関係のこじれは担任に負担になったのだろうと教頭は話した。
その担任は病休となり、後任の担任に代わった。校長もその母親のクレームを受け止めたが、それは途中からだった。
「それはもう、すごい剣幕で」
教頭はいかにも困った顔をした。クレーム対応は初動が肝心だ。校長はその担任に、保護者としっかり向き合いなさいと指示するか、初めから校長が対応すればいいのだと脇田は思った。
「どう対策されますか」
そう聞かれた教頭と教務主任は、何を言えばよいかわからないという顔をして黙ってしまった。教室には、職員室とつながる業務連絡用のインターホンが設置されている。担任から支援要請の連絡があれば、すぐにクラスに駆けつけていると、教頭は絞り出すように話した。教頭にも事後指導の発想しかないようだった。
その翌日、脇田は担任たちに話を聞くために再び玄海東小学校に向かった。終業まで時間があったので、3年生の教室に足を踏み入れた。
「また来たと?」
脇田は急にひとりの男の子に話しかけられた。大人のことなど目に入らない子供たちではなかったのか。自分を認識している子供がいるとは意外だった。慣れてくれば、人懐っこいのだ。この子供たちは人とのかかわり方を知らないだけではないのかと、ふと感じた。それならば、人間関係を築く特別活動の手法が効くはずだと直感した。
担任たちが集まったというので、脇田が職員室に入ると、重い雰囲気が漂っていた。担任は50歳代のベテランが多く、どの担任もどっぷりと疲れていて笑顔のかけらもなかった。まずは担任たちとの関係を築こうと脇田は考えた。
「みなさんは一生懸命にクラスを運営されています。いま、直面している問題について、お聞かせください」
担任たちの口から出たのは、子供に対する愚痴だった。
「うちのクラスのAは、立ち歩くだけじゃなく、教室から出るようになったと」
「うちのBは、いくら指導しても言うことをきかん」
別の担任は校長の対応力のなさを漏らした。
「保護者がなんか言うてきても、校長が守ってくれん」
これに他の担任たちも「そうそう」と頷いた。校長が守ってくれないとは、件(くだん)の転校生の母親のクレームに対して、校長が盾にならず、前任の3年生担任と母親の間に入らなかったことを指していた。校長は担任たちから信頼されていないのかもしれない。担任たちには不満が滓(おり)のように溜まっていると脇田は感じた。
脇田は担任たちにも荒れについての原因究明や改善策を尋ねようと思ったが、そうすることを止めた。そんなことをしても、「何かをせないかんことはわかっています。でも、無理です」という返事が返ってくるのが関の山だ。
脇田のなかで、リーダーシップを発揮していない校長と、そんな校長をあまり信頼していない担任たちという構図が浮かび上がった。校長は、どのように荒れた学校を改善したらよいかわからず、お手上げの状態なのだと捉えた。それは教頭も同じで、残るは、教務主任ということになる。
教務主任ならば、学校の教育課程を作成する立場にいるから、学校全体で何かに取り組むことができるし、旧知の間柄だ。脇田は教務主任に自分のアイデアを提案してみようと考えた。
脇田は放課後の教室にいた教務主任に声をかけた。
「荒れを何とかせんといかんやろ。どうする?」
教務主任は返答に詰まった。学校全体での取り組みが必要だとする脇田の考えに教務主任は同意した。
「子供たちの気分を一新するような活動をしてみんですか」
そんな活動があるのかと教務主任は興味を示した。
「どげんするとですか」
「6年生が下級生と集会活動をして遊ぶんよ」
脇田は、声をかけてきた子供の顔を思い浮かべながら、そう提案してみるが、「集会活動ですか……」とつぶやいた教務主任の表情は曇った。当時、教務主任は40歳代前半で、50歳代の担任たちを動かすのはなかなか難しく、年度途中で新しい活動をすることを担任たちはきっと嫌がるに違いないと嘆いた。教務主任は脇田の提案に理解を示したものの、集会活動をやってみようとはしなかった。
校長や担任たちは学級崩壊に対してあくまで即効性のある解決方法を求めていた。しかし、そんな方法があるのだろうかと脇田は思った。
教室を巡回して脇田が気づいたのは、担任と子供たちの間には、叱り叱られる関係しかないということである。子供との信頼関係を築いていないので、担任の指示が子供たちに通らない。脇田は担任たちに、子供との信頼関係をつくりたかったら、子供を叱り過ぎるな、とアドバイスした。
脇田は若いころ、叱る指導を止めると決意したときがある。初任校である福岡県宇美町立宇美東小学校に勤務して7年目、3年2組の学級開きのときだった。担任の脇田が教壇に立つと、女の子たちが怖がるような眼差しで脇田を見ていることがわかった。ある女の子は泣き出しそうな顔をし、ある女の子の顔は引きつっていた。当時、脇田は学校で一番怖い先生と言われていたのだ。子供が言うことを聞かないと、同僚の教員が「脇田先生のところに連れていくぞ」というのが殺し文句になっていたくらいである。
そのとき、脇田はハッと気づいた。厳しく指導すれば、子供たちはついてくると考えていた自分が間違っていたと思った。怖がる子供に罪はない。自分の指導力が足りないせいではないのか。それまで子供を叱るたびに後味の悪い思いをしていた。
何も叱らないうちから子供たちに怖がられたことで脇田は踏ん切りがついた。その日から子供を叱ることを止めた。そんな自分の経験から、叱り過ぎるな、と玄海東小学校の担任たちに指導したのだ。
後年、脇田が還暦を過ぎたころに、担任を受け持ったいくつかのクラスが合同して同窓会が開かれたことがある。叱ってばかりいたそのころの子供たちに謝れるものなら謝りたいと思っていた脇田は、そのとき、もう40歳代後半になった教え子に向かって、「あのころは叱ってばかりだった。自分の指導力がなかったもんやから、ごめん」と謝った。
脇田には、玄海東小学校の子供たちが昔の教え子と重なっていた。


