4年生担任になったあなたへ1年間の見通し&10の戦略!

校長先生より4年生担任を命じられたあなたは、どんな担任になればよいでしょうか。
4年生は、学校のリーダーとしての高学年への橋渡し、自立して何でもやっていかなければならない学年です。学級では? 授業では? 指導にはどんなコツがあるのでしょうか。どんな心構えを身に付けさせることが必要でしょうか。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
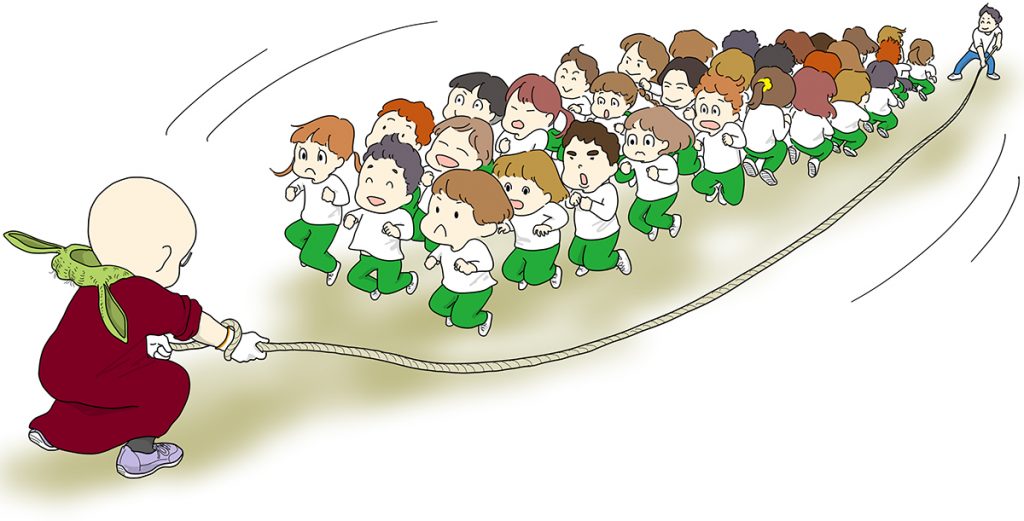
目次
学習指導・生徒指導編
1 学習を俯瞰する
担任を拝命したら、4年生で指導する内容を見ていきましょう。4年生の特徴として真っ先に挙げられるのが、前学年までと比べて抽象的な内容の学習が多い、ということです。
また4年生では、一段と見通しをもって学習することに重点を置き、本時の前後の学習との関連を密接にとるようになっていきます。3年生までも学習の見通しをたてて取り組むことはありましたが、1時間の授業をしっかりやろう、という方に重きが置かれていました。
4月はじめは、まず教科書を配付したら、担任のリードでざっと各教科の内容を見通してみることです。
そして、各教科ではどんなことを学ぶのか、どんな視点で学ぶのかを学習に入る前に教科書全体を見通し、児童とともに学習計画を立てていきたいです。
もちろん、学習の途中で児童に新たな問いや課題意識が出てきたら、それらを取り入れていっても良いわけです。まずは、学習を俯瞰することが大切です。
2 積み上げ、振り返りを生かす
4年生の学習では、前時で学習したことを取り入れて学習問題に取り組み、学習課題を解決していく学習が必要です。つまり、積み上げていくことが大切です。
前時の授業の終わりに書いてもらった「振り返り」から、児童の課題意識や問いを最初に紹介することもいいですね。社会科や理科、総合的な学習の時間では特に有効です。
また算数を例にすると、画用紙などに前時で学習した1時間の流れや結論などをまとめておき、掲示資料にしてみましょう。その掲示をもとに、本時の学習課題に取り組ませるという流れも良いです。
この方法はちょっと手間がかかりますが、画用紙1枚くらいへのまとめは、さほど時間がかかりません。かかった手間以上に、効果抜群です。
ほかの教科でも児童のノートに記載された「振り返り」だけではなかなかはっきりしないことも、授業者がシートにまとめておくことで、より便利に使えるようになります。
また、この振り返りをタブレットで記入させておく習慣をつけさせて、都度都度ロイロノートやGoogle Classroomなどでクラス全員が共有するのも良いでしょう。友だちがどんなことを考えているかを知ることで、一層学びに深みが出てきます。
3 品のある? 公的な会話の仕方を身に付けさせる
低学年のうちは、単語トークで、「せんせい、トイレ」「給食、おかわり」「はい、これ」などという語が飛び交っています。
3年生くらいでだいぶ、公的な場所での公的な言葉づかいが身に付いてきていますが、4年生ではそれを完成形にしたいです。
モデルの会話を示して、時にはやり直させ、できたら「すてきな言葉だね」とほめる。それくらい手間をかけて身につけさせたいです。
「せんせい、トイレに行ってきます」『はい、どうぞ』
「スープのおかわりをください」『はい、どうぞ』「ありがとうございます」
「うちからのお手紙です。お願いします」『分かりました。受け取りました』
こういった指導を繰り返し、小さなコミュニティとしての学級集団の質を高めていきたいですね。
4 伝える力を伸ばす
4年生では、学んだことや練習したことの発表が、全体からだいぶ個に移行してきます。
個人による発表の機会が増えるということです。
コロナ感染がだいぶおさまってきて、思い切った対話のある学習が組めるようになってきました。このチャンスを生かしていきたいです。
外国語活動(英語)では、スモールトーク、チャンツなどがたくさん出てきます。これらを適宜配置し、対話する機会、友だちと接する機会を多くしてみましょう。
また、学習しまとめたことを話す機会、発表の機会を多く設けて相手に伝えていく力をもたせたいです。
表現には制限を設けず、のびのびとやらせて良いと思います。例えば学校には、学習した漢字だけしか使っていけないという謎のルール(?)がありますが、国語の単元で出てきた漢字だけにとどまらないで、どんどん使わせてほしいです。
特に発表の掲示資料で習ってない漢字まで使うようになると、それにつられて多くの友だちが読めるようになります。
こうして伝える力を伸ばすことで、次年度の児童会活動やクラブ活動では、いっそう活躍するようになっていきます。
5 暗記ものの楽しさを味わわせる
人間はあらゆる年代で、違った才能が開花し、種類の違うものを覚えることができるそうです。
4年生は、何かと何かをくっつける総合的な暗記よりも、単発的な暗記力がぐんと伸びる年代で、学習内容と組み合わせれば、どんどん暗記ができるようになります。
社会科で言えば、自分の居住する県の市町村、そして日本全国の県名や県庁所在地などの暗記がその筆頭ではないでしょうか。
社会科イコール暗記ではないですが、覚えておけば、のちのちのさまざまな調べ学習での広がりのヒントになり、何かと何かをくっつけて新しい展開が望めます。
学級づくりや国語での取り組みとして、「○月の暗唱詩」なども素敵ですね。
小さい学校であれば、校長せんせいや教頭せんせいに暗唱を聞いていただきサインをもらう、という取り組みも可能ですね。他のせんせいに関心を持ってもらい、ほめてもらうことは意義深いです。
それが叶わない場合は、担任のスキマ時間を使って聞いてあげるようにしてほしいです。
このほか、地図記号、星座、昆虫、植物、英単語など、児童の実情に応じて計画していくと楽しいです。
させられる強制的暗記ではなく、自分でどんどん進んで暗記していけるようなしかけをつくってみたいですね。さまざまなジャンルに興味を持つようになります。

