先生は「教える」、子どもは「教わる」【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第7回】

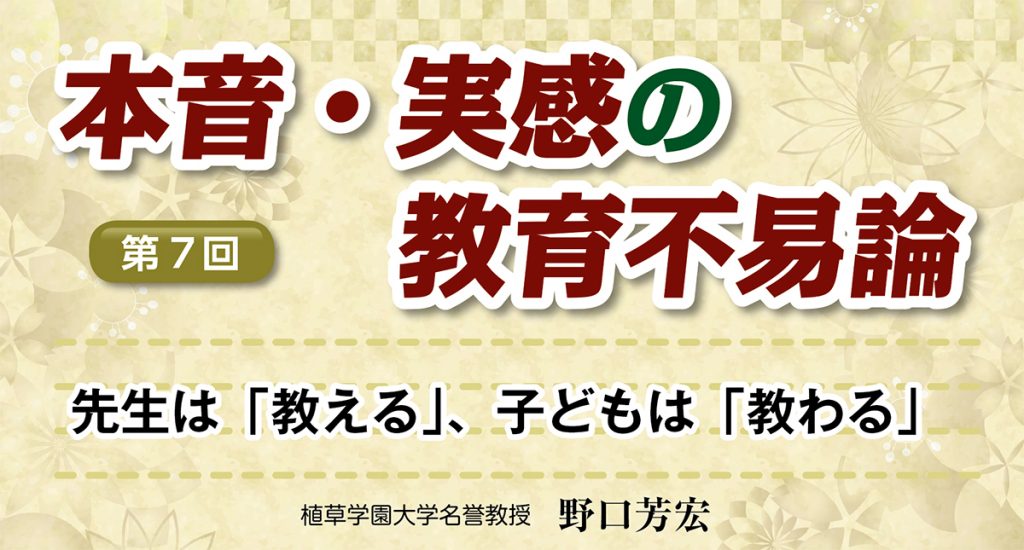
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第7回目は、【先生は「教える」、子どもは「教わる」】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 人は人によって人となる
この言葉に出合ったのはいつ頃のことだったろうか。大きく、深い感動を味わった。何と重く、何と確かで、何と真っ当なことか。「人」が三度出てくるが、私はこれを「ヒトは、教育によって人間になる」と解している。ヒトは動物の一属である。誕生のヒトは人間にはなっていない。それが、社会生活のできる人間になるには「人によって」という手続きが必要だというのだ。
ここにある「人によって」というのが、まさに「教育によって」なのである。そうだ。ヒトは、様々な教育を受けることによってのみようやく一人前の「人間」、つまり、人と人の間で暮らせる「社会性」を身につけていくことになるのである。
誰の言葉か分からないまま数年を経た某日、静岡の常葉学園大学での講演を頼まれ、この格言を引用、紹介した折に、「どなたか、出典を教えてくれませんか」と問うたところ、さっと挙手をした方があった。
「それはドイツの賢哲、カントの言葉です」と明言されて驚いた。何と西洋哲学の先生とのこと。全く、どんな方が来聴されているか分からない。丁重に感謝を述べ、以後必ず「カントの言葉だそうです」とつけ加えることにしている。
「ヒトは、教育によって初めて真っ当な人間になっていけるのだ」というこの名言は、教育者の我々にどれほど大きな勇気と誇りとを与えてくれることだろう。
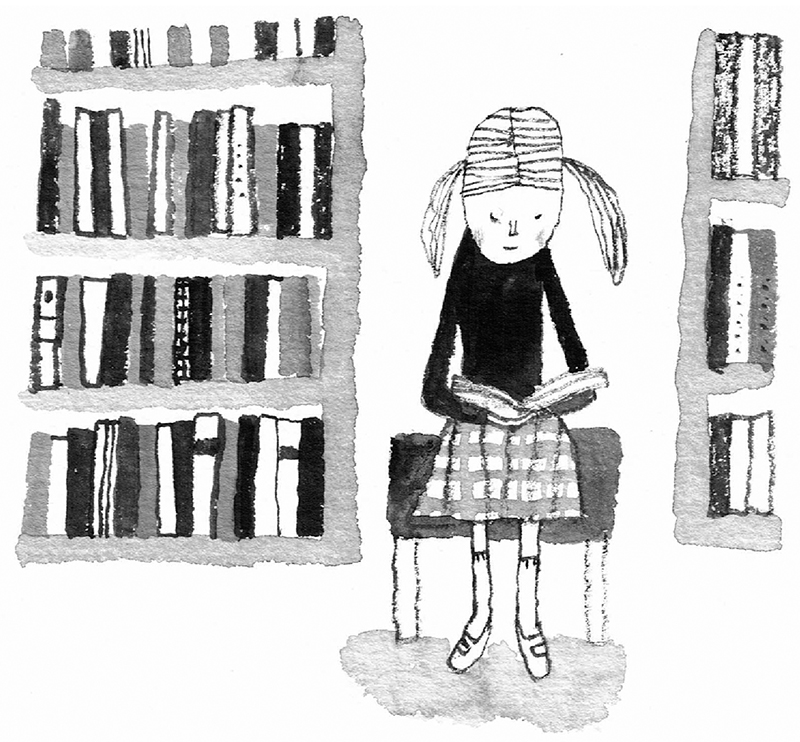
2 教育界に広がる子ども中心主義
ヒトを人間たらしめる営為を教育と言う。その営為とは、「教える」ことであり、その働きかけを受けとめることを「教わる」と言う。教育は、「教える」側と、「教えられる」側によって成立する。これが、教育という営為の原形であり、それが、教育ということの原理であり、根本である。
その故にこそ、教える側を教師と呼び、教員と言うのだ。また、教える部屋が教室であり、教える材料を教材と呼ぶのである。
近時この原点、原形、根本が古いのだと言い出した一部の人が、教材を学習材、教室はむしろ学室と呼びたいなどと小賢しい言辞を弄しているようだが、私は反対だ。
教わる者よりもはるかに高い所に教える者が立つのは当然のことだ。「仰げば尊し、我が師の恩」「三尺下がって師の影を踏まず」などの古来の言辞は、この間の事情を明確に示して揺るぎない。
本当に学習材と言うのなら、大人はそれに関知すべきではない。子どもが学ぶ材料を自分で選んでこそ学習材だが、そんなことができる訳がない。仮にそれが望ましいのなら「教師」そのものが不要になる。さすがに教室に代わって学室なる語が広まる気配はなさそうだが、「学習材」はしばしば耳にする広がりを見せていて嘆かわしい。
二昔前に「支援」と「援助」という言葉がはやって「学習支援案」「学習援助案」などと書く例があった。「誰に言われたのか」と問うと、「指導主事から言われた」と言う。私は、「えっ、指導主事? 支援主事じゃないの? 援助主事じゃないの?」と反論したら何も言えなくなって大笑いになった。
机間巡視という言葉が、管理的だと言って「机間指導」などと言う人があるが、それもまた笑止の沙汰だ。「巡視」の中の働きの一つに指導はあるが、他にも子どもの反応の分類や、当否や、指名計画や、指導方法の修正など、指導以外にも多くの機能を持って「巡視」と言うのである。先人の命名した深い意味も学ばずに、新しがり屋が思いつきを語るのも滑稽だが、すぐにそれらに同調する現場の軽薄さも悲しい。
このような一部の新しがり屋の次のような言葉が結構現場に広がり、汚染の度を深くしているようだ。
㋐子どもが授業の主役となって「自ら学び自ら考え、自ら解決して」いくようにしなければならない。先生が前に立ってあれこれ教える形は前世紀の遺物だ。
㋑授業が始まったら、子ども自らが「目的的、主体的、自発的に」席を離れて学び合う姿こそが望ましい。先生がどこにいるのか分からないような教室こそが理想だ。
㋒先生の考えを押しつけたり、子どもの考えを一方的に論断したりするな。もっと子どもの個々の考えを尊重すべきだ。
㋓子どもは無限の可能性を孕み、どんな子どももそれぞれに価値のある考えを持っている。それらを教師が否定したり、批判したりするのはよくない。
㋔答えが一つではない問題を自由に考えさせることが、子どもの柔軟な思考力を育てるのだ。教師はいつも一人一人の個性の味方にならなくてはいけない。
いずれも、一見まことしやかに聞こえるが、無責任な子ども中心主義の言辞である。こんな言葉に釣られているから、塾が繁昌するのだ。公教育の専門機関が子どもの学力形成や人間形成に無力だから、親は学校が終わると子どもを塾に走らせることになるのだ。
さる塾の経営者がそっと私に囁いたことがある。「ここだけの話だけど」と言ってから、「塾に来る子の親の職業を調べたら、学校の先生が一番多かったよ」と言ったのだ。他人の子どもには役に立たないことを教え、自分の子どもは塾にやるというのでは、一体日本の教育はどうなるのだろう。

