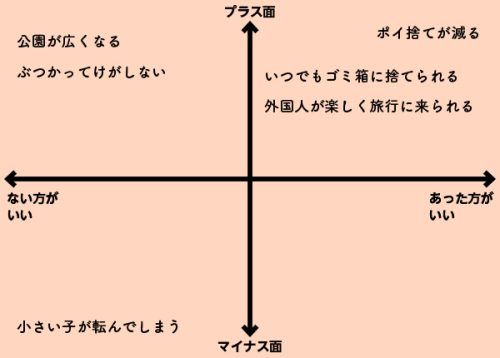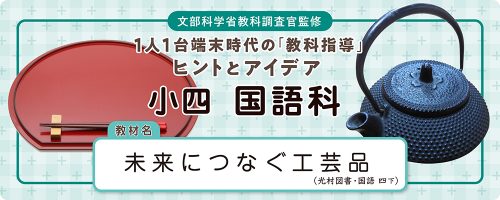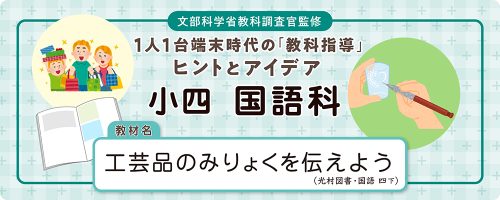小1算数「ひきざん」指導アイデア(1/12時)《13 -9をブロックをつかってかんがえよう》
執筆/福岡県公立小学校教諭・石丸こずえ
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井 健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準準
(本時の位置 1/ 12)
本時のねらい
10のまとまりに着目し、具体物を用いて計算の仕方を考える活動を通して、減加法を理解することができる。
評価規準
繰り下がりのある減法の計算の仕方を、10 -(1位数)という既習の計算に帰着して考えることができる。(数学的な考え方)
問題場面
ドングリが 13こ あります。ドングリを □こ つかいます。なんこ のこりますか。
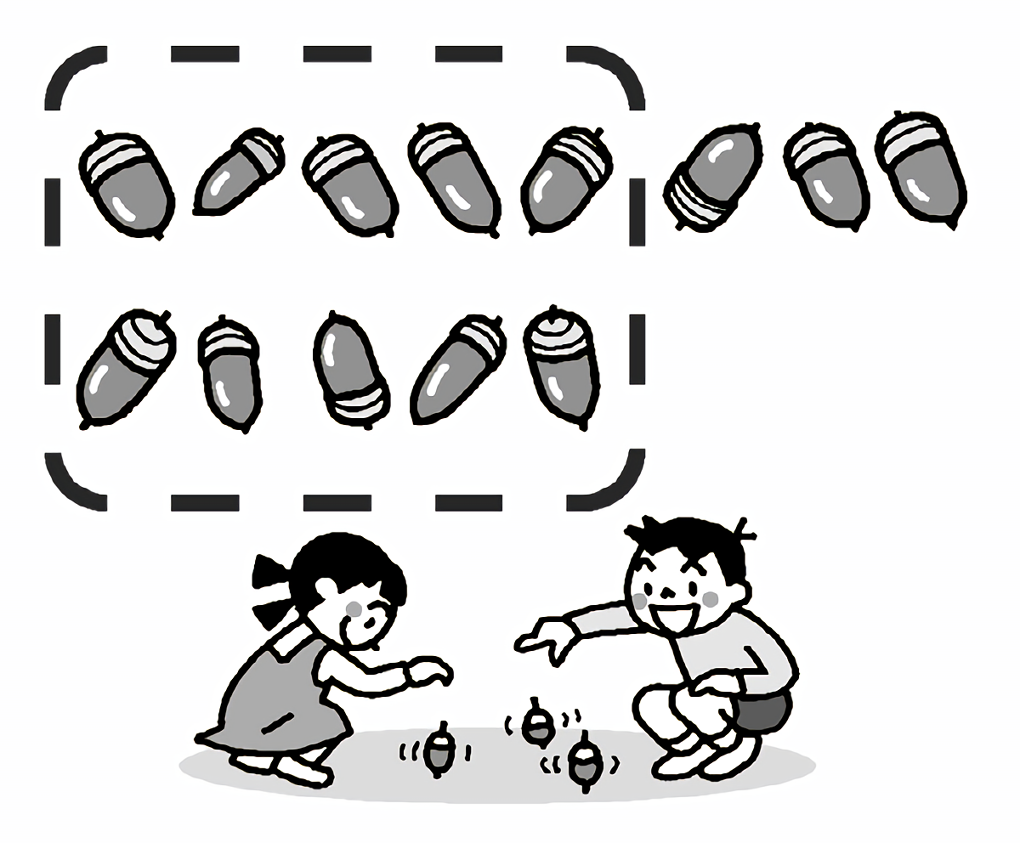
※問題文の減数の部分を□にし、既習の学習内容を確認します。
2個使うと、何個残りますか。式を立ててみましょう。
13 -2です。
なぜ、ひき算なのですか(演算決定の根拠を問う)。
「残り」を、求めるからです。
計算してみましょう。
11 個です。
3個使うと、何個残りますか。
13 -3で、答えは10 個です。
9個使うとき、式はどうなりますか。
13 -9です。
できそうですか?
難しいです。3から9は引けません。
これまで、何を使って計算の仕方を考えていましたか。
数図ブロックです。
では、数図ブロックを使って、9の引き方を考えていきましょう。
本時の学習のねらい
13 -9の こたえの みつけかたを、ブロックを つかって かんがえよう。
見通し
・数図ブロックを使う(方法の見通し)。
自力解決の様子
ドングリと同じ数だけ、数図ブロックを出しましょう。ここから9個取ります。できるだけ、さっと取れるとよいですね。どこから、どのように取ったらよいのかを、考えてみてください(少し考えさせる)。
それでは、先生が「せーの」と言ったら、9個取ってもらうよ。
「せーの!」
(9個取ったら手を離させ、操作の跡が見えるようにする)
みなさん、いろいろな取り方をしていますね。 どこから、どのように9個取ったのか、説明してもらいましょう。
A:つまずいている子
引く数を、間違える。
10のまとまりからの9個だけでなく、ばらの3個も引いてしまう。
B:素朴に解いている子
1つずつ、引く。
ばらから、引く(減減法)。
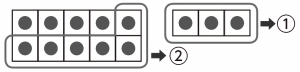
C:ねらい通りに解いている子
10のまとまりから、引く(減加法)。
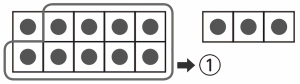
自力解決と学び合いのポイント
イラスト/佐藤雅枝
『小一教育技術』2018年12月号より