スモールステップで身につける!理科授業での「表計算ソフト」の活用 【理科の壺】

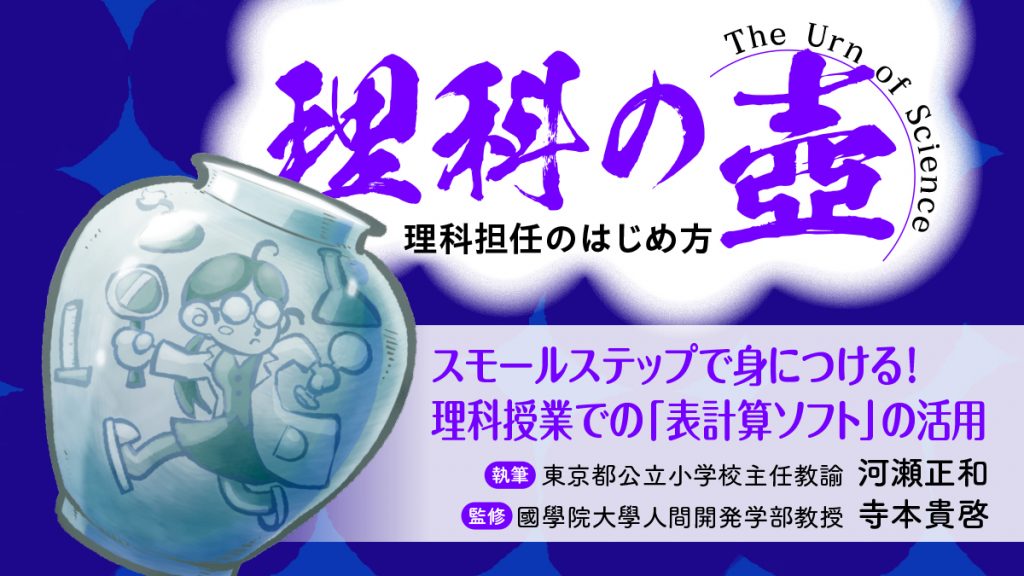
1人1台タブレット端末が配付され、タブレットを使った授業に取り組んでいることと思います。しかし、理科の授業でどのように使ったらよいのでしょうか? カメラ機能以外にも何か有効に使えないかな? そんな悩みはありませんか。今回は、理科の学習で表計算ソフトの活用について考えていきましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校主任教諭・河瀬正和
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.「表計算ソフト」の活用は難しい?
表計算ソフトに入力するよさは、今までノートに書いていた表を、マスの数やレイアウト、文字数などを考えながら書く必要がないことです。また、表ができてしまえば様々なグラフを簡単に作れることが、大きなよさと考えます。
表計算ソフトを活用するからといって、いきなり表やグラフをつくることはなかなか難しいかもしれません。なぜならば、表計算ソフトの使い方自体を教えなければならなかったり、表計算とあるように、入力したら計算するように式を入れなければならないという、授業前の準備が必要になったりするからです。
表やグラフは、書くことが目的ではなく、表やグラフから、結果や考察で情報を分析することが大切です。
そこで、児童が数字や文字を入力したり、グラフを表示したり、といった経験を、スモールステップで積み重ねていくことで、児童自らがゼロの状態から書くより、簡易かつ着実に表やグラフを作成し、結果や考察に生かしていくことが期待されます。

