小1算数「10より大きいかず」指導アイデア(1/7時)《いくつあるのかすぐにわかるならべかたをかんがえよう》
執筆/福岡県公立小学校教諭・加藤恵美
編集委員/ 国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
単元名「10 より大きいかず」
本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/7)
【本時のねらい】
10 のまとまりに着目して、20 個より少ないブロックの数え方について考える活動を通して、「10 のまとまりといくつ」に分けて数を捉えることができる。
【評価規準】
20 までの数について、数詞を唱え、数えることができる。(技能)
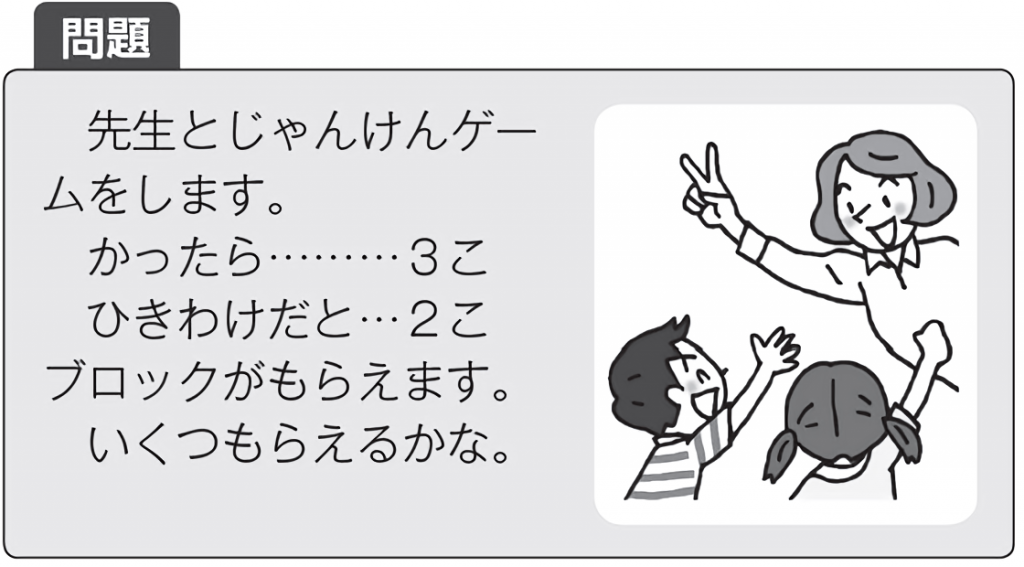
みなさん、じゃんけんゲームを楽しくできましたね。
ブロック、たくさんもらえました!
AさんとBさんがもらったブロックは、このようになっています(異なる並べ方を黒板に提示する)。
どちらが多いか、すぐにわかるように並べられるかな。
導入のじゃんけんゲームは、多くの子供が10 個以上取れている様子が見られたら終了します。そして、13 個の複数の配置を提示します。実際の子供の例をICT を活用して提示してもよいし、あらかじめ準備した架空の例でもよいでしょう。この提示によって、配置がばらばらだと、ブロックの数を比較しにくいことに気付かせ、「数がわかりやすい並べ方を考える」という本時のめあてを導きます。
本時の学習のねらい①
いくつあるのか すぐにわかる ならべかたを かんがえよう。
【見通し】
まとまりを作って、並べる。
【自力解決の様子】
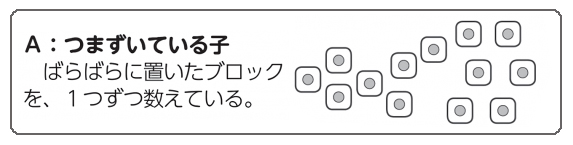
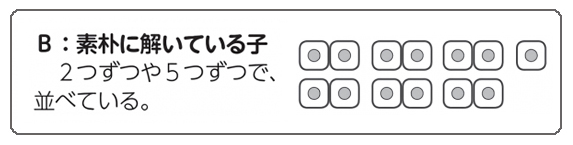
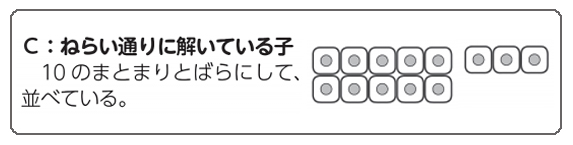
【自力解決と学び合いのポイント】
イラスト/佐藤雅枝
『小一教育技術』2018年9月号より






