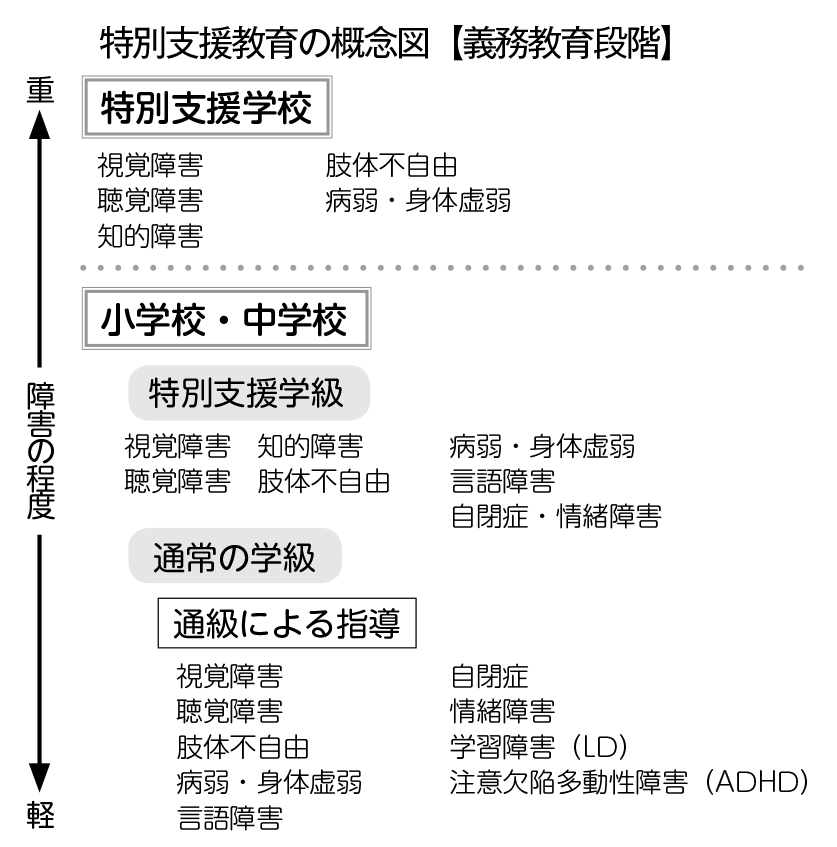学びの多様性を認める環境をつくる特別支援教育とは
特別支援教育と一言で言っても、とても幅が広く、奥が深いものです。ここでは、学校現場で何ができ、日常の授業でどんなことに配慮をしたらよいか、どんな工夫ができるのかを具体的に考えてみましょう。
執筆/福岡県公立小学校教諭・後藤和歌子
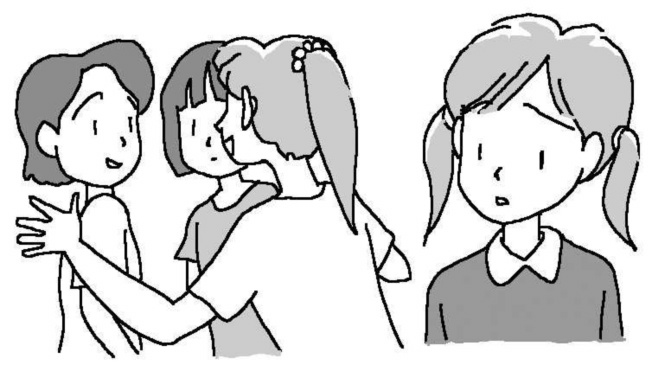
目次
どんなことに配慮すればよい?
①教師の気づき
- 同じことで友達とトラブルになっているな。
- 音読は得意なのに、書くことに強い抵抗があるな。
学校生活における子供の様子から、「あれっ」と気づくことがあります。その「気づき」が何より大切です。
②情報収集
様々な情報をもとに、子供が「どんな場面」で、「どんなこと」に困っているのかを多面的に探ります。
- 特別支援教育コーディネーターの情報
- 校内支援委員会の情報
- 担任やその他の職員の情報
- 保護者の情報
③共通理解
子供に関して収集された情報を、校内支援委員会で整理し、具体的な支援方法について共通理解を図ります。
・場面や相手によって対応が変わってしまうと、子供は戸惑ってしまいます。
・必要に応じて、保護者の了承を得て検査をしたり、専門家に助言を求めたりすることもあります。
④支援
子供たちをつなぎ、一人一人が安心できる「居場所」をつくることが大切です。つい、できないことばかりを意識しがちですが、その子の得意なことは何か、その子の強みは何かを見つけましょう。
その能力に着目した支援の工夫により、子供たちをつなぎ、安心できる居場所となる学級をつくっていきましょう。
⑤気をつけよう!
保護者に話をするときは、「○○障がいかもしれません」という言い方をしないようにします。「○○まではできていますが、△△の部分は苦手なようです」などのように、まず具体的にできていることを示して褒めた上で、気になる点について述べるようにしましょう。
教師は医者ではないので、診断はできません。保護者との意思疎通を図りながら話を進めることが大切です。