保護者と良好な関係をつくる教師の心がけと対応
「モンスターペアレント」や「我が子ファーストの親」などという言葉が、時折、マスコミ等で聞かれます。そんな保護者をつくらない方法やもしものときの対応の仕方について、日ごろより、気をつけておくことが大切です。
執筆/福岡県公立小学校教諭・藤井龍一

目次
保護者との関係づくりのための教師の対応
保護者の方も、担任がどんな先生なのか、期待と不安でいっぱいです。また、学校生活が見えないこともあり、心配な気持ちが膨らむことが多々あります。保護者の方が安心できる対応を心がけましょう。
日常的に気をつけたいこと
「メラビアンの法則」という言葉を聞いたことがありますか。人は、目と耳から入る情報がその大半を占めるというものです。服装や言葉遣い、表情(笑顔)に気をつけることで、保護者は安心し、信頼を獲得できます。
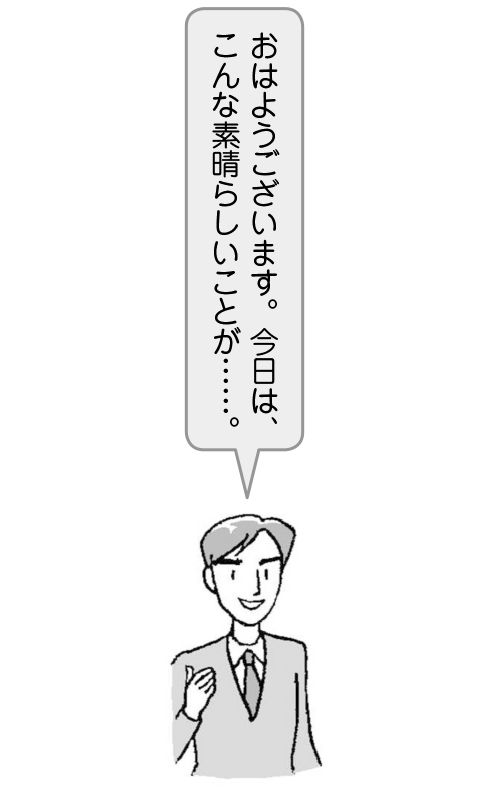
保護者への連絡で気をつけたいこと
保護者は、子供のことがとても気がかりです。けがや友達とのトラブルに関する連絡などは、こまめに行いましょう。
子供より先に情報があると、保護者は安心して子供の話が聞けるものです。

また、保護者への連絡内容が、子供の情報と違う場合には、保護者とトラブルになることがあります。
子供への聞き取りから、より確かな情報を、しっかり保護者へ伝えられるように、メモなどをとっておくようにしましょう。

連絡帳での対応で気をつけたいこと
保護者との連絡で最も多いのが連絡帳でのやり取りです。
連絡帳でのやり取りは、相手の表情が見えないので、対応には気をつけましょう。
学校や担任への苦情等に対して回答が難しいときは、「お電話でお伝えします」や「お家へ伺って、直接お話しをさせてください」など、文書での回答を避けて、直接会って話すようにしましょう。

子供との関係が親との関係
保護者は、子供の話をもとにして、先生の姿を想像するものです。子供が「優しい」と言えば、保護者は「優しい先生」と感じ、「遊んでくれる」と言えば、「子供想いの先生」と感じます。
子供たちとのよりよい関係づくりが親との関係づくりにつながります。


