少しの工夫で好感度UP!保護者との上手なコミュニケーション
新学年スタートの1か月は、子供と同時に保護者との信頼関係をつくるために大切な時期。人間関係づくりの上手なベテラン教師から、対保護者についてのアイデアを取材します。
監修/東京都公立小学校主任教諭・佐々木陽子
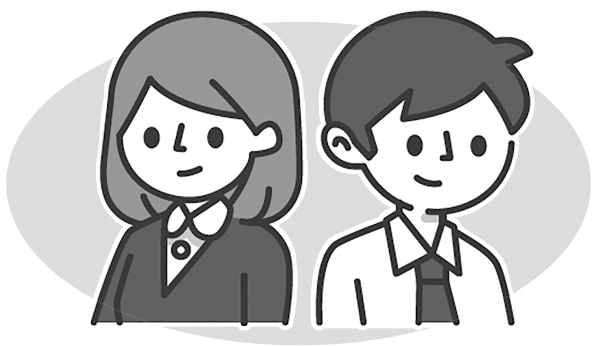
目次
保護者会
中身の前にまず外側を意識
保護者会では、第一印象が大事です。男女ともに紺、グレー、黒、茶の定番スーツの着用がよいでしょう。シャツや襟元に汚れやシワなどがありませんか? その細部に、教師としての心構えを感じる保護者も多いものです。
身なりをきちんとした状態でいれば、保護者から見て安心感があります。余計なところでマイナスに見られたり損をしたりしないためにも、あらかじめ服装の細部や髪型の確認をしましょう。
佐々木先生の経験談を一つ。当日スーツを着たらスカートのファスナーが閉まりません。体がふくよかになり、合わないことが発覚! しかたなく別のスカートを着用し、上下アンバランスな装いに……。こんなハプニングもあるので、事前に着用して確認しておくと安心です。
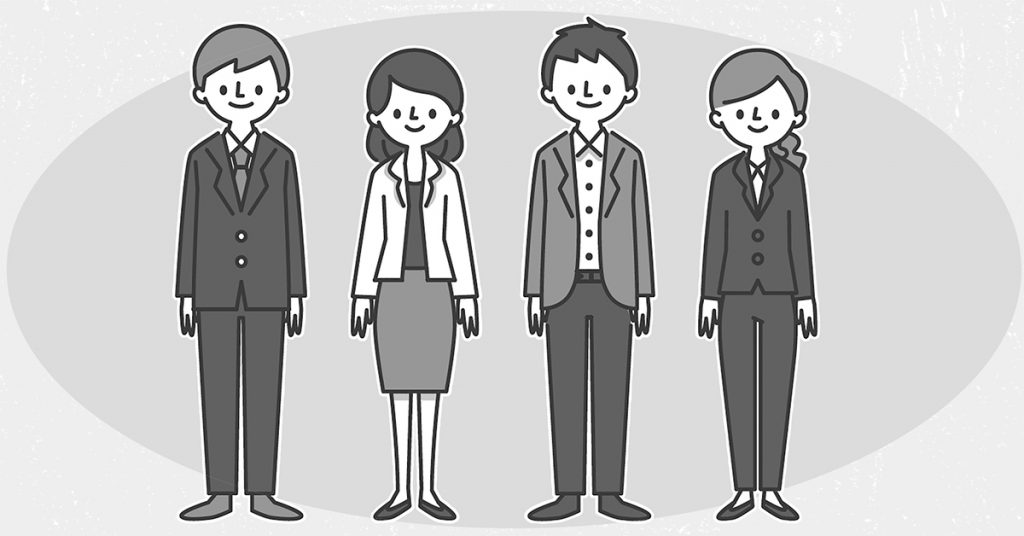
連絡帳・電話
謝罪やお礼の言葉を入れる
学校で子供にけがをさせてしまったり、物がなくなったりした場合には、「申しわけありません」などの謝罪の言葉を連絡帳の文面に入れます。事実だけを連絡帳に書くより、謝罪のひと言で教師の人となりが表れます。
また、保護者からの連絡ごとには、「ご連絡ありがとうございます」とのひと言を添えましょう。そのひと言で、コメントをしてくれる保護者が「連絡を入れてよかった」と安心します。
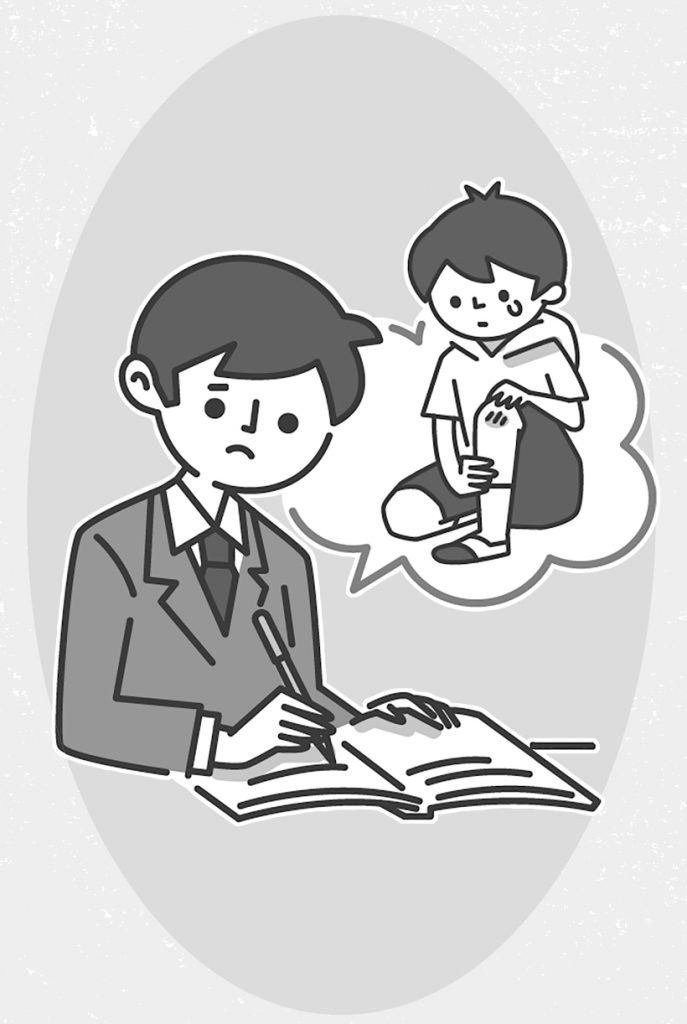
伝え方が難しいなら、電話を一本入れておく
連絡帳に書くことで誤解を招くような内容、伝え方が難しいと思うことは直接会う、あるいは電話で対応することをおすすめします。相手の反応を受け取りながら、正確な説明ができるからです。
詳しく言えば、連絡帳に書いたことはすべて証拠として残るものなので、言いわけができないうえ、表現のしかたや受け取り方に違いがあると事が大きくなり、トラブルのもとになりやすいからです。
「休み時間に走っていて転び、かすり傷のけがをしました。お家でも様子を見てください」などのちょっとしたけがなら連絡帳で伝えますが、「頭を強打した」など首から上の事故やけがなど、そのあとの容態が変わりそうな案件は電話で話しておきましょう。
また、「学習中に〇〇くんと喧嘩になり、定規が折れました」といった子供同士のトラブルや物の破損などは、双方の保護者に情報を共有しておかないと、後々トラブルの原因になることがあります。
状況が複雑なものであれば、連絡帳だけではなく、お互いの保護者に電話連絡を入れておくことが鉄則です。


