小3・4外国語活動:振り返りの時間を充実させよう

小学校外国語科検定教科書の編集委員でもある元神奈川県公立小学校の長沼久美子先生の好評連載! 年度末に学習を振り返る際のポイントを教えていただきました。
執筆/元神奈川県公立小学校教諭・長沼久美子
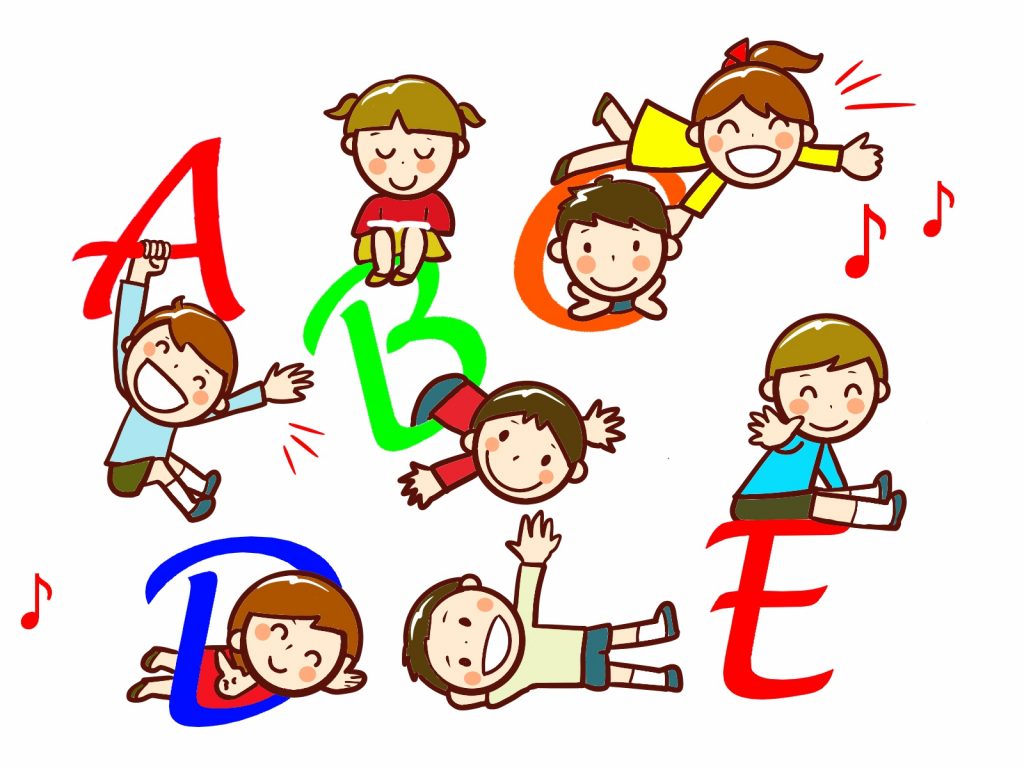
【関連記事】小3・4外国語活動:ヒントクイズのアクティビティのポイント
目次
Q1 3年生の年度末の外国語活動では、どのようなことを意識して取り組むとよいでしょうか。
(3年生『レッツトライ1』)
A.4年生に向けて、振り返りの時間を充実させましょう。
3年生の一年間の外国語学習で、「何を知り」「何がわかるようになり」「何ができるようになったのか」などについて、子ども自身が振り返る時間を設けましょう。自分自身の変化を知ることが、4年生に向けてのモチベーションになるからです。
振り返りの方法としては、振り返りカードを活用するのが簡単です。振り返りの項目を設けて文章で記述する方法から、3択や5択の選択肢から選ぶ方法などがあります。
「あいさつを聞いてわかる」「あいさつを言える」「友達が言っている好きなものが分かる」「自分の好きなものを友達に言える」等の項目に対して、「①ばっちり、②ときどき、③まだまだもう少し」の選択肢から選ぶ方法で、振り返りに取り組んでみてください。また、自由記述の欄を設けることで、詳細に振り返るのも効果的です。
項目選択式と記述式には、それぞれに利点があります。
例えば、「英語であいさつができる」という質問項目に対して、「できる」「だいたいできる」「できない」といったデジタル的な3項目や5項目の尺度から選ぶようにすれば、子どもはとても答えやすいはずです。
一方で、アナログ的、つまり記述式で答えてもらうなどすると、日本語の文章力のある子の場合、評価する側はその子供の状況が詳細にわかります。しかし、文章力のない子にとっては、きちんと書くことができず、振り返ることすらできないという状況になります。
低学年のうちは、記述をさせると顕著に文章記述能力的なものの差が出てしまい、見取りにくいことが多くあります。ただ、3尺度などの選択式だけでは、見取り切れないこともあります。項目選択方式と記述式の両方を取り入れるとよいでしょう。
振り返りは、子どもが自身の学習状況を知る意味でとても有効ですが、同時に、教師にとっても授業改善のために役立ちます。子どもがどのような気持ちで学習に向かっていたのか、どのくらい理解を深めていたのかなどの現状を把握することができるからです。
振り返りの際に注意したいこととしては、できていない自分と向き合うことになった子どもに対する支援の仕方です。
振り返りを終えた子どもが、
わたし、全然できてないのかも…
と落ち込んでしまっては、振り返りは逆効果になってしまいます。
その時は、鉄棒の逆上がりをイメージするように伝えましょう。
逆上がりを考えてみてください。くるんと回って降りてこられなくても、上の方まで足を振り上げることができる人は多いよね。それと同じで、「あと少し」!
クラスの3分の1くらいができているけれど、まだまだできない人も多いということはよくあります。
今できていると思えなくても、いつかできるから大丈夫だよ。また次の学年でも頑張ろうね
と、次学年への意欲へ繋げてあげてください。
外国語学習では、なかなかできるようにならないことは当たり前にあるものです。そのことも含めて、「何を知り」「何がわかるようになり」「何ができるようになったのか」、自分自身を見つめる振り返りが重要であることを、子どもたちに伝えていきましょう。
【関連記事】小3・4外国語活動:グリーティングカードを送るアクティビティのポイント

