国語の教材分析① ~教材分析で大切にしたいこと~

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 今回は、国語の教材分析において大切にしたいことについてのお話です。
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
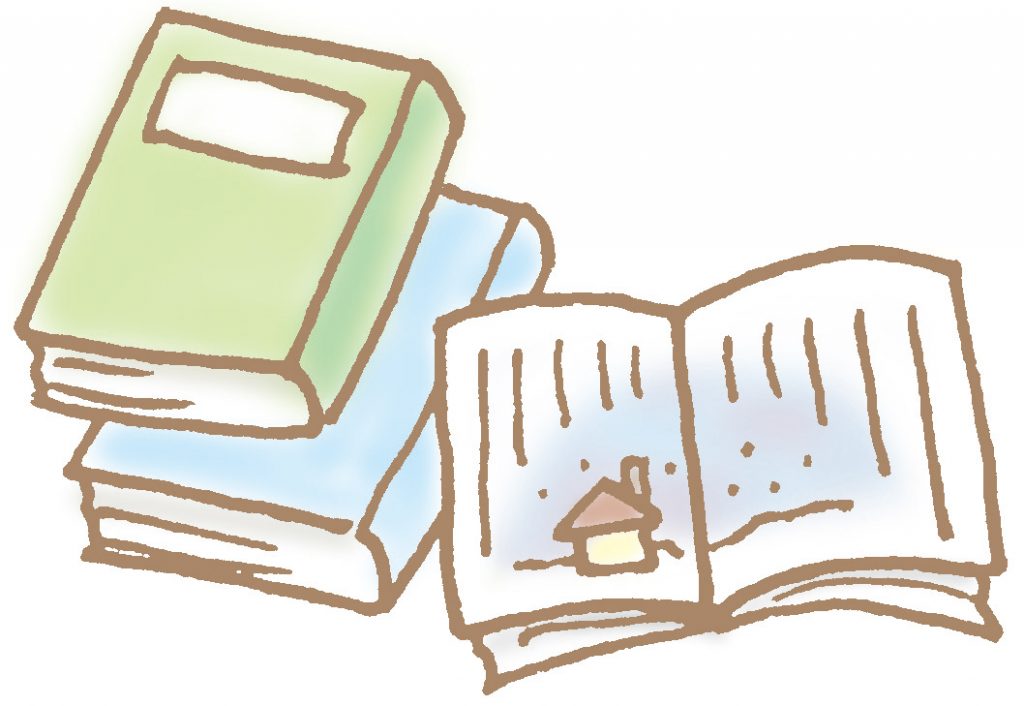
【関連記事】
子供たちに伝わる板書の書き方を徹底解説している特集。様々な事例がたくさん!→ 樋口綾香&樋口万太郎夫妻が解説! 国語・算数 伝わる板書のルール
目次
国語の教材分析の難しさ
私が冬休み中に、SNSで国語についての質問を募集したところ、いちばん多かったのが、「教材分析のしかたを教えてほしい」という内容でした。
これまでも、職場や研究授業の講師として訪れた学校、セミナー等で直接相談を受けてきました。多くの先生方が、国語の教材分析の難しさを感じられているのだと思います。
その中で最も多い困りごとは、「分析の仕方も、正解も分からない」というものでした。
この困りごとに対して、私は次のようにお答えしています。
「分析のものさしは先生によって違います。そして、分析後の解釈は、人の数だけあります。正解を探そうとすると、国語の授業づくりは楽しめません」
何もかもが分からなかったのは、当然私も通ってきた道です。今でも分からないことはたくさんあります。しかし、多くの教材を分析すればするほど、少しずつ知識は増えていき、いつの間にか分からないことや難しいことも楽しく感じるようになってきました。
どうしてそのように感じ方が変わったのかをお話しします。
【関連記事】
綾香先生が単元全体の板書とノート例を教えてくれるシリーズ!
単元丸ごと!板書&ノート① ~小一国語「やくそく」~
単元丸ごと!板書&ノート② ~小二国語「お話のさくしゃになろう」~
単元丸ごと!板書&ノート③ ~小四国語「プラタナスの木」~
単元丸ごと!板書&ノート④ ~小五国語「大造じいさんとガン」~
住田先生との出会い
私が教材分析の面白さを感じられるようになったのは、8年前に、大阪教育大学教授の住田勝先生にお会いして、毎月いっしょに分析をさせていただくようになったことが大きく影響しています。
住田先生に出会うまでの私は、何が分からないかも分からず、勉強不足な自分を恥じて、どこかごまかして授業をしていました。指導書を読んだり、先行実践を探ることで精いっぱいでした。
住田先生と行う学習会では、ひと月に1回、いつも8名ほどの教員が参加し、持ち寄った教材を分析します。
特徴は、自分が担任していない学年の教材分析もすること、そして複数で行うことです。
この二つが、私の国語授業づくりの視点を大きく変えました。

