コロナに負けない学力づくり① どの子も計算力をつける「さかのぼり」

コロナ明けで授業の遅れを取り戻すため、スピードを上げて授業を進めている先生も多いことでしょう。しかし、積み上げ型の教科である算数では、1か所つまずいてしまうと、その後もできないままになり、学力は身に付きません。特に基礎計算でつまずいていては、算数の理解は困難になります。既習の内容にまでさかのぼってくり返し学習し、苦手をつくらない算数授業を行っていきたいものです。withコロナでも短時間で無理なく取り組める学習法を紹介します。
大阪府公立小学校教諭・岡本美穂
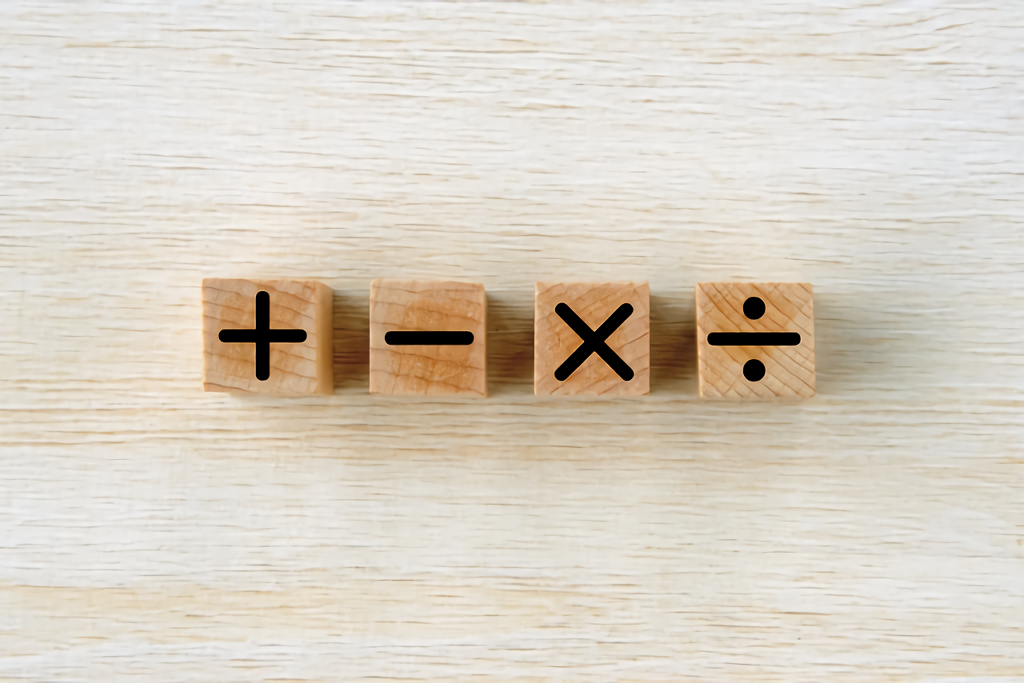
目次
さかのぼり学習のススメ
コロナの影響を受けて算数の日々の授業をどうにか進めることだけで精一杯になってしまい、「学力づくり」にまで意識がいかないのが現状です。
算数で一番大切にすべきことーーそれは「できる」という実感です。他の教科に比べると、友達との差も感じやすく、学年が上がるにつれて苦手と感じる子どもが増えていくものです。だからこそ日々の授業のなかでいかに「さかのぼり」学習を無理なく行えるのか、またそれと並行して新しい単元をどう学習していくのかが問われていきます。
さかのぼり指導とは、前学年まで学習した計算問題で、苦手な課題のおさらいをして、できるようにしようとする取り組みです。
算数は、未習事項を、既習事項に置き換えて考えるという特質があります。例えば、整数のわり算が苦手な子は、小数のわり算も苦手です。
くり上がりの計算とかけ算九九ができないと、けた数の多いかけ算や、わる2けたの計算ができないのは当然のことです。学年にかかわらず、苦手なところからおさらいをすることが、計算力をつけることにつながります。
そこで、まずは子どもたちの実態調査を行います。
子どもたちの計算力を知るには、「計算実態調査」を行うのが有効です。「徹底反復・新計算さかのぼりプリント」(1年~6年/小学館・久保齋)の各学年10題のプリントがおすすめです。
※「徹底反復・新計算さかのぼりプリント」は在庫僅少です。
算数の”健康診断”から始めよう
子どもたちには、「今からする計算のプリントは『健康診断』ですよ」と言っています。さらに、次のように話します。
「体がしんどい時に、病院に行って、どこが悪いか診てもらいますね。悪いところが見つかったら、そこを治すために、治療をしたり、薬を飲んだりします。おなかが痛いのに、頭痛の薬を飲む人はいませんよね。勉強も同じです。苦手なところはどこかを自分自身が知ることは、大切なことです。何となく、よくわからないけど算数が苦手だ、計算が遅いと思うのではなく、自分がどの計算ができて、どの計算が苦手なのかを知ることが、算数を得意にすることにつながるのです。」
と伝えます。自分のできることとできないことを自覚し、できないことをできるようにすることが、学習の基本です。計算力の差が、授業のリズムやテンポを乱すことにもつながります。そして何よりも子ども自身が「できない」と理解し意欲が低下していってしまいます。

