小6道徳「手品師」指導アイデア 誠実な生き方について合意形成を目指す
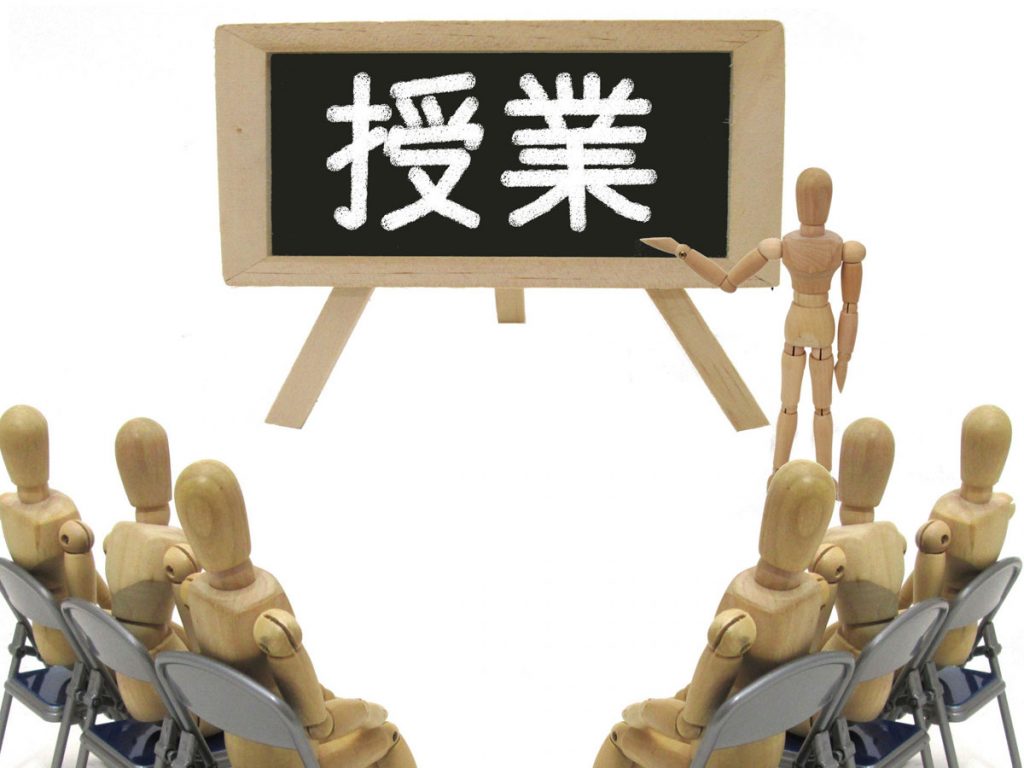
執筆/大阪府公立小学校・金大竜
教材名:「手品師」(日本文教出版「新・生きる力」)
内容項目:誠実に、明るい心で生活すること A[正直、誠実]
目次
授業の設計をする前に、内容項目について考える
道徳の授業を考える際には、授業の中身を考える前に、まずは内容項目について考えるようにしています。「手品師」の内容項目は、「誠実に、明るい心で生活すること。(A 正直、誠実)」です。
では、「誠実」とはなんでしょうか。辞書を引くと「偽りがなく、まじめなこと。真心が感じられるさま」とありました。さらに、「真心」を引くと「偽りや飾りのない心。真剣につくす心」とありました。
「手品師」の主人公の行動は確かに誠実です。それは間違いありません。しかし僕は、手品師の行動とは反対に、たとえ人との約束を破ってしまったとしても、自分の夢を追うことは、「誠実」で「真心」がある行為なのではないのかと考えます。
僕個人は、日本の道徳の教科書には、「自己犠牲、他者愛」を促すような教材が多いように感じています。だからこそ、そのような教材については特に、「本当にそうなのか?」と考え直すようにしています。そうして、様々な角度、立場からできる限りの考えを出します。
そうしたことを十分にした後、授業の最後にどのような話合いをすればそのような考えが出るのか、その話合いをしたくなるには教材とどのように出合い、どの部分をメインに扱うのかを考えます。
つまり、本時の内容項目に関して自分で考えた後、授業のゴールからスタートに戻っていきながら考えるイメージです。
思考が続くよう、授業をすっきり終わらせない
僕の考えた「手品師」の授業の展開では、子供たちが「手品師が選ばなかった行動は誠実ではないのか」と考えますが、それに答えはありません。答えを出さないまま授業を終えるので、子供たちはモヤモヤします。
こうして一見、当たり前だと思うことも、本当にそうなのかと考えることで思考が深まり、理解が深まります。大切なことは、そのことに問いを持ち続けることではないでしょうか。
すっきり終えるとそこで思考は止まります。モヤモヤすると、休み時間に友達と、家では家族と話す姿が見られるでしょう。このように思考が続くようにするのが深い思考のスタートだと考えています。
さらに自分とは違う考え方が、一定数は存在することを度も体験することで、世の中の問題は答えが一つではないこと、多様な面から常に考えることが求められること、考え・議論する必要があることを子供自身が感じ取れるようにしていきたいのです。

