特活の作品制作は「話合い」「合意形成」「役割分担」で
特別活動では、さまざまな作品を共同で制作します。作品づくりの活動は、ただ作ることを目的として活動するのでなく、児童同士が話し合い、認め合いながら、課題を解決していく過程がとても重要になってきます。そのような指導によって完成した作品の数々が、一冊の資料集にまとまりました。著者の福岡県公立小学校教諭・大久保利詔先生に指導のポイントを伺いました。
福岡県公立小学校教諭・大久保利詔さん

目次
特活の作品制作に込められた指導観とは
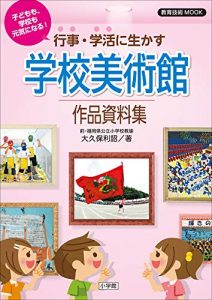
―本書 「子どもも、学校も元気になる! 行事・学活に生かす 学校美術館作品資料集」 の特徴を教えてください。
大久保 特別活動の実践を通して、子供たちが制作した様々なグッズを「学校美術館」として紹介しています。もちろんすべてを載せることはできませんので、その中からエッセンスとなる内容に絞ってまとめています。
第一章は、児童会活動に関する製作物、第二章は、学級活動に関する製作物、第三章は、児童会活動や学級活動の実践に役立てるための資料集となっています。これらは、私が子供たちと取り組んできた実践の38年間の足跡といえるものです。
これらのグッズは、単なる製作物という意味合いではありません。子供たちがよりよい学級・学校生活を築くために、本気で話合い、合意形成をし、役割分担をしながら制作したものなのです。

―先生は、「特別活動」の研究を長年続けてこられました。子供たちにはどのような指導が大切ですか。
大久保 子供たち一人一人に、よりよいクラスにするための視点に立った議題発見の力を付けさせ、学級会で話し合って解決し、学級のみんなで協力して実践するという経験を数多く積ませることが大切です。そして、成功感を味わわせ、学級全体で取り組むことのよさを実感させることです。
学級活動の指導は、児童会活動にも大きく影響を与えます。学級活動や児童会活動を通して、子供たちに自発的・自治的活動の体験を十分に積ませることが必要です。
高学年になると、中・低学年の夢も大切にする「全校的な視野」に立った活動も子供たちを育てることになります。そのような活動経験を豊富にさせることで、「全校から憧れをもたれる高学年」へと成長することができます。

