不登校①【わかる!教育ニュース #78】
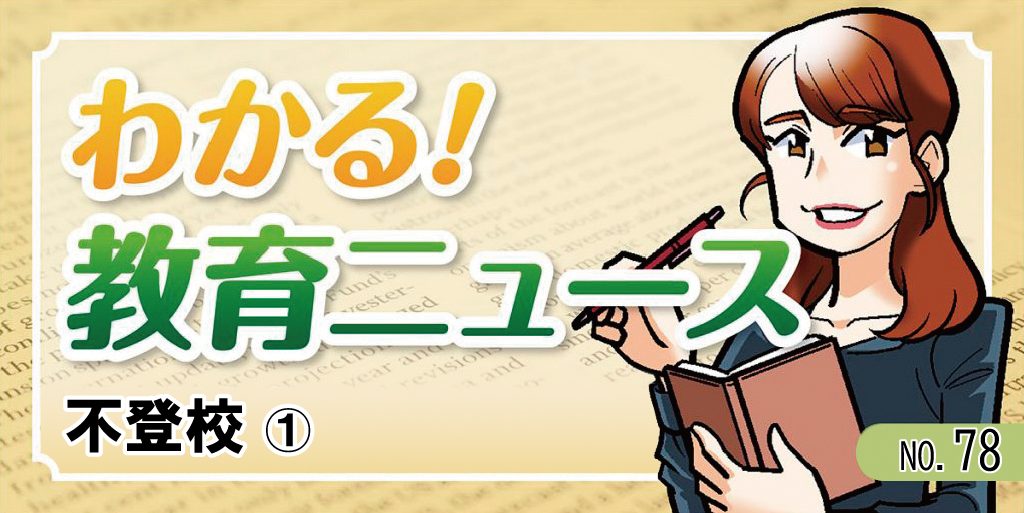
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第78回のテーマは「不登校」です。
目次
不登校の子のための「特別の教育課程」の制度設計に向けて、初会合開催
学校に行けない子供が、11年連続で増えています。2023年度の不登校の子は、過去最多の34万6482人。この子供たちの学びを支えるために、新しい教育課程をつくる議論が始まりました。
不登校の子のために創設する「特別の教育課程」の制度設計に向けて、中央教育審議会の作業部会が初めての会合を開きました(参照データ)。話し合う内容は多岐にわたります。まず、この新しい教育課程の基本的な考え方。次に、具体的にどういう子を対象にするのか。文部科学省は不登校の子すべてに行うわけではなく、学校が「特別の教育課程で指導したほうがいい」と判断した場合、という考えを示しており、「保護者の求めで実施義務が生じるものでない」とも付け加えています。
他にも、具体的な学習内容や授業時数、どこで学ぶのか、校外で学ぶことも想定した指導計画や学習評価、高校入試での学習評価の扱いなど、検討内容は様々。今後、月1回ペースで会合を開き、議論を重ねていきます。
近年、不登校の子供の数は増え続ける一方。文科省も学びの場の確保や早期発見などを盛り込んだ一連の対策「COCOLOプラン」を2023年3月にまとめました。学校に行けない子や、登校できても教室に入れない子を支援するために、校内外に設けた教育支援センターの増設や機能強化を目指すほか、指導要領に縛られず柔軟な教育課程をつくることができる「学びの多様化学校」を、現状の58校からさらに増やす考えです。

