「英語が嫌いな英語教師がいてもよいかな」【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #47】
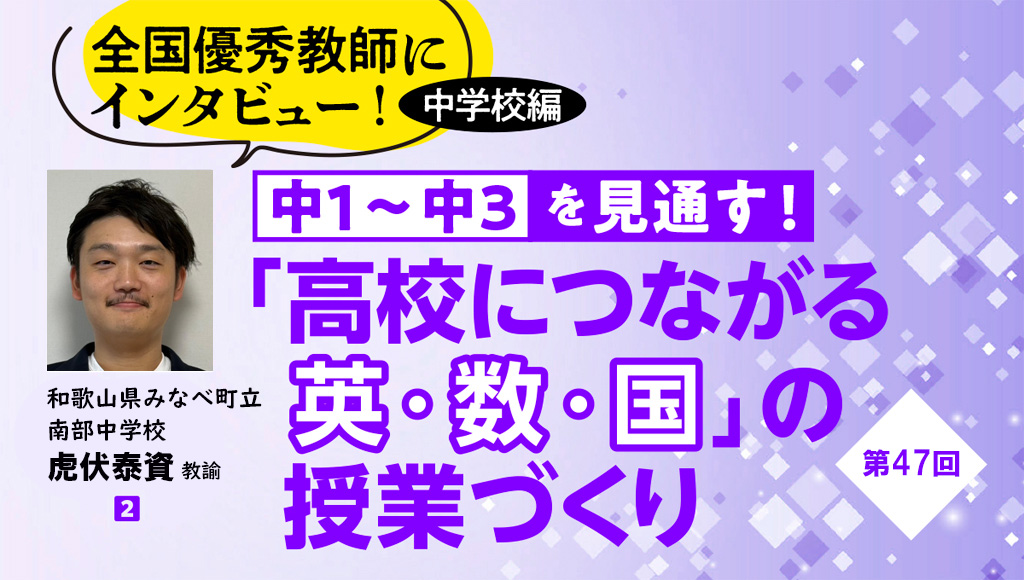
前回は、今年11月の全国英語教育研究団体連合会全国大会・和歌山県大会で実演授業を行う予定の、みなべ町立南部中学校・虎伏泰資教諭に、自身の授業づくりの考え方を象徴する1年生の授業例を紹介していただきました。
今回は、そのような授業づくりの背景となる考え方や教育観、また、そのような考えに至るようになった自身の英語体験について紹介をしていただきます。
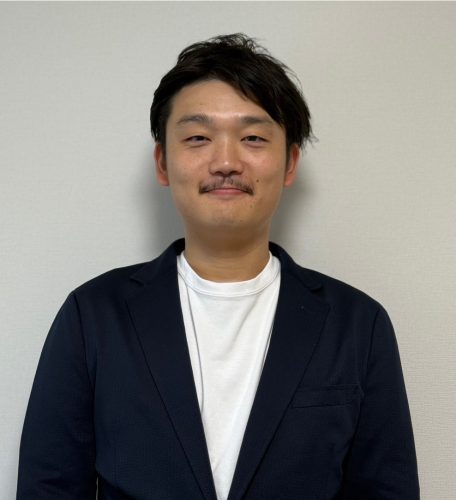
虎伏泰資教諭
目次
英語の授業でも「苦手だ」と思わせないことには力を入れる
実は、前回紹介したような帯時間を複数重ね、多くの英語をインプットしていくような授業づくりには、「英語が得意ではなかった」という子供時代から、ハワイへの留学、帰国後の大学での学びまでといった英語への関わりが大きく影響していると虎伏教諭は話します。
「私の中学校時代の英語の成績は、10段階の2や3を行き来しているくらいで、英語自体も好きではありませんでした。ただ、中学校の先生方には恵まれ、教師になりたいという思いをもってはいました。そんな中学生の頃、ハワイで単身赴任をしていた父から『ハワイに来てみないか』と言われ、『ハワイに行けば英語が話せるようになるかな』くらいの気持ちで、高校からハワイに行くことにしました。
しかし、いざハワイで生活してみると、家庭は父親との二人暮らしで日本語ですし、学校も公立高校ながら、ESL(English as a Second Language)という、英語が母語ではない子供たちばかりのクラスで、正しい英語を話しているのは先生だけという環境でした。それでも、なんとなく英語でコミュニケーションを取りながら高校時代を過ごし、話せてはいるけれども、someもanyも違いが分かっていないくらいで、文法的に得たものは皆無だったのです。ですから、ハワイで高校3年間を終えて日本に帰ってきた後、友達に『英語できるやろ?』『英語しゃべって!』と声をかけられるのがとても苦痛でした。
ちなみに、大学は中学時代からの思いがあって、教員免許が取れる大学を探したのですが、高校3年間をハワイで過ごし、数Ⅰ、数Ⅱも分からないという状況で、通常の大学入試を受けるための基本的な一般教養がありませんでした。そこで、当時はまだ少なかったAO入試で入れ、なおかつ教員免許取得可能な大学を選びました。
そのときの試験は、『英語で授業を受けて感想を書きなさい』というもので、文法に自信はありませんが、話を聞き取り、自分の意見を言うことはできました。ただし、授業の感想を日本語で書いたときに、漢字があまり書けず、ほとんど、ひらがなで書くような状況だったのです。それをおもしろいと思ってくださった大学の先生がいらして、何とか合格することができました」
そのように中学校時代の教師や大学の教授、虎伏教諭とは逆に、英語を話すのは苦手だが文法などは非常に得意な大学の同級生(現・夫人)といった人との出会いを通して、英語にどっぷりと浸り、英語の教師になったと話します。
「今も英語が好きではないのですが、英語が嫌いな英語教師がいてもよいかなと思っています。だから、『英語が嫌い』という子供がいてもよいとは思いますが、『できたら得やで』とも話しています。今の時代は、英語ができたほうが得だし、『英語に限らず、何でもできもしないのに否定するのはあかんで』と言っています。
ですから、英語の授業でも『苦手だ』と思わせないことには力を入れています。『そんなにむずかしくないで』『ほら、できたやん!』という経験を積ませるようにしたいと考えています。

言語を習得する上で、インプットの質と量が大事
授業づくりの考え方の基盤は、大学で学んだ第二言語習得論(SLA: Second Language Acquisition)が大きかったと虎伏教諭。
「自分の習得過程と比べながら、『確かに母語である日本語習得と英語習得は違うんだな』と考えました。そのような学びの中で、スティーヴン・クラッシェンが提唱した、インプット仮説には影響を受けました。学習内容は学習者の理解レベルよりも少し上のインプットを行うことが大事だという、レフ・ヴィゴツキーの『発達の最近接領域』にも通じるものです。
この仮説について批判があることも承知していますが、言語を習得する上で、インプットの質と量が大事だということは誰しも思うところだと思います。『話すことが大事』『使うことが大事』と言われますが、使うためにはそれなりのインプットを与えることが必要です。当然、インプットするためには、子供が英語を嫌いだったり、緊張があったり、発話者の雰囲気が苦手だったりしてはいけません(クラッシェンの情意フィルター仮説)。
それは、私自身のハワイ留学を通した体験とも重なります。自分自身が英語ができないという意識があるので、日本語も英語も得意な友達の前で英語を話すのがとても嫌だったのです。『こいつ、英語下手だな』とは思っていないかもしれませんが、そう思われているのではないかという不安で、話すことができなかった経験がたくさんありました。そのような思いを、子供たちにさせたくないと思っています。
そのようなインプットとアウトプットをしていく授業工夫の1つが、前回紹介したような、小さなカセットで構成していく授業になるのです」


