会社活動で主体性を育む『メタ認知と責任感の両立』

新人教員のための学級安定実践13選⑤
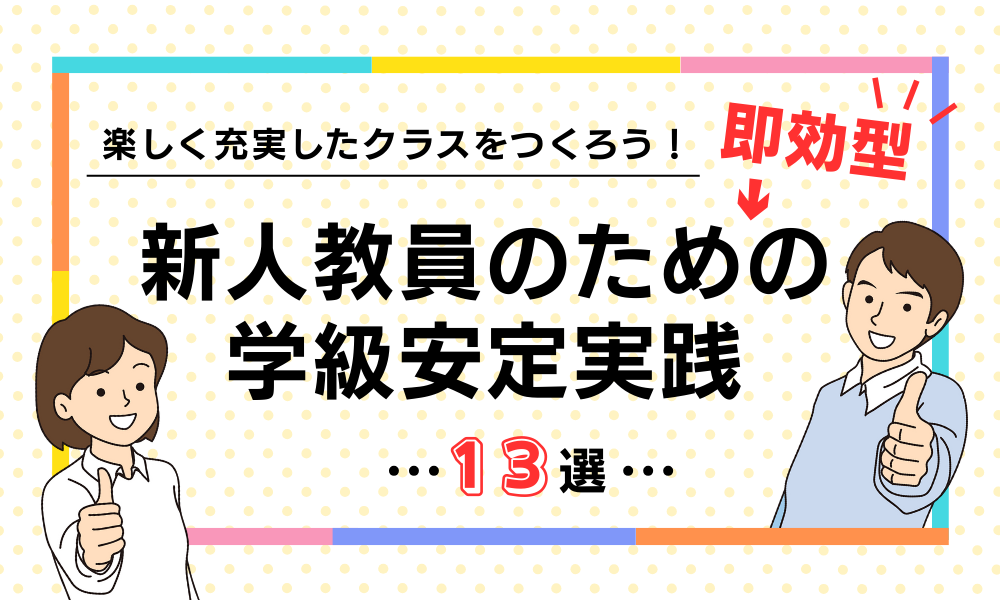
会社活動は係活動と似ています。クラスのために仕事を行うといった意味では同じです。違いは係活動はクラスのために「なくてはならない」仕事を行うものですが、会社活動は「なくてもすごく困るわけではないが、だれかが助かったり笑顔になったりする」活動、と定義しています。
会社活動は、子どもたちが自分たちでやることを決め、責任を持って参加する活動です。従来の係活動と異なり、会社活動では子どもたちがまさに「経営者」になって、活動の企画・運営・評価まで行います。これにより、単なる作業の分担ではなく、創造的で主体的な活動が実現できるのです。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
会社活動の本質:当事者意識の育成
会社活動では、子どもたちが自分の興味や関心に応じて、「自分たちの学級をより良くするために何ができるか」を考える機会を提供します。例えば、文章が得意なら「新聞会社」、ダンスが得意なら「ダンス会社」、学習が得意なら「テスト予想会社」などが考えられます。また、会社名も「掃除会社」ではなく「ピカピカ笑顔カンパニー」、「図書会社」ではなく「日本読み聞かせ推進会社」といったように、子どもたちのワクワク感を大切にします。
重要なのは、教師が活動内容を決めるのではなく、子どもたち自身が「この会社は何のために存在するのか」「どんなサービスを提供するのか」を考えることです。これにより、活動への愛着と責任感、そして何より主体性が格段に向上します。
会社設立の3段階プロセス
会社活動を成功させるには、段階的なプロセスが重要です。第1段階は「課題発見」です。「今の学級で困っていることは何だろう」「もっと楽しくするには何が必要だろう」といった問いかけにより、子どもたち自身が学級の課題を発見します。
第2段階は「会社設立」です。発見された課題を自分の得意に当てはめて解決するための会社を設立し、メンバーを決めます。この際、希望が重複してもいいです。たとえば、新聞会社が複数あっても構いません。同じ新聞会社であったとしても、扱う分野は違うかもしれませんし、分野が同じであっても書き手が違えば内容は変わってきます。
第3段階は「事業計画作成」です。いつ、どこで、誰に向けて、どんな活動を行うかを具体的に計画します。この段階で子どもたちは、自分たちの活動が他の人にどんな影響を与えるかを考える、メタ認知的な視点を身につけます。ただし、ここでのハードルを上げ過ぎては、会社設立が少なくなり、盛り上がりにかけてしまいます。一応上記のことは考えるように話しますが、実際に提出するものは「会社名、メンバー、やること」くらいの簡単なものが良いでしょう。

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

