予告を先にするトラブル回避『見通しが生む安心感』

新人教員のための学級安定実践13選④
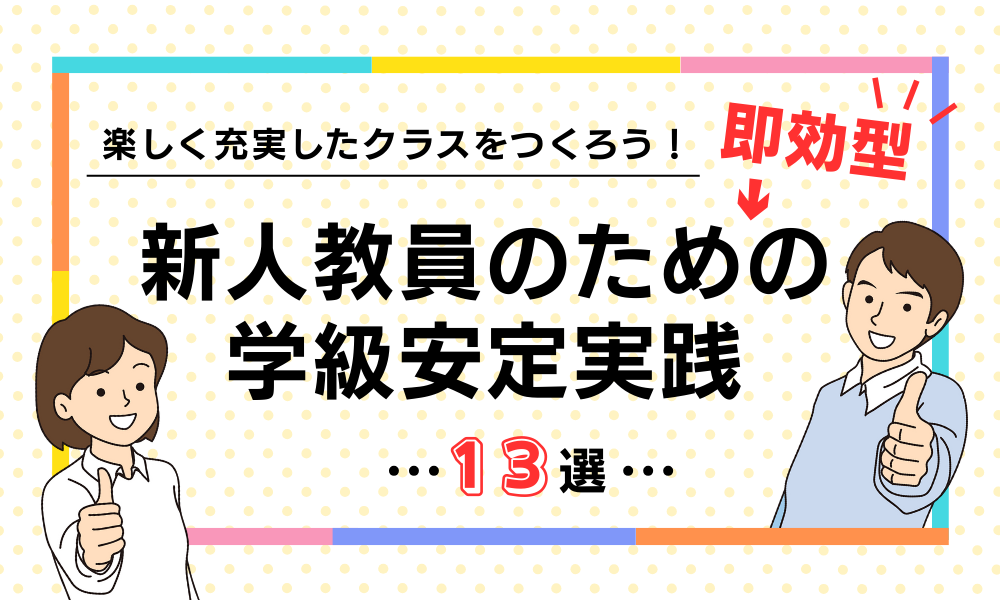
子どもたちは見通しが立たない状況に強い不安を感じます。突然の予定変更や、事前の説明なしに始まる活動は、子どもたちの心を不安定にし、時として学級全体の混乱を招きます。逆に、事前の予告と丁寧な説明により、子どもたちは心の準備を整え、スムーズに活動に取り組むことができるのです。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
予告の威力:心の準備時間
「10分後に体育館に移動します」「来週の火曜日は授業参観があります」といった予告は、子どもたちに心の準備時間を与えます。この準備時間こそが、トラブルを未然に防ぐ重要な要素なのです。
特に発達に偏りのある子や、環境の変化に敏感な子にとって、予告は必要不可欠です。しかし、すべての子どもにとって予告は有効であり、学級全体の安定につながります。「次は○○をします」という一言が、子どもたちの不安を取り除き、前向きな気持ちで活動に向かわせるのです。
効果的な予告の3つのポイント
効果的な予告には3つのポイントがあります。1つ目は「具体性」です。「後で移動します」ではなく、「10分後の10時30分に体育館に移動します」と具体的に伝えることが重要です。
2つ目は「理由の説明」です。なぜその活動を行うのか、なぜその時間なのかを子どもたちに説明することで、納得感を持って行動することができます。「体育館での練習時間を確保するため」「他の学年の邪魔にならないよう」といった理由は、子どもたちの協力的な態度を引き出します。ここでは、ダラダラと話すのではなく、端的に一言で表現することも大切です。教師の言葉は短ければ短いほど、子どもに届きやすくなります。
3つ目は「段階的な予告」です。「来週火曜日に授業参観があります」「明日は授業参観の前日です」「今から授業参観の準備をします」というように、複数回に分けて予告することで、子どもたちの準備を段階的に支援します。
変更への対応:柔軟性と謝罪
予定は時として変更せざるを得ません。その際に重要なのは、変更を直前まで言わないのではなく、早めに伝えることです。「事情があり(理由を端的に述べる)、予定を変更させてください。楽しみにしていたかもしれないけれど、ごめん」という部分的な謝罪から始めることで、子どもたちは教師の誠意を感じ取り、変更を受け入れやすくなります。こんなことで謝っていては、教師の権威が落ちるではないかと思われるかもしれませんが、それは逆です。むしろ、「期待させている気持ちがなくなり、かっがりさせてしまったことには謝る。そして、仕方のない事情について説明をして、伝えて分かってもらう」このコミュニケーションの仕方は誠実や合理的な方法であり、それを行える教師は子どもたちの良いお手本になります。
ですから、変更の理由も可能な限り説明します。「雨が降ってきたので」「他の学年の都合で」といった理由などは分かりやすく、子どもたちに状況を理解させ、柔軟性を身につけさせる良い機会となります。
予告システムの構築:黒板とプリント活用
日常的な予告システムを構築することで、予告の効果を最大化できます。教室の一角に「今日の予定」コーナーを設け、朝の会で一日の流れを確認する習慣を作ります。また、プリントやお便りを活用して、保護者にも予定を共有することで、家庭でも心の準備ができるようになります。
特に大きな行事や変更がある週は、週明けに全体像を示し、毎日少しずつ詳細を伝えていくことで、子どもたちの不安を最小限に抑えることができます。
トラブル防止
あらかじめトラブルが予想される場合は、「今日の校外学習で起きそうなトラブルを予想できる人はいるかな」と考えさせておきます。これを行うことによって、子どもたちの言葉で予告を行うことができるのです。また、それが起きないための具体的な行動目標を立てさせます。更には、それでもトラブルが起きてしまったときの対処法についても具体的に子どもたちに考えさせます。教師がすぐに解決策を提示するのではなく、子どもたちに思考させることが重要です。これを行っておけば、実際にトラブルがあっても、それは予測の範囲内のもので子どもたち自身で対応がしやすくなります。
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

