性教育って保健体育だけ? 学習指導要領からの視点【教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業】#2
小学校や中学校で性教育の指導に長年携わったスペシャリストである、帝京平成大学教授・郡吉範先生による連載「教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業」の第2回目です。この連載では、安心して実践できる基礎的・基本的なことがらやすぐに使えるヒント、ちょっと背中を押す言葉などをお届けします。第2回のテーマは「性教育って保健体育だけ? 学習指導要領からの視点」です。性教育は全教員に関わること。性教育について学習指導要領からの視点を紹介します。具体例は、郡先生の経験や現場での実践に基づくものですので、現場でのヒントにしてください。
執筆/帝京平成大学人文社会学部教授・郡 吉範
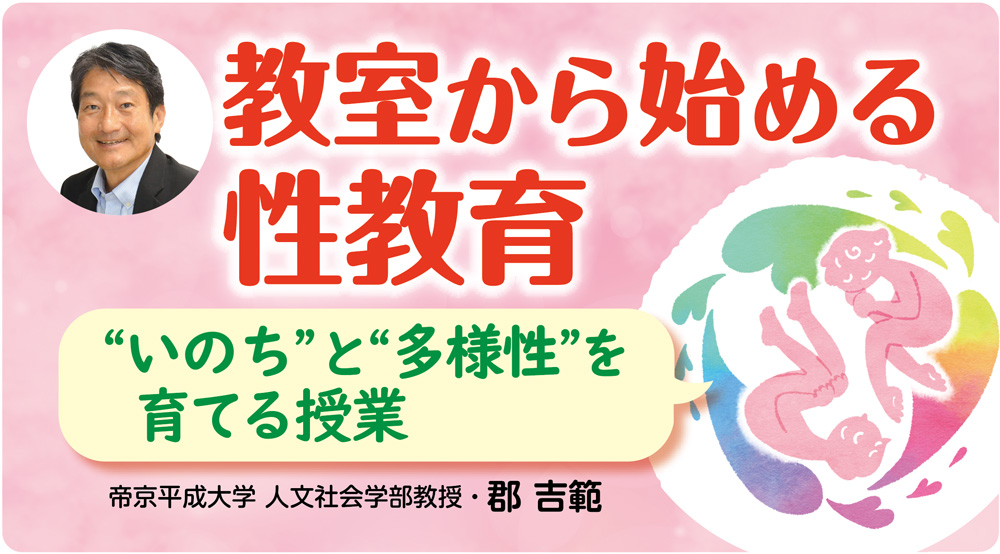
目次
性教育は“学校全体で取り組むこと”と学習指導要領に書いてある!
小学校学習指導要領の「総則」には、こんな一文があります(中学校、高等学校でも同様の趣旨)。
「心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、」
こうして読むと……思いませんか?
「ん? これって、性教育って学校全体のことじゃない?」と。
「保健体育の先生だけの仕事」ではない!
性教育といえば、「保健の先生」や「体育の先生」が頑張ってやるもの、というイメージをもっている人も多いかもしれません。でも実際は、全教員で取り組むべき内容として、学習指導要領の中にしっかりと書かれているんです。
「おお、性教育ってこんなに堂々と扱われてるんだ!」私はこの文章を読むたびに、ちょっと誇らしくなってしまいます。つまり、性教育は学校の中の一部の教科や限られた先生だけが背負うものではなく、学校全体で子供たちを支えるための大事なテーマとして位置付けられているんですね。
まず大切なのは、すべての教員がこの立ち位置を共有することです。「性教育は保健体育の範囲でしょ?」という考えから卒業して、「これはみんなで関わるものなんだ!」という意識をもつことが、何よりのスタートになります。学習指導要領も、「みんなで頑張ってね」と、しっかり背中を押してくれているんです。

あの言葉の意味を、今改めて実感する
性教育に関わり始めた頃、私が何度も先輩から言われた言葉があります。
「性教育は、全教員が関わるものだよ」
これ、ほんと耳にタコができるほど繰り返し聞きました。若い頃は正直、「またその話か……」と思ったこともありました。でも今では、その言葉の意味と重みをしみじみ実感しています。
数学も関係ある! 性教育に“無関係な教科”はない
当時はよく冗談っぽく、「でも数学科だけは関係ないよね」なんて話も出ていました。でも、今ではそうも言っていられません。例えば、性に関する統計やデータを正しく読み解く力。いわゆる“データリテラシー”は、性教育にも欠かせない要素ですよね。
そう考えると、数学の先生だって大いに関わる余地がある。むしろ、重要な役割を担っているとも言えます。
あれ、最近このフレーズ、聞かなくなってない?
最近では、この「性教育は全教員が関わるもの」という言葉自体を、あまり耳にしなくなってきた気がします。それはなぜなんだろう……と考えてみたとき、ハッと気付いたんです。もしかしてそれは、私自身がその言葉を発信しなくなっていたからじゃないか? と。
「もうみんな分かってるよね」と思い込んで、どこかで伝えるのをやめてしまっていた。でもやっぱり、大切なことは繰り返し伝えていかなければいけない。だから私は、あらためてこの言葉を自分の口からしっかり伝えていこうと決めました。
性教育は、学校全体で取り組むものです。そのためには、すべての教員が「自分事」としてその意識をもつことが第一歩です。この連載でも、そんな視点を共有していけたらと思っています(とはいえ、「全教員でやるって……何を?」と戸惑う先生もいらっしゃると思います。でも大丈夫。この連載を通じて、ヒントや具体例を少しずつお届けしていきますので、気楽に読み進めてくださいね!)。

