「フィルターバブル」とは?【知っておきたい教育用語】
学校現場でもICT端末の利用が活発になり、調べ学習ではインターネットによる検索も積極的に活用されるようになりました。ただ、子どもたちがインターネットやSNSを使って情報に接する際には、「フィルターバブル」に注意することが必要です。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
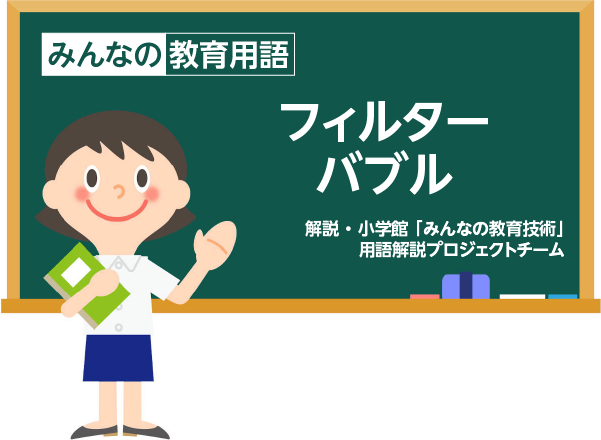
目次
フィルターバブルとは
【フィルターバブル】
インターネットの検索履歴が過去の検索に基づいて、行動や好みなどのパーソナライズを分析し、自分にとって都合のよい情報しか見えなくなってしまう現象のこと。エコーチェンバー現象の要因にもつながる。
2011年にアメリカの実業家であるイーライ・パリサーが提唱した概念で、インターネットの検索履歴が「フィルター」のように同じ情報ばかりを表示するようになり、まるで「バブル(泡)」の中にいるように、自分の見たい情報だけを取り入れるようになってしまいます。
なぜ、フィルターバブルのような現象が起きてしまうのでしょうか。その仕組みには、ウェブサイトにおける以下の3つの機能が関係しています。
●トラッキング機能
ウェブサイトを訪問したユーザーを追跡し、データを収集する。
●フィルタリング機能
トラッキング機能で収集したデータに基づき、ユーザーの好みや傾向に合わせた情報を選別する機能。
●パーソナライゼーション機能
トラッキング機能やフィルタリング機能を踏まえて、ユーザーごとにさらに個人最適化されたコンテンツを提供する機能(Amazonのおすすめ商品やYouTubeのおすすめ動画など)。
ユーザーは偏った情報しか得ないことで、無意識のうちに、特定の意見や考えだけに触れる環境がつくられてしまいます。その結果、誤情報やフェイクニュースなどが拡散される温床になってしまうだけでなく、多様な情報、価値観、考えに触れる機会が減少し、自分の考えに反するものを排除するような思想の偏りにもつながりかねません。
フィルターバブルやエコーチェンバーによる影響
総務省による2023年版「情報通信白書」によると、SNSでは自分の意見や考えに近い情報が表示されやすいことを「知っている」と回答した人の割合がおよそ4割。7~8割であったアメリカやドイツ、中国の3か国と比較して、とても低い結果となりました。また、入手した情報が正しいかどうかを検証する「ファクトチェック」の認知度もアメリカや韓国に比べて日本は低いことがわかっています。
この結果から、日本では多くの人が、SNSなどに表示される情報は自分にとって都合のよいものになっていることを把握せず、無意識に情報を受け取っていること、受け取った情報の検証が十分でないことがうかがえます。
またフィルターバブルに関連して、「エコーチェンバー」という言葉もあります。これは、SNSなどを通じて、自分と似た興味関心をもつ人々とつながり、同じ意見を見聞きすることで考えが偏っていく現象を指し、録音室(チェンバー)で音が反響すること(エコー)に例えた言葉です。
フィルターバブルやエコーチェンバーによる子どもへの影響を考えてみましょう。SNSは匿名性が高いことから、「○○人が迷惑行為を行っている」「○○人がこの国を壊す」などの悪質なデマや誤情報、ヘイトスピーチなどが散見されます。こうした差別的な言葉を、情報リテラシーが十分とはいえない子どもが受け取った場合、「大人もそう言っているから」と偏見や排他的傾向を生み出してしまう恐れがあります。
また、誤った情報やニュースの存在によって、ストレスや不安を感じるなどの精神的な発達への影響、情報を受け取ることに対して消極的になったり、関心を低下してしまったりするメディアリテラシーの低下を招くこともあります。

