登校渋りは3つの観点から適切に対応しよう! 子どもの心と命を守って、ステキな2学期びらきを!

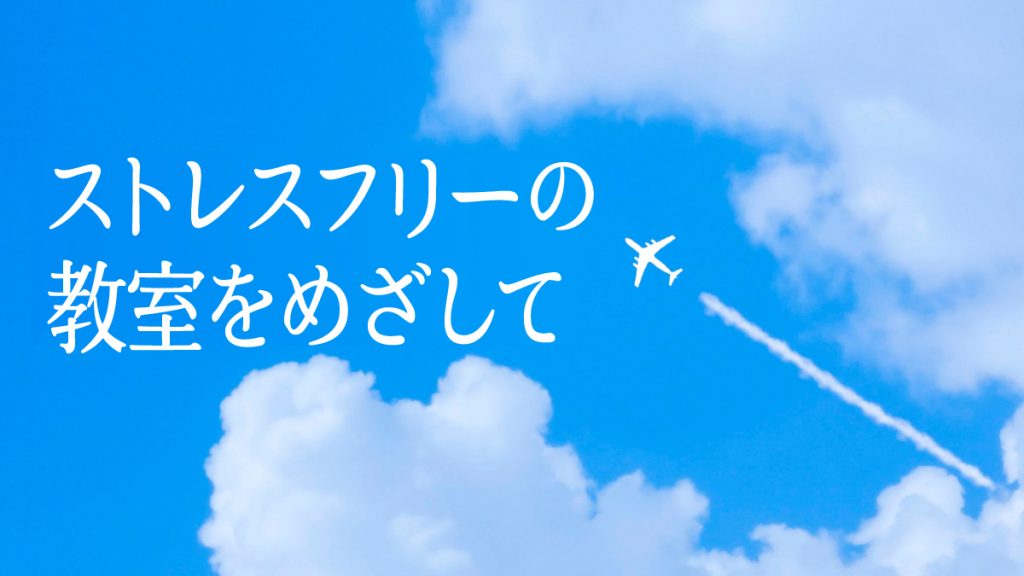
夏休み明けは、子どもの自死が年間で最も多い時期であることが、警察庁や文部科学省の統計から明らかになっています。長い休みの後に学校へ戻ることが、大きなストレスや不安として子どもにのしかかっているのでしょう。夏休み明けの数週間は、子どもの命と心のケアにおいて、教師や学校が最も注意を払うべき時期だといえます。そこで今回は、夏休み明けに増える登校渋りを、「未然防止」「早期発見」「適切な対応」という3つの観点から整理し、先生方に役立つ具体的なヒントをお伝えします。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #34
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
夏休み明けの子どもたちはどんな状態?
夏休み中の過ごし方は、子どもによって様々です。長い休みにしかできない体験活動や地域の行事に参加するなどして充実した毎日を送る子がいる一方で、ほとんど家から出ずに、昼夜逆転状態で毎日を過ごしたような子もいるでしょう。先生たちは、こうした多様な背景をもって登校してくる子どもたちと、改めて向き合うことになります。
新学期のスタートは、子どもたちにとって「もう一度、学校という社会の中に飛び込む」ようなものです。とくに夏休み明けは、4月の新学期とは異なり、「既存の人間関係への再適応」が必要になります。また、夏休み中の出来事や変化により、子ども同士の関係性が微妙に変化している場合も考えられます。
例えば、夏休みの間に「ほとんど友達と会っていなかった」「友達とトラブルになった」などのネガティブな要素があると、登校すること自体が大きな不安材料になります。友人関係のみならず、「夏休みの宿題が終わっていない」「学習内容を忘れてしまった」という焦りから、学校へ行きづらくなる子もいます。
また先述のように、夏休み中は夜更かしやゲーム漬けの生活で、昼夜逆転してしまう子もいます。朝起きるのがつらく、心身が重く感じられることで、登校への意欲が低下することがあります。これを単なる「怠け」として叱るのではなく、「生活習慣のリズムを戻すための支援が必要な状態」と捉える視点が重要です。
さらに夏休みは家庭で過ごす時間が長く、親子関係やきょうだい関係の摩擦が増える時期でもあります。親の仕事の都合で家庭内にストレスがたまったり、経済的な理由で旅行や遊びに行けなかったりしたことが劣等感となるケースもあります。よく「夏休みの思い出」などをテーマにした絵日記や作文などが宿題として出されることがありますが、到底書けるような内容が思い当たらず、これらが「学校に行きたくない」という言動の背景になっていることもあります。
子どもが登校する前に打つ一手―夏休み中に行う未然防止策―
登校渋りの未然防止策として、子どもが登校する前に打てる手もあります。
そのひとつが、ICTの活用です。近年は、夏休み中にタブレットを持ち帰らせている学校が増えているようです。もし「クラスルーム」などの機能がインフラとして活用されているようであれば、夏休みの最終日に担任の先生からのメッセージ(みんなに会えることを楽しみにしています! など)を送信するのもよいでしょう。
また、1学期から登校渋りの兆候が表れていた子どもに対しては、夏休みの終盤に保護者へ状況確認の連絡をすることも有効な手段です。「夏休みはどのように過ごしていましたか?」「お子さんの様子はいかがですか?」など、簡単な会話で構いません。もし保護者の側に懸念事項があれば、そのタイミングでお話ししてくれるでしょう。ここで学校と保護者の足並みをそろえておくことで、万が一登校渋りが継続してもスムーズに連携することができます。
新学期のスタートは「関係づくり」から―学級で行う未然防止策―
体育やスポーツを行う前には、必ず「準備運動」がありますよね? 学校生活も同じことが言えるでしょう。その意味で筆者は、夏休み明けの3日間も「黄金の3日間」だと思っています。ぜひおすすめするのは、1日10分でもよいので、「関係づくり」のためのアクティビティを行うことです。このアクティビティがその後の学校生活と子どもの学級適応を円滑にしてくれます。
とくにおすすめするのは、「構成的グループエンカウンター(SGE)」という活動です。「ふれあいと自他発見」という理念に基づくこの活動は、非常に内容が豊富であることに加え、所要時間も様々なので、学級の実態に応じてセレクトすることができます。
こうした活動に加え、ゆっくりと夏休みの思い出を語る時間をとってもよいでしょう。このとき、「全体の前で一人ずつ発表」などのルールにしてしまうと、むしろそれが負担になってしまう場合があるため、ペアやグループなどの少人数で行うことをおすすめします。
子どものSOSに気づくための「アンテナ」を高くはる―「早期発見」のポイント
夏休み明けの1週間は、子どもの心身の変化を観察する重要な期間です。以下のような小さなサインが、登校渋りの兆しである可能性があります。
- 朝の準備が極端に遅くなる
- 「おなかが痛い」「気持ち悪い」など体調不良を頻繁に訴える
- 表情が硬い、目が合わない、笑顔が少ない
- 教室で落ち着かず、友達の輪に入らない
- 宿題や提出物に過度な不安を示す
- 外見(体重の急激な増減を含む)に明らかな変化がある
- 髪を染めたり、ネイルをしたりしたまま登校している
これらのサインを「よくあること」と見過ごすのではなく、「変化の背景には何があるか」という視点で捉えることが大切です。担任だけではなく、保健室の先生や管理職とも連携して、ささいな気付きを早期に共有することが重要です。

子どもも大人も同じ気持ち―「適切な対応」とは―
万が一登校渋りの兆候が表れたときには、適切な初期対応をすることが大切です。基本的な姿勢としては「学校へ行くのが嫌だ」という気持ちを否定しないことです。

