よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第9回 研修講師の基本
指導主事には、各学校からの指導助言に加え、研修講師の要請が舞い込むこともよくあります。授業研究会における指導助言と比べて、しっかり時間をとって伝えることができますし、「瞬発力」も要しないのでプレッシャーもそれほどかからないはずです。しかし、安心してはいけません。準備を怠れば、受講者に抽象的な内容をひたすら聞かせるパッシブラーニングを強いる時間となってしまうことにもつながりかねません。このように、指導助言とは別の難しさがある研修講師ですが、今回は、そういったことに陥らないようにするためのヒントをお話しします。
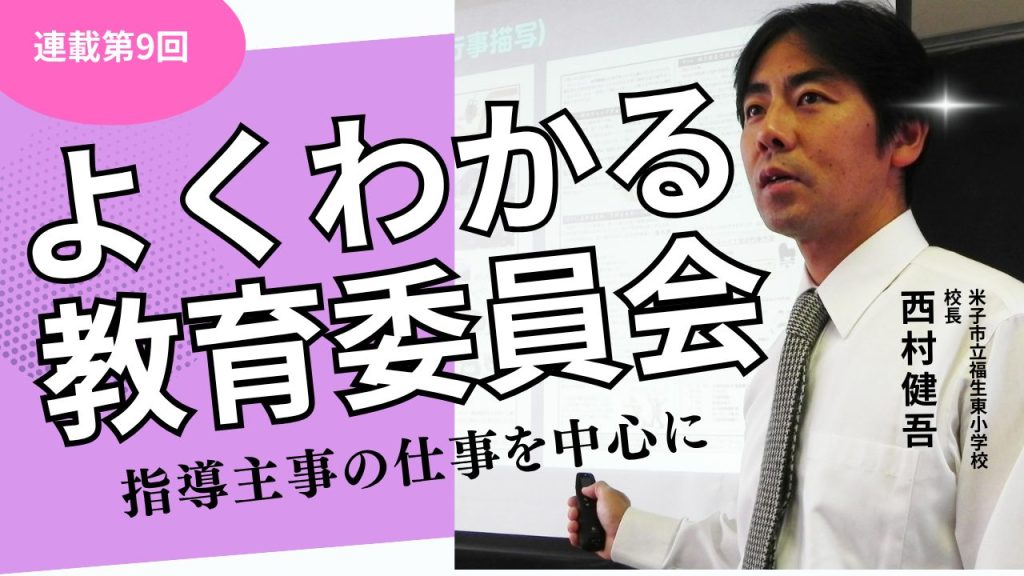

西村健吾(にしむら・けんご)
1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。
目次
研修講師の心構え
授業研究会における指導助言要請とは別に、時折、校内研修(生徒指導部会・教務主任会・小教研主催の研修等も含む)の講師依頼が舞い込むことがあります。「持久力」と「瞬発力」の双方を要する指導助言と比較して、研修講師の仕事は事前にしっかりと準備できる(「持久力」に専念できる)分、当日に冷や汗をかくことはないでしょう。
しかし、学校において子供相手に授業をするのと同様、内容の吟味や裏付け、構成や伝え方の工夫、タイムマネジメントに至るまで、入念な準備が必要です。以下、準備のポイントについて説明します。
研修の参加者を知る
まずは対象や内容のマーケティングです。研修の参加者がどんな人たちなのか、何を求める傾向にあるのかを把握するのです。リーダー層なのか、中堅なのか、若手なのか、どんな立場で働いている人なのか、あるいは同じようなテーマでの研修履歴などはいかほどか、そういった情報を集め、ニーズをつかんだうえで研修を構想します。ちなみに、可能なら知識レベルや関心事なども把握しておくと、説明手法はもちろん、ちょっとした余談や冗談を交えることにも役立ちます。
どのような情報が必要か不要かを整理し、相手の立場に立った構成を考えることが大切です。

