【特別支援教育】学級経営③「集団指導と個別指導」指導のポイントとアイデア
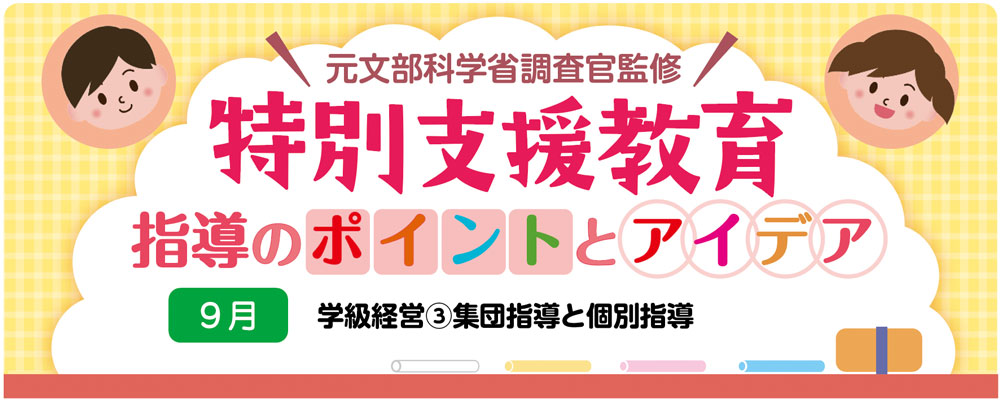
元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈学級経営③「集団指導と個別指導」〉を紹介します。集団指導と個別指導をどのように展開していけばよいか。すべての子供たちが生き生きと学び合うための授業づくりの具体的な例をお届けします。
執筆/熊本県公立小学校教諭・曽宮博子
監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子
白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授・山中ともえ
目次
特別支援教育 年間執筆計画
04月 児童理解①児童の状態の把握
05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用
06月 児童理解③児童への具体的な対応
07月 学級経営①多様性を尊重する学級
08月 学級経営②学級内での人間関係づくり
09月 学級経営③集団指導と個別指導
10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業
11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫
12月 授業づくり③ICTの活用
01月 連携①保護者との関係づくり
02月 連携②校内連携
03月 連携③関係機関の活用
【解説編】集団指導と個別指導
多様な教育的ニーズのある子供たちが通常の学級の同一クラスにいるなかで、集団指導と個別指導をどのように展開していけばよいかと悩むケースは多いのではないでしょうか。すべての子供たちが生き生きと学び合うためには、通常の学級においても特別支援教育の視点を生かした授業づくりが大切です。
1 実態に応じた指導の工夫〜キーワードは「つなぐ」〜
子供たちの実態は一人一人異なります。学習面、家庭環境、生活体験、物事の捉え方や感じ方、好きなこと、苦手なこと……すべて同じという子供は1人もいません。また、同じ1人の子供であっても、学級や学年が変わると状態が変わることもあります。対象となる子供や場面が変われば、同じ手立てで同じように効果が得られるとは限りません。一人一人の実態に応じて、授業づくりや学級経営に取り組んでいくことが大切です。
そのときに教師として意識したいのは、「つなぐ」ことです。学級は一人一人実態の異なる子供の集団です。子供一人一人の違いやよさをどのように生かすか、どのように「つなぐ」かによって、学び合いの仕方も変わります。次の例を参考に、学級における「つなぐ」場面について考えてみましょう。
自分と「つなぐ」
「学習を始める前の自分と学習を終えた今の自分を比べてみよう」「似たような経験をしたことがないかな」「未来はどんな自分になりたいかな。そのために今できることはなんだろう」など、学習内容と自分自身のなかにある学びや経験などとのつながりを意識する。
友達と「つなぐ」
「友達と伝え合おう」「○○さんが言っていること、どう思う?」「友達の考えを聞いて『なるほど』と思ったことは?」「助け合って解決できたかな」など、自分自身の学びの深まりや自信、成長が実感できるように、友達とのつながりをもつ。
教材と「つなぐ」
「他の教科で同じ言葉が出てきたね」「前の学年で学習したことと、何か関係があるのかな」「この方法は、他の学習にも生かせそうだね」など、他教科や既習内容との関連を意識し、学習内容や学び方を考える。

