スマホのルール、どう理解させる?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
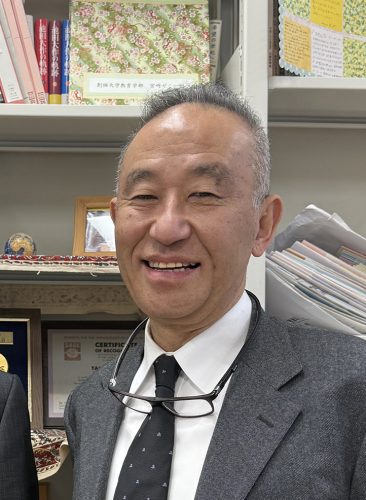

教員の指導のもと、子どもたちが話し合ってSNS利用の自主ルールづくりを奨励する自治体もあります。学校はこうした自治体とも連携しながら各家庭への周知や協力を求めながら指導しましょう。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#26
子どもたちがスマホを利用することで、どんな問題が起こる可能性があるのでしょうか? 教員として、何をどう指導していったらよいのでしょう?
スマホの保有率が高まり、ネットを介した情報流出やいじめ、問題行動などが多発しています。問題が表面化してからでは、事態はもはや深刻化している状況といわざるを得ません。学校は適切な利活用を指導していく必要があります。
目次
スマホに伴う問題、トラブルとは?
子どもたちにとって、スマホはインターネットやSNS、ゲームなど多様なコンテンツが利用できる身近で手放せないツールです。それだけに、問題やトラブルは付きもの。主に下記のようなものが挙げられます。
ネットいじめ
互いに顔の見えない状況の中で、個人や集団が特定の者を仲間外れにしたり、誹謗・中傷したりする書き込みをして攻撃します。犯罪につながることもあります。
ネット依存症
ネットに夢中になることで、次第に自制できなくなってしまう症状です。日常生活や学習活動に支障をきたすこととなります。生活習慣が乱れて不登校となり、カウンセリングや心療内科への通院が必要になることもあります。
問題行動の発信と炎上
SNSなどを通じて、悪ふざけした写真やコメントを投稿する行為です。問題行動の発信で、自身の投稿サイトが炎上するだけでなく、個人が特定されて批判を浴びる事態にもなります。在学する学校にも通報されて、学校側が対応を迫られることがあります。
個人情報の流出
SNSなどに自身や他人の個人情報(氏名や人物の画像、年齢、通学する学校名など)を自ら掲載してしまうことです。また、自身のスマホを位置情報が自動記録される設定のまま使い、撮影した画像を発信して住所を特定されることもあります。
コミュニティサイトと性犯罪
顔の見えない相手との交流は、出会い系のようなサイトだけでなく、ゲームやSNSのDM(ダイレクトメッセージ)などでも多発しています。性犯罪だけでなく、薬物などあらゆる犯罪の入り口になっているケースも多くあります。
生徒指導自治体が定めたルールとの連携
東京都教育委員会は、子どもたちがいじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれないように、また学習へ悪影響が及ばないように、「SNS 東京ルール」を策定しています。また、子どもたち自身による「自主ルールづくり」の実施を支援、奨励しています。
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

